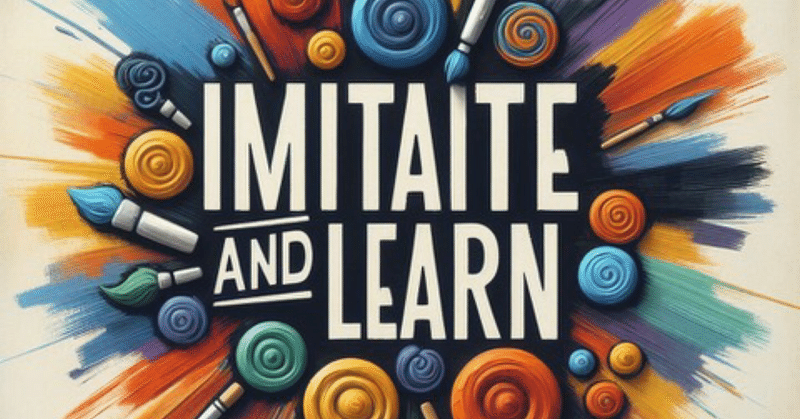
マネてマナブのはじまり
今日から5月、日本各地雨模様。
noteをはじめて2ヶ月、投稿14本ほか下書きに戻したものも。
プロフィールも投稿もブレまくりの迷走状態ですがケセラセラで行きたいと思います。
話題は生成AIについて。
たくさんの書籍や記事を探して読みながら生成AIに関する情報を習得していますが、まだまだ不完全なところがたくさんあります。
ノンプラグラマーの身でありながら、一端にプロンプトやらPythonを覚えようともしていますが、当たり前ですが一筋縄とはいかず。
つい1ヶ月前までは急がば回れの気持ちが高かったですが、こちらもブレて「急がば真似ろ」という気分になり、書籍やネットでは様々なツールやコピーを提供してくれる会社や優しい専門家の知の恩恵を探し、つべこべ考えずにまずはマネて、そこから「スゴい」と驚嘆しマナぶ順序へと移りました。
・仮装のサポートセンターが簡単にできました(コピペですが、)
・パワポ資料のドラフトが超簡単にできました(公開の無料サービスを使ってですが、)
そもそもどうして生成AIに興味を持ったかは、すでに実装してみたいことがいくつかあり、それらはこれまでだとヒトやモノやカネがある場合は別ですが、一介の小さな力では相当の根性やら努力やら地頭がないと無理と諦めていたものが、あながちシッポくらいは捕まえられる(いや、捕まえられなくとも見えるゾ)と感じたからです。
業務に置き換えると、例えば勤務シフトの作成。人力だと数時間、ベンダーのを使っても典型的パターンが主流のため個社に対しては行き届かない場合もあります。またパワポなど使った企画書やワードやエクセル資料なども今では装飾に凝るのでなく、要点を分かりやすくが求められている気がして、伝えたいことを明確にという点に関して生成AIを「味方」につけることは楽かつ深掘りもできて思考も実務にも幅ができると感じたことです。ゲームや動画までは及びません。ただ、文書や数値や画像を記録し分析し共有し、といったことに人と時間や、時にはベンダー企業に支払うサブスクともいうべき社員数分の月額利用料もいくらかは他に回せるといった効用が感じられ、余った手間はどうするかと言えば、遊ばせる・・遊ばすというのは仕事しなくていいでなく、それぞれの中に宿るさまざまな好奇心の中から新しい創造のチャンスを探る機会をもつこと、そもそも今、大きな組織こそ人間がますます機械化され、コンプライアンス×ハラスメントというフィルターの中で釣りバカの浜ちゃんも、無責任男の植木等といった薬にも毒にもなる人間キャラが絶滅危惧にある。これらは人工知能には及ばないが、人工知能にないテーストが安心感を誘う場合もあったりすると思っています。
また業務以外でも、例えば生成AIはシニアの方こそ触ってほしいツールだと思っています。これについては、昨年の暮れ77歳になる建設会社の社長さんと飲んだとき、そんな話をしたことがあります。
その方はガラケーで十分だとスマホを手に入れようとしなかったのでスマホを持つことを勧めてみました。
その方は「なぜだ?LINEもいらないし、デジカメは高価な物を持っている、YouTubeは見るがPCがある、小さな画面では見る気がしない、だからガラケーで十分だ」と頑なでした。
ChatGPTを触って欲しいから、と答えましたが、その時は私の説得力が足りませんでした。その方はご自身のことと併せ社会活動としてもACP(アドバンス・ケア・プランニング - 人生会議 - 、将来の万が一に備え、自ら希望する医療ケアを家族や医療関係者と話し合い共有しておく取り組み)に強い関心を持っておられため、ツールとしての可能性も意見交換がしたかったのがそもそものきっかけでした。
私は昨年の暮れあたり、その方だけでなく、身近にいる老若男女の人たちに(まるでChatGPTの回し者かの如く)GPT3.5を勧めましたが、そのとき、やってみたいと意思を感じた人は皆無だったと思います。「へえ」とか「1回やりました」とか、中には登録が面倒、登録したくないもいれば、その人にとっては正論と言えるアンチAIの理由で拒絶した人もいました。
今、思えば、推し進めるだけで、なぜ?の答えを私が持っていなかった。もっと理解して、分かりやすく話がしたいことが、そもそも生成AIを学ぼうと思ったきっかけかもしれません。
周囲でChatGPTをやらない理由として印象に残ったのが「何がしたいのか、何を聞けばいいのかわからない」がありました。AIとチャットができる(だけどすべてが正しい訳じゃないよね?)、AIが絵を描いてくれる(だけど思った絵を描いてもらうのもムズカシイ)と理由は色々、それよりもゲームしたり他のことに時間を使った方が有意義だと思う人はもちろん多いです。これについては、今、生成AIに関心を寄せる層は絶対数としてまだ少ないのもしれませんが、それはひとつのアドバンテージだとも思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
