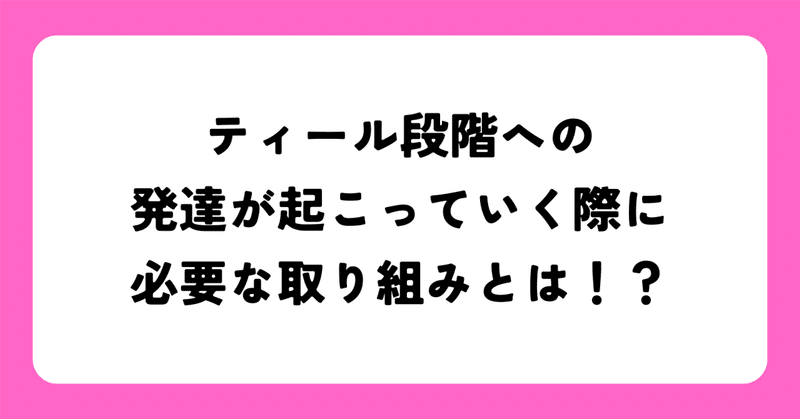
ティール段階への発達が起こっていく際に必要な取り組みとは何か?
はじめに
先日の記事ではティール段階への発達プロセスの中で起こる影の特徴について紹介しました。
今回はせっかくなのでプロセスを促進するために必要となる取り組みについても紹介したいと思います。
引用元は書籍「人が成長するとは、どういうことか ーー発達志向型能力開発のためのインテグラル・アプローチ」です。
この発達プロセスの特徴は?
「人類の意識の形態は、生まれてから成熟した大人になるまで、どのように進化してきたのか?」
歴史家、人類学者、哲学者、神秘主義者、心理学者など、多くの人がありとあらゆる角度からこの問題を探求してきました。
どの研究者の研究結果にも共通していたのは、人間性が「段階を踏んで」進化するという点です。この段階に関しては研究者の興味関心に基づいて様々なモデルが提唱されていますが、どのモデルも、注目している場所は異なる(例:あるモデルは欲求を見て、あるモデルは認知を見ている)一方で同じ山を見ているそうです。この山のことを発達段階と言えます。
「ティール」もあるモデルにおける1つの段階であり、そこに至るまでのプロセスがあります。
注)書籍「ティール組織」で紹介されている色づけされたモデル(例:グリーン、ティール)は原著者のフレデリック・ラルーが様々な研究を消化した結果が反映されているものであり、参照元の研究者が提唱している特定のモデルと完全一致しているわけではありません。
ここで紹介するのは、あくまで鈴木規夫さんの書籍で紹介されているモデルに基づくものとなります。
ここでは、そのプロセス自体がどのようなものになっていくのか?についてイメージできそうな特徴を抜粋していきたいと思います。
思考という活動そのものが構造的に内包している限界に気づき、それとは異なる方法を通じて現実と出会いたいという欲求を覚える
共同体の中で一人の個人としての「自我」を確立し、それに基づいて人生の前半期を全うすることができたときに--それまでの人生を通して成し遂げたことに対する大きな充足感を実感しながら、そして、そこにかすかな虚無感が息づいていることに気づきながら--始まる質的に全く新しいプロセス
一人の個人として、共同体に貢献するための役割や能力を獲得し、長年にわたる試行錯誤を通して、自らの存在に基本的な自信をもち、それを受容することができたときに始まるプロセス
あらゆる瞬間において、人間の体験を規定する主体という感覚--そして、そこに存在している感覚--そのものを探求の対象として眺めようとする再帰的な探求プロセス
何かを「信奉」したり、「追及」したりしている自己そのものが主たる探求の対象となる
ウィルバーはこの段階を「内向の段階」と形容しているが、それは、その主たる関心が、自己の内にひろがる巨大な内面世界を探求し、そこに答えを見出すことにあるからである。
「外向の段階」が、自らが生まれた時代や社会に与えられた脚本に基づいて生きることに集中する段階であるとすれば、「内向の段階」とは、そうした脚本の呪縛から自由になり、自己の内的な真実に基づいて生きるための格闘をする段階
「こうした「内向の段階」が始まる時期において、人はしばしば自己との対話に大量のエネルギーを傾注することになるために、周囲の人々の目にはその姿は非常に自己中心的なものに映ることがあるという」
「そのために、その姿は、「成長」に向けて歩み始めた者のそれではなく、むしろ、より自己中心的な状態に、「退行」しようとしている者のそれとしてみなされる」
それまでの人格形成のプロセスにおいて、ペルソナを形成する中で排除・抑圧されてきた感性や感情や発想が存在することが認識され、そして、それらを回復するための探求が始まる
今、目の前に存在する社会に適応するために都合のいい自己の側面や特質だけで生きるのではなく、それまでは排除や抑圧の対象とされてきたものも含めて、自己の全体性として生きようとする
適応という大義の下に断片化された自己として生きるのではなく、自己の全体性としてーーそして、自己の中に息づく真実性に立脚してーー生きることができるようになる段階
社会の中で繰りひろげられる「ゲーム」の論理に基づいて生きるのではなく、自己の内なる声に基づいて生きることができるようになる段階
人間としてこの世界に在ることの現実をーーその「不都合」な側面や要素も含めてーーありのままに直視することができるようになる段階
時代や社会の中で条件づけされた「自我」の「檻」から自由になり、この世界において人間として生きるということが本質的に宿すことになる普遍的な課題や問題に関心を移していく段階
それまでの人格形成のプロセスを通じて生み出された「構築物」としての自己と脱同一化して、あらためてこれからの自己の人生の羅針盤となり得る構想や真実を見出そうとする探求のプロセス
それまでとは質的に大きく異なる意識を創発させる発達段階
「それまでに自身を支えてくれた価値観や世界観が相対化され、自己の内に息づく心の声を聴く内省と探求の作業が大きな意味をもち始める」
「深い内的探求の重要性が顕著に高まる」
早く知りたい方のための要約
取り組みについては書籍の内容を網羅的に紹介したいと思ったので長くなってしまいました。端的に掴めみたい方はこちらだけご覧ください。要はこういうことがプロセスで必要なのね!と掴むためだけの整理です。この分類は分かりやすくするための私の簡易的分類であり、実際は心も頭も体も別々ではなく相互に関連し合っていると捉えています。
ココロ的取り組み
実存的な課題と正面から対峙する
自己の存在を深く揺さぶるのを許す
苦悩を抱擁するための耐性を涵養する
影の領域の治癒と探究
自己の存在の内に形成した偽りの「殻」や「鎧」を一つひとつ解除していく
アタマ的取り組み
衝動や欲求、そして、価値観や世界観を徹底的に精査する
特定の価値観や世界観に対する「こだわり」を相対化
「視点取得」と「視点探索」の訓練を継続
カラダ的取り組み
身体領域の探究と鍛錬
条件づけされた身体をその呪縛から解放する
(補足)
それぞれのキーワードについてもう少し詳しく知りたい方は次の段落をご覧ください。もっと詳しく知りたい人はぜひ鈴木規夫さんの書籍をあたってみてください。
プロセスでは例えばどのような取り組みが必要となるのか?
では、ここからはプロセスを進んでいく中で必要な取り組みについて触れられている箇所を抜粋していきます。
それまでの人生を振り返り、それを規定していた衝動や欲求、そして、価値観や世界観を徹底的に精査することが必要になる。
自らの生きる時代や社会が自己にいかなる影響を与えてきたのかという問いと向き合いながら、それが自己の存在の内に形成した偽りの「殻」や「鎧」を一つひとつ解除していく
条件づけされた身体をその呪縛から解放することで、それまでに抑圧・排除されていた感覚や感情を回復しようとする
例:恐れや悲しみや痛みの感覚、また、弱さや傷つきやすさ等、この世界で成功を収めていくために「克服」されるべきものとみなされていた諸々の特性。
それまでの発達の過程において、心理的主体としての自我の道具として対象化されていた体を改めて真に生き生きとした生命体として統合する
「後慣習的段階とは、その本質において、こうした自らの認識の限定性に対する自覚のうえに成り立つものである。しかし、それをこの世界における機能的な能力として発揮するためには「視点取得」と「視点探索」の訓練を継続していく必要がある」
・視点取得
他者の視点をもちながら傾聴したり、考慮・配慮したりすること
↓
厳密には2つの側面がある
(1)視点取得
利害関係者の存在を認識して、そこに配慮すべき視点が存在することを意識・尊重すること
(2)視点探索
それらの利害関係者と実際に対話をして、彼らが何を意図しているかを確認すること
それまでに自身を支えていた価値観や世界観が揺さぶられるような体験
重要なことは、物理的に外国を訪れることではなく、異質なものと出会う能力であり、また、異質なものが自己にもたらす実存的な衝撃を受け留め、それが自己の存在を深く揺さぶるのを許すこと
「実存的な課題と正面から対峙することを求められる 」
「単に優れた思考力(「システム思考」)を開発するだけでなく、こうした課題がもたらすことになる存在を貫くような苦悩を抱擁するための耐性を涵養すること」
「そのためには、それまで以上に影の領域の治癒と探究が必要となるだけでなく、また、そうした耐性を育むための身体領域の探究と鍛錬が必要となる」
→涵養(かんよう)とは初めて知りましたが「水が自然に染み込むように、無理をしないでゆっくりと養い育てること」といった意味だそうです。
自らの意識を呪縛する特定の価値観や世界観に対する「こだわり」を相対化する
影(シャドゥ)って何?
取り組みの中で重要なキーワードである影(シャドゥ)とは何か?についても紹介します。
「影とは、心理学の用語で、意識から排除され無意識化された人格の部分や側面のことを意味する」
「人生を生きる中で、時として辛い経験をすることになるが、そうしたときに経験される強烈な感情(例:屈辱・恥辱・落胆・絶望・怨念)は、しばしば意識の外に追いやられることになる。あまりにも生々しい感覚や感情を意識の中に維持したままでは、平静を保って生きていくことが難しくなるからである」
「影化する心理的特性の中には危険なものもあり、それらを抑え込むことができなければ、社会的な生活を営むことに支障を来してしまうということもある。その意味では、「抑圧」とは、この社会の中で、安易に暴力に訴えることなく、社会性のある行動をして生きていくための必須の能力とも言えるのである。」
影領域の実践とは、このようにこれまでの人格形成の過程を通じて否定されたり、排除されたりして無意識化された人格の側面や要素を意識化し、回復することで、人格をより全体性のあるものに治癒しようとする取り組み
さいごに
今回の記事では、具体的な方法論にまで言及していません。というよりも、引用元の書籍ではそれらの紹介はほとんどありませんでした。
むしろ、詳細はケン・ウィルバー(※1)の提唱する「インテグラル・ライフ・プラクティス(※2)」という実践法に任せるといった感じでした。
※1)「ティール組織」著者のフレデリック・ラルーが書籍を書く上で中心的に参照したアメリカの思想家・理論家。インテグラル理論の提唱者。
※2)インテグラル・ライフ・プラクティス
人間存在が内包する重要な領域の全てに配慮したうえで、それらを互いに関連づけながらーすなわち、統合的な態度に基づいてー探求・開発していくための方法論
ボディ・マインド・スピリット・シャドゥという4つの領域
→この網羅的な探求が必要とのこと。
その内容はこちらの書籍で扱われています。
読んだことはありますが、なかなかのボリュームの本です 汗
個人的には今後、より具体的な方法論についても触れてみたいですし、それらと過去に自身が取り組んできた経験と照らし合わせる記事を書いて理解を深めていきたいなぁと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
