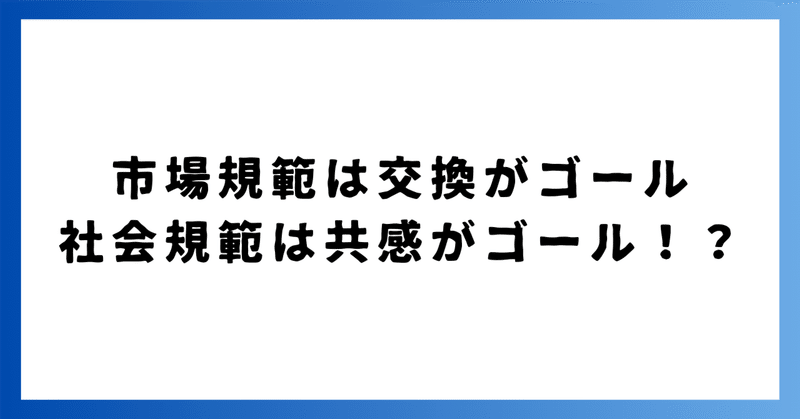
市場規範は交換がゴール。社会規範は共感がゴール!?
はじめに
最近よく読書会をやっている『タダの箱庭』本では「市場規範と社会規範」という言葉が出てきます。
この言葉は、私たちが普段生きている世界の中にごちゃ混ぜになっているという話と共に書かれており、大事なキーワードでありながら、私は今まで聴いたことがありませんでした。行動経済学の用語だそうで、せっかくなので理解を深めたいと思い、行動経済学にまつわるこちらの本『予想どおりに不合理: 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」』を買ってみました。
土地勘がないテーマなので、何が名著なのか分かりませんが、まずはベストセラーに手をつけてみようということで選んでみました。
ということで、今回の内容はこの書籍から学ぶ「社会規範と市場規範」となります。
社会規範と市場規範とは?
それぞれの用語に関連して書かれている内容を抜粋し並べてみます。
社会規範とは?
・友だち同士の頼みごと
・私たちの社交性や共同体の必要性と切っても切れない関係にある
・たいていほのぼのしている
・即座にお返しする必要はない
・社会的交流の特徴をもつ
・社会的交流においては、何かまずいことが起きても、相手方がそばにいて、自分を守り助けてくれると人々は信じている。契約書に明記されているわけではないが、必要なときにはお互いに面倒を見たり手を貸したりするのが一般的な義務だ
・一緒に何かをつくりあげる興奮
・社会規範が忠誠心を育てる(企業において)
・社会規範は人々を奮起させる。柔軟で、意識が高く、進んで仕事に取りかかるという、企業が今日必要としている従業員になろうと努力する気にさせる
・職業への誇りや義務感
・何かが社会のものになったとたん、わたしたちは社会規範の領域へといざなわれ、他者と共有するための決まりごとに従うようになる
・社会規範は人々に他者の幸福を思いださせ、その結果、利用できる資源に負担をかけすぎない程度まで消費を抑えさせる
市場規範とは?
・ほのぼのしたものは何もない。賃金、価格、賃貸料、利息、費用便益など、やりとりはシビアだ
・独立独歩、独創性、個人主義も含まれるが、対等な利益や迅速な支払いといという意味合いもある
・支払った分に見合うものが手にはいる
・市場的交流の特徴をもつ
・昇進ごとにだんだん増えていく給料など
・考えのなかにいったん市場規範がはいりこむと、社会規範が消えてしまう
この2つの規範をべつべつの路線に隔てておけば、人生はかなり順調にいく、とのこと。一方で、この2つが衝突すると、社会規範が消えて、市場規範が残るそうだ。そして、問題が起きてしまう、とのこと。
また、
・やりとりに金銭が絡まないとなると、かならず社会規範がついてくる
・値段がゼロで社会規範が問題になっているとき、人々は世界を共同体のものとしてとらえる
・値段を持ちださないことが社会規範をもたらし、社会規範があることでわたしたちは他者のことをもっと気にかけるようになる
・やりとりを金銭の絡まない不明瞭なものにすることは可能であり、そうすることで、社会規範の利点を踏みつぶすのを避けられる
・わたしたちは、やりとりに金銭が絡まない場合にのみ、自分の行動の社会的影響を考えはじめる
・社会規範で動いている状況に金銭を持ちこむと、意欲が増すどころか減ってしまう
と似た表現が何度も言葉を変えてでてくるくらい、やりとりに私たちがお金だと思っているものがからむと市場規範が登場する、とのこと。
思ったこと「市場規範は交換がゴール、社会規範は共感がゴール?」
書かれている事例を読んでいく中で、市場規範と呼ばれるものは何のやりとりだろうが、「交換」が満足のための必須のゴールの1つになっている一方で、社会規範は「交換」が必須でもゴールでもなく、「共感(感情を共有できている状態)」が満足のための必須のゴールという意味で作法が全く違うもの、という捉え方のイメージが湧きました。これは私の解釈であり、本の中で書かれている表現ではありません。(最後まで読み切ってないですが)
行動経済学という前提の上で使われている用語がゆえに、勝手に社会規範も交換モデルで、何を交換しているかによって市場規範と社会規範を分けてるのかな?と思っていたのですが、あくまで現時点での理解度ですが、違いましたね。
よくドラマや漫画などで「これ、私の気持ち」というようにおまけをしてくれるシーンなどがありますが、そのコミュニケーションの時にやりとりしているのは目に見える物のやりとりがされているとしても、それ自体では決してなく、見えない領域の分けられない感情ということなのですね。言い換えれば、重心は見えない領域にあるということ。
一方で、市場規範は実際の物、あるいは物理的に見えないとしても、分けられていて、所有できる「モノ」に重心があるということ。
そしてこの2つは、コミュニケーションの時の2つの状態「共通理解」と「共感」に似ているかもしれないと思いました。
この2つは「一緒にやる!」を相手が力を最大限発揮してくれる形で実現するための重要な土台となります。
「共通理解」とは、文字通り、特定の事柄に対して共通の理解ができた状態のこと。言い換えれば「私が思っていることを相手に正確に理解してもらったと思える」状態と言えます。
しかし、話している中で「言っていることは理解できるけど・・・何かスムーズじゃない、軽やかにいいねとならない」あるいは「確かに言っていることはそういうことだけど、伝わっている気がしない・・・」ということはありませんか?これは、「共通理解」は至れているが、より土台にある「共通感情」略して「共感」に至れてないために起こる現象なのです。
(この「共感」に至れていなくても、仕事や家庭などで相手を動かすことはできますが、「共感」がないと、どんどん乾いた土のようになっていきます)
この「共感」とは、一言でいうなら「私が感じていることが相手にも伝わったと私に感じられている」状態と言えます。
この状態は、単純化していいますが、思考チャンネル(言葉でやりとりする)だけでは至れません。感情チャンネル(感性・エネルギーでやりとりする)ことが必須です。言い換えれば、片方の感情チャンネルが閉じていると至れない状態となります。
この話と、2つの規範がどのくらいつなげられるかは、もうちょっと考えてみないとですが、両者のギャップは「共通理解」と「共有感情」のギャップに通ずるものを感じた次第です。
さいごに
今回、行動経済学で言われている市場規範と社会規範について書きました。
それぞれの質感について自分なりに理解を深めることができたのは大きな収穫でしたし、特に社会規範への理解が深まったことで、以前からイメージしつつもなかなか解像度が高まらなかったもう1つの規範(あえてこの言葉にしてますが)がクリアーになってきたと思います。もうちょっとで言語化できそう。
おまけ
「タダの箱庭」読書会の感想、気づきなど書いている記事はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
