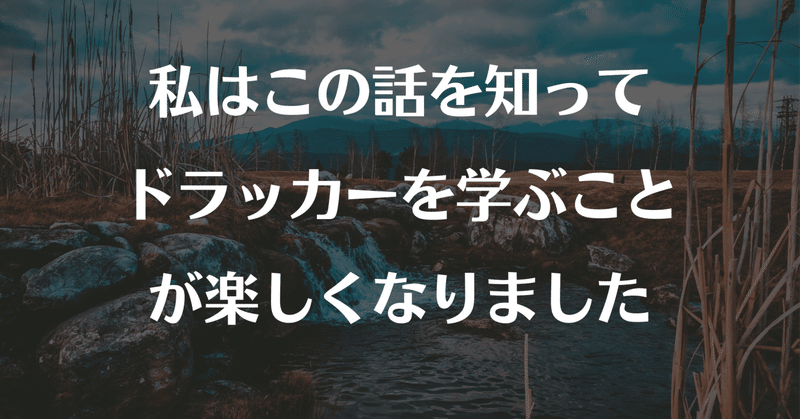
ドラッカーの著作群を通底しているテーマとは何か!?
はじめに
過去、「マネジメントの父」と名高いP.F.ドラッカーの書籍から「マネジメント」を学ぶために分厚い著書を手にとった時は内容が難解だと感じられて挫折しました・・・。
その後、2013年頃に仕事でドラッカーの著作群に再度触れる必要が出てきたのですが過去に挫折したこともあり不安を感じたことを覚えています。
ですが、あることがきっかけとなり、自ら関心を持ち彼の膨大な著作を読み進めることができるようになり、挫折するどころか、どんどん興味が湧いて仕方がないという状態になりました。
何がきっかけでドラッカーへの興味が爆発したのか!?
それは、ドラッカーのあることについて共感したことがきっかけです。
「なるほど!そういうことだったのか!」
その感覚が芽生えたときに「もっと知りたい!」という興味と好奇心が湧き上がったことを覚えています。
そのあること、というのは彼自身が問い続けた終生のテーマについてでした。
ドラッカーの関連本は「仕事での成果の出し方」について書かれているものが書店でも多くならんでいますが、それは彼のメインテーマではありませんでした。むしろ、会社は利益のためにあるのではないとさえ断言していました。
そんな彼が終生掲げていたテーマ、問いは何かというと『社会的存在である人間の真の幸せはいかにして実現されるのか?』であったのです。
そして、ドラッカーはその答えを「〜イズム(主義)」ではなく「マネジメント」に見出しました。
組織において適切なマネジメントがなされれば、その組織に関わる人々は、真の幸福を実現することができる、と。
また、ドラッカーはモデルとすべき組織像を2つ示しました。
その1つがNPO型組織であり、もう1つが古き良き日本型経営でした。
彼は、日本美術を愛していた背景から日本を訪れ、盛田昭夫さんら戦後復興期の若きリーダーに出会い、その思想・経営哲学に深く感銘を受けたそうです。
私は、彼の終生の問いについて知った時にものすごく共感しました。というのも、私自身、同じ問いを持っていたからです。
そして、急に親近感が沸くと共に、彼の著作の根底を流れるストーリーを感じました。
ストーリーを感じたからでしょうか。今まで無味乾燥に思えた「マネジメント」を始めとした彼の著作郡が急に生き物のように感じ始めたのです。
その結果は、最初に書いた通りです。むさぼるように読み進めました。
もし、ドラッカーを学びたいが足踏みされている方がいたら彼の背景について知ることから始めてみてはいかがでしょうか。
おまけ1:オススメ本の紹介
その背景について知るにはまずこちらがオススメです。文量も多くなく読みやすいです。
その他、個人的にオススメなドラッカーの書籍について紹介します。
●ドラッカー自身についてのオススメ本
→上記の100分DE名著のより詳細バージョンという感じ。読書体力が相応には必要とされるのでまずは書店で手に取ってみるのがいいかもしれません。
→ドラッカーが自身の半生を振り返る自伝なのですがとても面白いです。お婆さまのエピソードなど心動かされる箇所がありました。
●ドラッカーのコンサルティングについて迫った本
→あまり知られていないですが、ドラッカー思想の経営現場での実践について触れることができる他にはないタイプの本です。内容の濃さと読みやすさという点でもオススメです
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
