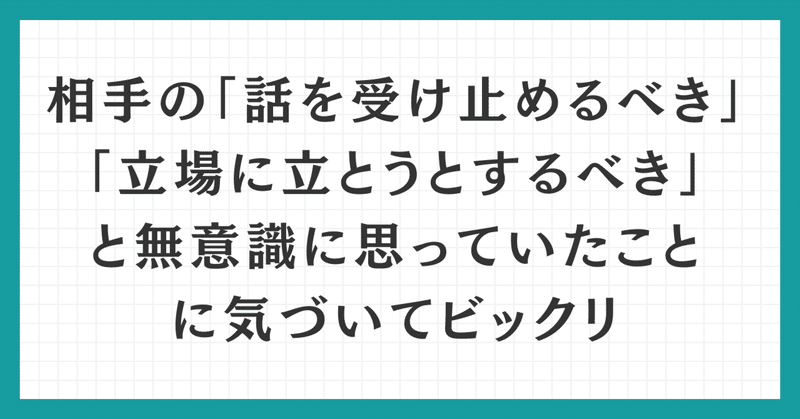
相手の「話を受け止めるべき」「立場に立とうとするべき」と無意識に思っていたことに気づいてビックリ。
はじめに
最近、どのくらいぶりか分からないレベルで久しぶりに、人間関係でのモヤモヤで自身で紐解くところまでいけないことがあり、友人に相談にのってもらいました。
そこで友人から教えてもらった傲慢なコミュニケーションというものがあります。そこで大きな気づきがあったのでそちらについて書きます。
傲慢なコミュニケーションとは?
聴いた話を無理やり?4象限にしてみた図がこちら。

ちょっとごちゃごちゃしちゃっていますが、この4象限は、自分の言ったことを①相手がどう受け止めるのか?②どう行動するか?といった2点において、自分の望むようにすべきだと思っているか、相手に委ねる・任せるかという2つの極があることを表しています。
左下「傲慢1」
傲慢1というのは、受け止め方も行動も伝える側の望むようにすべきというコミュニケーションのことを指します。会社でいう上司部下の関係で起こりやすいことかと思います。
右下「傲慢2」
傲慢2というのは、自分の言ったことに対して相手がどう動くかについては委ねる・お任せができているけど、言ったこと自体をどのように受け止めるか、については望む受け止め方があり、そのようにすべきだと思っているコミュニケーションのことを指します。
左上「傲慢3?」
教わった時には出てきませんでしたが、4象限にすると生まれるこの象限も傲慢なコミュニケーションのうちの1つとなりますね。ここは、言ったことに対する受け止め方は委ねる・任せるですが、どう動くかについては望む動き方があり、そのようにすべきだと思っているコミュニケーションになりますね。この象限についてはどういう時にあるか?が今のところ浮かんでいませんが、4象限にしちゃったので置いています(笑)
右上「傲慢ではない(どういう表現になるのだろう?)」
傲慢さ、という観点でいうと2つの軸で委ねる・任せるができているのが右上の象限となります。
自分のことで気づいていなかったこと
この話を聴いて気づいたのは、自身が右下の傲慢2になっていることが多いということでした。
具体的にいうと相手に対して「私の話を受け止めるべき」「私の立場に立ってみようとするべき(私の捉え方では、共感的という言葉はこの姿勢を指します)」といった無意識の望みを持っていたのです。
だからこそ、親しい友人との間で、特定のコミュニケーションになると「話を受け止めてもらっていない」と感じ、少なからずイラッとしていたのでしょう。
そしてこれは違う観点でいうと、私が私にこの2つを強いているからこそ、親しい友人にもその正しさを適用してしまっていたということでした。
いやぁ〜、これは気づかなかったですね。。。
まさか、「話を受け止める」「共感する」が「すべき」「正しさ」という偏りになっていたとは。
ここでいう偏りとは、自由自在ではない、という意味合いで使っています。自由自在であるということは、「話を受け止めない」「共感しない」ことにもちゃんと位置を与えることができている、選ぶことができるという状態を指します。言い換えれば、あくまで私にとってですが、より全体性を取り戻せている状態と言っていいでしょう。
いや〜、無意識に「話を受け止めないこと」「共感しないこと」は良くないことというか、ネガティブなこととセットになってしまっていたんですね〜。
最近の自分のテーマの1つに、「エッジ(境界線)を明確にする」「所有しているものをちゃんと所有する」というのがあるのですが、この「話を受け止めない」「立場に立とうとしない」ことのメリットがこのテーマにつながってくるなぁと思えて、その点でも興味深い気づきです。
さいごに
確かに大きな気づきでしたが、これで変わった!と思うつもりもなく、まずは気づいたことで感じられている新たな体感覚にじっくり浸ってみたいと思います。
「話を受け止めてもいいし・受け止めなくてもいい」「立場に立ってもいいし・立たなくてもいい」そんな両極を自身のものとして感じられるようになることが大事なことかなぁ。
まだ、人間界に関するモヤモヤの相手への具体的なアクションを見つけるまでには至っていませんが、その前段階の内的なジャーニーは友人のおかげでぐっと自力ではいけないところにいけた感覚があり、その意味で前進できてよかったです。改めて、友人へ感謝です!
ちなみに、長らくコーチ的に活動していたり、普段から、傾聴力・共感力が高い人たちと接することが多かったり、そもそも自身が人の話に対して「そうありたい」という想いもこの盲点に気づきにくかった要因かもしれません。
これは安易な一般化ですが、今回私が気づいたような「受け止める」「共感する」ことに関する傲慢さは、コーチ・カウンセラーといった役割を担っている方などにとっても盲点になっている=パワーを取り戻すチャンスポイントなのかもしれない、なんて思ったりもしました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
