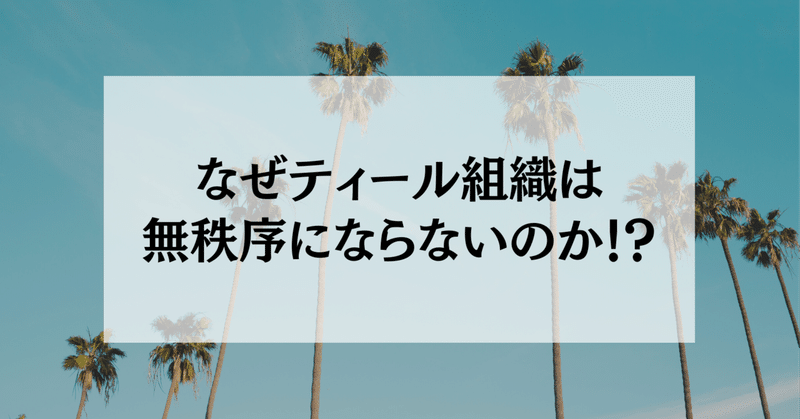
なぜティール組織は無秩序にならないのか!?〜●●システムの働き〜
はじめに
2021年に書いたメモですが、ティール組織について深めていくプロセスでの気づきは、今のタイミングでも役立つ人がいるのではないか、と思ったため、ほぼそのままにして投稿したいと思います。
ちなみに今回扱う自己修正システムとは、書籍「ティール組織」では言葉としては登場していませんが、フレデリックいわく自主経営の核心にあるのが、自己修正(self-correcting)というぐらい重要なものとなります。
ここが分かると「ティール組織は無秩序なんじゃないの?」とコメントが誤った理解に基づいたものだと分かります。
当時関わっていたコミュニティでの出来事
私が当時、関わっていたオンラインコミュニティ"手放す経営ラボ"では書籍「ティール組織」著者であるフレデリック・ラルーによるINSIGHTS FOR THE JOURNEYという動画を日本語訳していただいた記事を1つずつ投稿し、それに対して有志で気づき等をコメントし合うという取り組みをしていました。
その中で生まれたやりとりで興味深い気づきを得たのですが、そのきっかけとなった記事はこちらです。(ちなみに本記事は以下のリンクを読まなくても分かるように書いています。)
この記事を読んで私が気になった箇所と感想
・気になった箇所
『私がそれ(※)に代わって望むのは、何かが機能しない場合、人ではなく、システム自体がすばやく問題を検出し、自己修正できるような制御メカニズムです。それは、免疫システムに似ています。』
※そこで働く人が嫌なメカニズムを使って人を制御しようする古い制御メカニズム
・私の感想
ここでいう制御(コントロール)メカニズムって何だろう?と思った時に浮かんだのは管理会計と情報の透明化でした。
ㅤ
自分のいる事業部の売上がある値を切ったら、自身の収入が下がる、あるいはボーナスがもらえなくなる、そういった状態が日々見える化されている、かつ、組織の財布と自分の収入がつながっているという実感がある場合に「このままではまずい」という自己修正システムが働く。裏を返せば、その実感もない、数字の見える化もされていない、という状態で経営者が色んなものを手放しても無秩序になるだけ。
ㅤ
実際、ティール的組織の先駆的実践企業だったダイヤモンドメディア社(現在は社名が変わり、経営スタイルも変わっています)では2010年頃に社員に「好きな働き方をすればいい」と言って収拾がつかなくなった時期があったそうです。
「5、6年前くらいに、社内のみんなに好きな働き方をすればいいじゃんと言って、やりすぎて本当に収拾がつかなくなった時期があったんです。その頃は、物事すべての中心に「自由」を据えてやっていたんですけど、結局はそれが一人歩きしてしまって。
そこで、外部のパートナーだったら「採算合わないから契約を切る」という選択もできますが、雇用関係があって社内で一緒に仕事していたり、雇用関係がなくても内部の人として仕事していると、一方的に切ることってできないじゃないですか。組織として一体化しているわけなので。
でも、一体化しているはずなのに好き勝手に働くっていうのは、本当は一体化していない証拠ですよね。この帳尻をどう合わせるのかというのを考え抜いた結果、そこからは合理的な経営システムを導入していくことにしたんです。」
※武井さんの実践知は進化しており、上記に書かれているのはあくまで2016年当時のものだということをご了承ください。
その結果、管理会計を徹底的に整備したり、アメーバ経営を取り入れたりしたそうです。
ㅤ
そう考えると、会社の利益と自分の利益が一致し続けることを目的とするのが自己修正システムの主旨なのでしょうか?
この翻訳記事だけを読んだ時点では私の感想はこの問いで終わりました。
ラルー氏の記事を翻訳してくれた方からのコメント
そんな私の投稿に対して、合計131本に及ぶラルー氏の動画のうち、約100近くを無償で翻訳してくださった小林範之さんがコメントしてくれたんです。
自己修正、もしくは自己修復システムは4項に渡って出てくる、とても重要で難しい概念です。ここでは心理的安全性を含めたホールネス、当事者意識、それらがきちんと機能していれば、自己修正システムは機能する、そうでなければ自己修正システムも機能しない、という捉え方になると思います。
例えば、雑草という名前の草はないといったような自然農法の中に、いきなりプラスチック製品が放りこまれたところをイメージしてみてください。
中央集権的な組織では何か問題が起こったら、大騒ぎして、すぐにマネージャーが現場に駆け付け解決を図ろうとします。また、その解決手法や結果によってマネージャーは評価され、力はマネージャーに集中していきます。そして組織全体は、問題が起こるたびに規則が一つ増え、一段階、風通しが悪くなります。
これに対し自律分散的な組織では何か問題が起こったら、まず、果たしてそれが本当に問題なのか、解決すべきことなのかが問われ(放っておいてもいいかもという選択肢)、そこで本当に、見過ごせないという当事者意識のある人がアドバイスプロセスを立ち上げます。そこで話し合われ解決に向かうさまが免疫システムに似ているとラルーさんは言っています。
いっしーが言っている、メーターのようなもの、これも立派な免疫システムです。
私がこのコメントを読み感じたことは、この免疫システムに似た自己修正システムを機能させるために必要な前提条件にはどんなものがあるのか?ということでした。
当時の私は、
(1)情報の透明性を高める仕組みといったシステムが整っていること
(2)問題が起こったときに「それが本当に問題なのか?解決すべきことなのか?」という問いが浮かび立ち止まる力、本当に見過ごせないという当事者意識(言い換えれば、私が取り組む・取り組みたいという意志)に気がつける内省力、といったものが少なくともそのチームの主だった習慣となるレベル(それを組織文化と呼びたい)で育まれていること
が必要不可欠な要素なのではないかというメモを残しています。
自己修正システムを機能させるための3つの原則
このテーマについてフレデリックは動画シリーズの中で自己修正システムを機能させるための3つの原則について話しています。
その1つ目は心理的オーナーシップです。
組織のメンバーが抱く感情のことであり組織や仕事に持つ当事者意識を指します
2つ目は組織のメンバーが仕事の結果(痛みや誇りなど)を直接体験できるシステムです。
組織の誰もが仕事や行動の結果を直接体感すること
シンプルに言い換えると組織の全員が直接仕事に伴う痛みと誇りを感じる必要があります
より具体的に3つの要素が紹介されています。
①チーム全体として何が健康な状態なのか、統一見解を持つ
②データによる絶え間ないフィードバック
③データに基づく対話の機会を持つ
3つ目は、誰もが変化を起こす権限を持てることです。
動画シリーズでは少なくとも4本の動画に渡って自己修正システムについて語られていますので詳しく知りたい人はぜひご覧ください。
さいごに
最後に紹介した3つの原則を眺めてみると、特に2つ目、3つ目は機械的と言われるオレンジパラダイムの組織に見受けられる要素のように思えます。
これは言い換えれば、組織の進化が決して何段階も飛ばして起こるものではなく、「適切な順番がある」ということでもあるなと。
こういう記事を書いておいて何ですが、フレデリック自身が動画で言われているように、ティール組織というコンセプトを目指すのではなく、今感じている個人的な痛みは何か?から始めることが、改めて大事だと感じます。
今回に関連するテーマについてまた違った切り口で書いた記事がありますので深めたい方はぜひご覧ください♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
