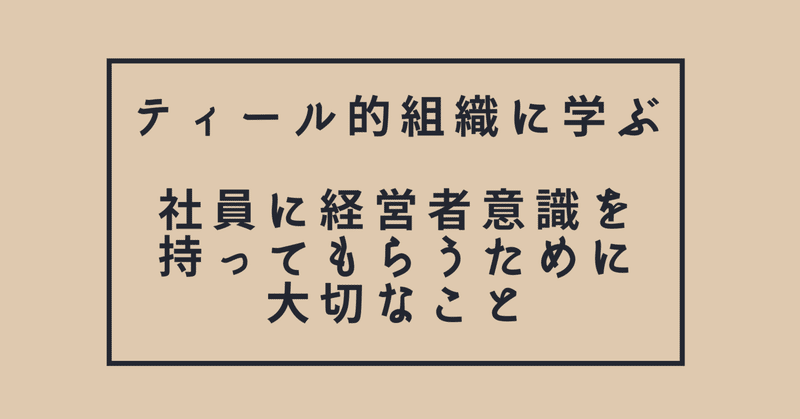
「当事者意識を持とう!」と言ったり教育し続けようとするよりも●●を整えた方がいいかもしれません
はじめに
私は仕事柄、いろんな組織に関わるのですが経営層の方と話していてよく話題にあがるのが社員やスタッフとの目線の違いについての話です。
先日話をした経営者の方ともそういった話になりました。「同じ目線、意識を持ってもらいたいけれど、なかなか持ってもらえない。そのギャップを埋めるためにはどうしたらいいか」ということで、研修を企画しようとしていました。
もちろん、「こういった意識を持とう!」と啓発したり体感型の教育も大切だと思うのですが、他にも重要な視点があるということを紹介したいと思います。
当事者意識について
書籍「ティール組織」が出版されるよりも10年近く前から先進的な経営を実践されてきたその分野のパイオニア的存在である武井浩三さんがこのテーマに関連してよくいうことがあります。
当事者意識は与えること、渡すことができない
当事者意識は当事者しか持てない
これをそのまま組織に置き換えるならば、経営者としての意識は経営者しか持てないということになります。
経営者がなぜ会社全体に当事者としての意識を持っているか。
それは、例えば
・意思決定権を持っている
・自分で責任を取れる(痛みを直接感じることができる)
・プロセスに主体として関与できる
という権利を持っているからと言えます。
言い換えれば、これらの条件を社員自体も持てるようにすれば、社員は当事者になり、結果として当事者意識を持てるということなのです。
事例紹介
例えば、愛知県で上記のようなスタイルで経営されている店舗があります。
そこでは、店長がいないため、クレーム対応はそれを生み出したスタッフが最後までやらなければいけません。クレーム対応は決しても気持ちがいいものではないですし、絶対避けたいですよね。その痛みを味わうからこそ、スタッフは自らを成長させようと思うようになります。その結果、クレームはほとんど出ないどころか満足度が高くなっています
また、同じようなスタイルで経営されている北関東にある別の会社はクリーニング屋さんをやっています。
その店舗は繁忙期と閑散期があるのですが、閑散期が続くと気を抜いてダラダラするそうです。しかし、油断が続くと急に忙しくなり、残業が続くことになります。そんな状況であっても経営チームは手伝いません。店舗の人によって起きたことは店舗の人がどうにかするしかないのです。実際に、取り返しつかないくらい生産現場が崩壊したこともあったそうですがそういった機会を経て、自由と同時にある責任を自覚し、自分たちで自主的に話し合い、立て直しをはかるとのことです。
環境を整えること+大事なこととは?
先に会社において経営の当事者であるためには
・意思決定権を持っている
・自分で責任を取れる
(痛みを直接感じることができる)
・プロセスに主体として関与できる
といったことを伝えしました。
そういった環境を整えることが重要となりますが、それだけでは足りません。合わせて大切なことは「心理的オーナーシップを育む」というものです。
これは、プロセスを通じて成長するものなので環境が変わればOKということではなく、体験・関わり合いが必要ということです。
このもう1つの要素について私が最近思うことがあります。
それは、他責の前に無責という段階の人がいるのではないか、ということです。
そもそも責任がある立場にいることに無自覚ということ。そんな状態の人が何か出来事があった際に不平不満を言ったとします。
その際にニュートラルに「じゃぁ、あなたはどうしたい?」と質問することはその人の責任ステータスが無責から他責に変わり、自責(言い換えれば当事者)としての意識を育んでいける道がスタートする、ということだと思うのです。
そして、こういった関わり合いをコツコツ行っていくからこそ、環境で用意されているさまざまな機会を活用できるようになっていき、当事者であるという自覚を持つ位置に立てるのだと捉えています。
さいごに
今回は、当事者としての意識を持つということに関して昨今話題となっている経営スタイルを例に出しながら紹介しました。
実際はもっと色んな要素が有機的に結びつきながら成り立っていますが、理解が深まるきっかけになれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
合わせて読みたいオススメ記事はこちら。
(1)事例で紹介している愛知にある店舗型ビジネスでの実践について経営者自ら語っています
(2)事例で紹介したクリーニング屋さんについて詳しく触れています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
