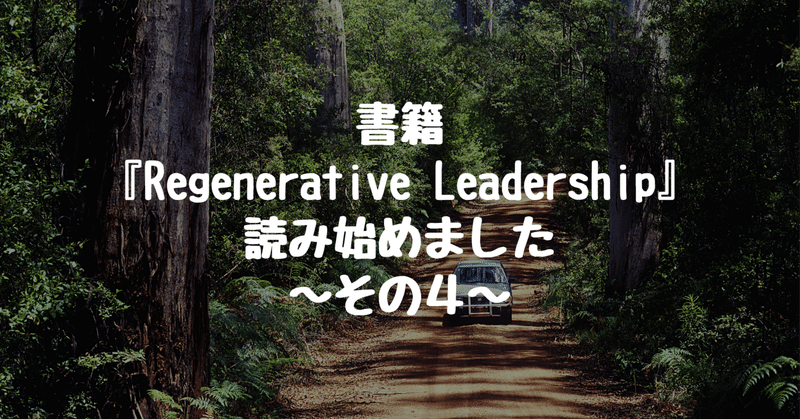
「Regenerative Leadership」Chapter4を読みました
はじめに
書籍「Regenerative Leadership」を友人たちと読み進めています。前回からだいぶ時間が空きましたが(このセリフ2回目です 汗)続編となるChapter4"A New Regenerative Model Based on The Logic of Life(生命の論理に基づく新しい再生モデル)"を読んで感じたことを書きます。
前回の記事はこちら。
Chapter4の内容pick up
原著をDeepL翻訳を用いて和訳した文をピックアップしています。
・あらゆる分野のリーダーに求められているのは「再生の時代」への移行です。
・科学革命、産業革命、技術革命で学んだこと、適応したことと、自然の叡智から学ぶことを結びつけることが、人類の次の進化のステップなのです。つまり、機械論的な分析や高度な技術革新と、自然界の洞察や生態系への配慮を統合することです。後者を取り入れるには、自分自身、お互い、そして周りの世界との関わり方を新しくする必要があります。私たちは、自分自身の内なる自然(自己意識)と外なる自然(周囲の自然環境)とのつながりを取り戻さなければなりません。
・私たちは人間らしさを取り戻し、生き方、社会、組織を「Logic of Life(生命の論理)」に基づいて再構築しなければならないのです。
・私たちが自分自身や他人、そして世界に与えた内外の傷を認識し、個人的・集団的レベルで私たちの人間性の抑圧された部分と和解するのです。
・ありがたいことに、この癒しのプロセスはすでに始まっていることを示す証拠があります。
※書籍で紹介されているものから一部抜粋
ヨーロッパ中の小学生がストライキや行進を行い気候問題について世界の指導者に行動を求めている、オーストラリアとアメリカにおける先住民への公式謝罪、持続可能な開発目標へのほぼ全世界的な支持と参画・・・
・先住民の知恵は、現代社会と自然界との調和を図る昔のやり方との間に橋を架けるのに役立つ。
・人類学者のマイケル・ハーナーは、さまざまな先住民族の文化を研究し、何千年にもわたって、世界中の地理的な位置に関係なく、文化の間で思考、信念、実践に著しい一貫性があることを発見しました。地域や大陸に関係なく、自然と調和し、その叡智を敬う生き方は同じだったのです。ハーナーは、世界中で見られるこれらの古代の実践に内在する共通性を表現するために、コア・シャーマニズムという言葉を作りました。
・コアシャーマニズムの原則は、すべてのものはエネルギーでできていて、すべてが相互につながっていることを説明しています。この概念は、科学革命の台頭とともに、私たちの世界観から追放されました。自然界との相互接続の代わりに、人間は自然界から切り離されたビットやバイトに注目するようになり、やがて還元的な分析的、左半球的な処理方法は、生命そのものに関わる参加型の方法から我々を遠ざけたのです。
・20世紀に入ってから、アインシュタイン、ボーア、プランク、ネルンスト、シュレーディンガー、ボームといった新しい科学者たちによって、この整然とした機械論的世界観は破られ、それぞれが、すべてを包含する場の存在を証明する発見をしました。今日、多くの人がこの場を「量子場」または「ゼロポイントエネルギーフィールド」と呼んでいます。この本では、このフィールドが生命のすべてに浸透しているとして、「リビングシステムフィールド」として参照します。
・リビングシステムフィールドを認識することは、人類が「再生の時代」の中に戻ってくるための鍵
・成人発達理論では、この回帰を「Tier 1(第1階層意識)」から「Tier 2(第2階層意識)」への移行として認識しています。
・私たちは、ゼロから出発しようとか、森の中に戻って狩猟採集民として小屋で暮らそうなどと言うつもりは毛頭ない。いや、全く違います。私たちがリジェネラティブリーダーたちに求めているのは、古代の理解や自然の知恵を活かした生き方を取り戻し、現代の科学的知見や技術的発明と融合させることなのです。
・生命の仕組みを理解することは、私たちが内外のネットワークに活力を与える組織文化を創造する旅に出る際に、非常に重要なこと
・生命を統合的に理解するために、私たち(著者)は多くの著名なフレームワークや原理原則、科学的研究を参考にしてきました
→ジェームズラブロック、レイチェルカーソンなどの科学者・環境保護主義者、システム理論家、複雑系理論家、パーマカルチャー、ゲーテ、人類学と自然科学に関する研究など・・・
・Logic of Life7つの原則
(1)生命を肯定する(生命は、生命を助長する条件を創造する)
(2)変化し続ける&適応的
(3)相関的&相互接続的
(4)相乗効果&多様性
(5)周期的 &リズミカル
(6)エネルギーと物質の流れ
(7)リビングシステムフィールド
Chapter4を読んで感じたこと
・Logic of Lifeの7つの原則の1つ目である「生命を肯定する」という箇所で生物学者、Janine Benyusの言葉『すべての生命は、より多くの生命を育む』という言葉が紹介されていました。私はこの章ではこの言葉が最も響きました。その理由は、この言葉を問いに変えるだけで日々の生活に活かせる行動規範になると思えたから。「私のこの行動はより多くの生命を育む方向につながっているか?」
・著者の主張が「原始的な生活にかえろう!」というものではなく、現代の科学的知見や技術と統合するという姿勢に共感。
Logic of Lifeの7つの原則のうち、実感した経験があると思えるものをピックアップしてみた
振り返ってみて全部を紹介するとなると膨大な量になることが分かったのでいくつかだけ紹介します。
「周期的 &リズミカル」を実感したタイミングとは?
ここでいう「周期的&リズミカル」というのは、言い換えれば「展開→成長→手放し→内省→更新→展開」といった四季のような周期的なリズムのことを指しています。
私が「季節だけではなく特定の物事にはサイクルがある」ということを知識として初めて知ったのは20代半ば頃にマーケターの神田昌典さんの書籍に触れた時だったように思います。神田さんと西洋占星術士の方がコラボレーションすることで生まれた「春夏秋冬理論」と呼ばれるものでした。当時は面白がって今の季節は何だろう?と調べていましたが、活かすに至りませんでした。他にも、算命学・四柱推命に触れたこともありました。実際にみてもらったこともありますが「ふーん」という感じで終わり、その後も興味を抱くことなく今に至っています。
一方でサイクルとして実感し活用しているものがあるとすれば、現時点では2つあります。1つ目は、コーチの平本あきさんという方が提唱されている「人生の3つの時期」というモデルです。詳しくは過去に記事化したのでそちらを読んでいただきたいですが、すごく簡単にいうと私たちは人生の中で「歩く時期」「走る時期」「止まる時期」というサイクルを繰り返しており、それぞれの時期において適切な行動が変わるというものです。
上記の記事を書いたのは2020年の4月ですが、まさにその時期は止まる時期であり、その時期に適切だと言われる考えるよりも感じるを実践していました。その後、サイクル通りに進んでいきましたし、今ではこのサイクルの通りに生きることが自然だと感じています。
また、上記のモデルと合わせて活用しているのが、この書籍でも何回も引用されている「U理論」です。
U理論とは?
過去の延長線上ではない変容やイノベーションを個人、ペア(1対1の関係)、チーム、組織、コミュニティ、社会のレベルで起こすための原理と実践の手法を明示した理論
(こちらのサイトより引用)
「人生の3つの時期」の1つである「止まる時期」に適切な行動は、しっかり立ち止まること・考えるより感じる・自身を掘り下げるといったことがあるのですが、この時期にU理論のアプローチを活用することでまさに過去の延長線上にない変容・進化を人生に起こしてきました。
最後に個人レベルではなく組織に関するモデルを紹介します。活用しているわけではないですが、当てはまっていると実感したものです。それは、有名な書籍「ビジョナリーカンパニー」シリーズの3冊目である、『ビジョナリー・カンパニー3 衰退の五段階』です。
5段階とは?
第1段階:成功から生まれる傲慢
第2段階:規律なき拡大路線
第3段階:リスクと問題の否認
第4段階:一髪逆転策の追及
第5段階:屈服と凡庸な企業への転落か消滅
とある組織にいた時に途中から明らかな衰退を感じたことがありました。その時にたまたま見つけて当てはめてみたところ、あまりに同じ段階を辿っていたので驚きました。市場がグングン伸びているフェーズだったからだと思いますが「1から5にいく寸前くらいまで」に1年しないうちに到達したのは、渦中は大変でしたがとてもいい経験でした。
「エネルギーと物質の流れ」を感じたタイミングは?
ここでいう流れには色んなレベルがあると書かれています。主には生物学的なレベル、組織というシステムというレベルに関してです。
私が組織というシステムにおいて流れを感じた機会はいくつかあるのですが、ここではネガティブな意味の流れが弱くなった経験について紹介します。
40名規模ぐらいのスタートアップにいた時のことです。私は営業部門に所属していました。規模が急拡大していき、営業部門だけが丸ごと新しいオフィスに移りました。
その後、売上が低迷した時期に何とか回復させるために、それまで出席できていた全社会議よりも営業のアポイントが優先されるようになったり、スケジュールの組み方自体も余白がなくなり、仲間とのちょっとした雑談の時間も取れなくなっていきました。
その結果、本社との流れが弱くなったように感じ、全社の中では営業部門が、営業部門の中でもチームごとに、孤立したような感覚になっていったのです。また、私もその状況になって数週間経ってから明らかに自身のエネルギーが枯渇しやすくなったと感じました。もちろん、やることはやるのですが、組織の中で自然と得られていた燃料を自分の人生から持ってこなければいけないという感覚でした。この感覚が続くと、明確な意志を持って働いている人の場合は組織が自分が得たい経験が得られる限りは所属し続けますが、それが満たされたり得られないことが分かった時点でやめてしまうだろうなと思いました。実際に、ハイパフォーマーも何名か辞めてしまいました。
おわりに
今回も前回同様に読んで感じたことが浮かばず、筆が進まなかったのですが「Logic of Life7つの原則」を自分の経験と照らし合わせてみるというideaが浮かんでから一気に進み、こうして記事をupすることができました。
友人たちとの読書会自体は、来週で最後のchapterを迎えるのですが記事はまだ8つ残っています(汗)はたして最後まで書くことができるのでしょうか。。。気負わず頑張りたいと思います。
長文最後まで読んでいただきありがとうございました。
続きはこちら
これまでの記事も読んでみたくなった場合はこちらから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
