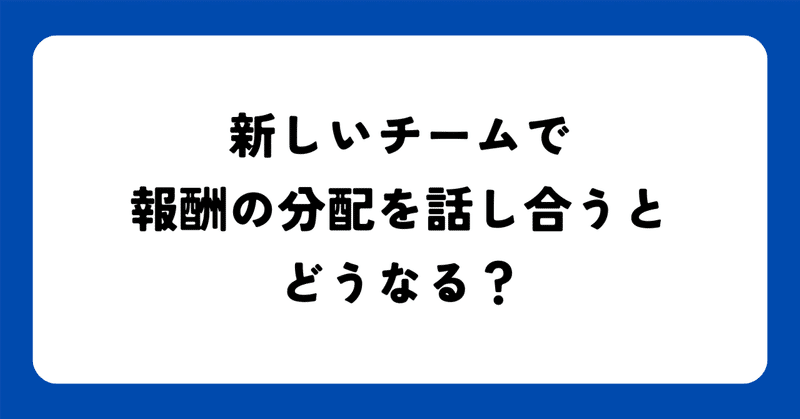
新しいチームで「報酬の分配」を話し合って決める中で気づいたこと
はじめに
ティール組織(進化型組織)が話題に上がる際に、「給料を自己決定する」という制度が注目されるケースは少なくありません。今回は、数年前に私自身がとある自律分散的な組織において予算のついたプロジェクトの報酬分配をチームメンバーで行ったときの気づき・学びについて書きたいと思います。
<前提情報>
その組織では、経営ロールを担っている人がその期限つきプロジェクトの原資を設定してくれていました。
チームの人数は5人で。発起人でありプロジェクトマネジャー的な人が2人とメンバー的な人が1人。そして、今回を機に新しく私ともう1人の人はそれぞれのプロマネが声をかけたメンバーでした。
ただし、この組織ではマネジャーの方が偉いといった上下関係はなく、あくまでロールを担ってくれているという前提があります。
どうやって分配するか?
私がプロジェクトに正式に参加してから数ヶ月かけて成果物ができあがり、納品が完了しました。
その結果、予定通りの報酬が提供されることになり、それを分配するフェーズになりました。このフェーズで考えるべきは「どうやって分配するか?」です。また、プロジェクトマネジャーはいましたが最終の意思決定権は誰が持つのかについては明確にしないまま、かといって問題が起こるわけでもなく進んでいました。
分配を決める方法については、私がネットで見つけた先達にあやかり、以下にすることで合意形成ができました。
【シェアリングバリューシステム タスク決定方式】
1.はじめにタスクの大項目と小項目を決め、全体を100として各タスクの比率を決定する。
(基準となる報酬額が自動計算される)
2.誰がどの程度の割合で仕事をしたかという評価を決める。
(評価の数値が入ると、メンバー各自の報酬が自動計算される)
3.全員が入れ終わった時点で、調整期間を設け、各メンバーより意見を聞きつつ微調整する。
4.調整期間終了後、その額が決定額とされる
1.についてはプロジェクトマネジャーの1人が大項目と小項目案をつくってくれたので、それを見たチームメンバーがアイデアが浮かべばフィードバックすることになりました。私はその案を参考にしながらプロジェクトを振り返り、自分なりの大項目と小項目を立ててみました。
その結果、私が出した代案は「成果物に直結したと私が主観的に感じられる項目を評価する」という価値観に基づくものになりました。プロジェクトマネジャーの案は「プロセスすべてを評価したい」という価値観に基づくものだったことから、対極にあると言ってもいい案が並びました。
そこから少し話し合い、タスクの項目及び比率を調整した上で、メンバー全員が「2.自己評価」を行いました。私はその後のプロセス及び、金額についての最終決定はプロジェクトマネジャーの2人に委任することにして、そこからは報告を待つことにしました。
なぜそこからのプロセスを任せることにしたのか、というと最終的な意思決定基準が決まっていないかつ、プロジェクトにおいて何を評価されるべき仕事と捉えるかという認識が異なる2人が、対等な立場で話し合い続けても平行線を辿るだけだと目に見えていたからでした。もちろん、納得いくように話し合うことはできたかもしれませんが、
・仕事観や前提などが異なる、かつ知り合って間もなくプロジェクトを一緒にやることも初めてであるその人と、どう話し合えば円滑におさまりがつくのかイメージが湧かなかった
・そのプロセスにおいてお互いに疲弊し、人間関係が悪くなってしまうんじゃないか、という懸念もあった
・そもそも、このプロジェクトに誘ってくれたのはその人であり、ここで自分が納得したいという我を通す場面ではないと思った。むしろ途中から加わった身としてここまでさせてもらえて有り難いくらいと感じていた。(プロジェクトの種自体は私が関わる前からこの人を含めた3人がコツコツ育ててくれていたのでそういう意味では感謝しかありません)
といった理由もあり早々にお任せすることにしたのです。
自分の中に生まれた"ある感情"に驚く
数日後に、最終決定した内容が共有されました。結果としては、合計を人数で割った金額が分配されることになりました。要は給料一律ということです。
個人的に興味深かったのは、自分に割り振られたフィーと他の3人のフィーに対してはそのような感情が湧かなかったのですが、ある1人のメンバーにも同じフィーが支払われるという最終決定をスプレッドシート上で見たときに私の心が大きく動いたことでした。
その感覚を言語化すると「え?なんで同じなの?」という感じでしょうか。
というのも、その人は他のメンバーと比べて明らかに仕事量が少なかったからです。また、仕事の内容も思考力が必要な上流工程というよりは振り分けられた作業をやってくれていたというのもありました。
仕事量が少ない、業務内容もタスクレベルがメイン。シンプルにいえばその評価に納得がいかなかったんでしょうね。
自分への評価は納得しているのに、他人への評価にも納得感を求めてしまう、という心理が興味深いなぁ。
このあたりは今改めて振り返ってみると、早々に意思決定を委任してしまい、本当はどうしたいか、を伝える(ここまでは自分でコントロールできることだったのに)をしなかった、このもう一歩踏み込まなかった自分へのモヤモヤが溢れた、ということだったのかもしれません。
ちなみに私の心が動かされた、その人自身はその結果を見た時に「そんなにもらうほどやっていないのでこの金額は辞退したい」と自ら言われていました。最終的にどうなったかは知りません。
振り返り
上記の経験を経て気づいたこと。
(1)「何を仕事と捉えているのか」「その仕事をどのように評価するのか」それは多くの場合バラバラである。この2つの目線を合わせるには相応のエネルギーがかかる。特に、当人が考えたいと思っていない中でやるのは余計ストレス。疲労感が増す。経営者志望やティール組織に強く興味がある!という人以外はほとんど頑張る動機がないと思える。
(2)多くの場合お金のことをざっくばらんに話すことに慣れていないため、テーマがお金というだけで感情が大きく動く。(特に感情を抑圧しがちな社風の組織だと直接関係がない過去の感情のエネルギーも吹き出しやすい。)また、内面のことを踏み込んで話すこと自体もそういう文化が形成されていない中ではもう1つの大きなハードルとなる。
↓
裏を返せば、上記の前提が整っていれば給与の自己決定をスムーズに進めることができると言える。
さいごに
「ティール組織」原著者のフレデリック・ラルーは自主経営組織の給与について語っているこちらのビデオの中で、
給与制度はいつ考え始めればいいのか?という問いに対するアドバイスとして次のように話しています。
私からのアドバイスは “後でいい”です
私としては先に他の成功を 収めることを勧めます
まず自主経営を 機能させましょう
組織を成熟させるのです
お金に関することは 皆に負荷がかかります
組織が最大限に成熟したら 取りかかればいい
早い段階で取りかかれば 厄介な問題を引き起こしかねません
「先に他の成功」「組織を成熟させる」とありますが、実際に現場に入ってきた中で感じることは給与の自己決定といった目を引くような制度だから話題になりますが、実際に現場に即した形を考えると、土台としての全体性(ホールネス)を整えること、その上で自主経営(セルフマネジメント)の仕組みを整えること、という適切な順番(厳密には完全に順番というより重なりながら取り組んでいくイメージ)があるのだとつくづく感じます。
それらの取り組みは言い換えれば、振り返りで紹介した (1)(2)の条件が整っていくということだと捉えています。
前提条件は揃っていなかったものの、当事者として体験できたのはよかったので、クライアントの支援に活かしていきます。
関連記事
給与の自己決定とは直接関係はありませんが成熟していく、とはどういうことなのか?プロセスを垣間見ることができるのでオススメ記事です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
