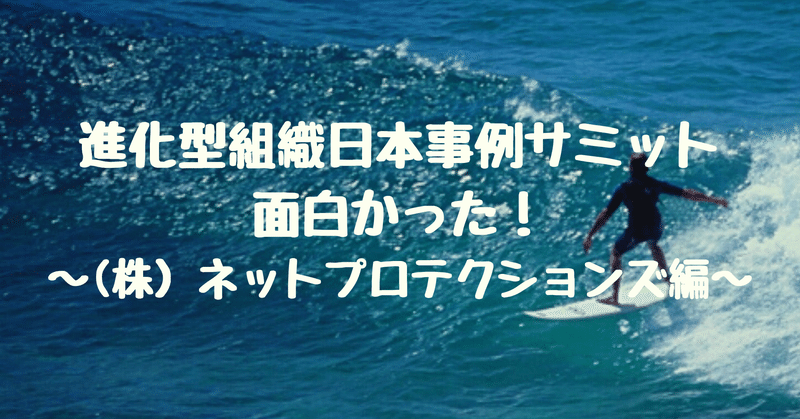
進化型組織日本事例サミットに参加したら面白かった!〜その2〜
はじめに
先日参加した進化型組織、日本事例サミット(NPO法人 場とつながりラボ homes'vi主催)の感想レポート的記事、その2です。その1はこちらから。このサミットが開催された意義・意味もすごく大事だと感じているのでまだの方はぜひご覧ください。その1ではGaiax社の木村さんの発表について書いています。
今回は、2社目のネットプロテクションズについて書きます。
ネットプロテクションズ執行役員 秋山瞬さんのお話し
2000年に設立され、昨年東証一部への上場も果たしたネットプロテクションズに2009年に人事として入社された秋山瞬さんがお話しされました。プロフィールはこちらです。
慶應義塾大学卒業後、設立2年目の人材系スタートアップ企業に新卒1期生として入社。ベンチャー企業の経営幹部層に特化したヘッドハンティング・人材紹介に従事。新規事業の立上げや関西支社設立にも携わった後、「次世代を担うリーダー創出」を志し、2009年に株式会社ネットプロテクションズの人事として参画。2017年、執行役員に就任。新卒・中途採用や人材開発・育成、理念・ビジョン策定等幅広い業務に携わり、2018年には、マネージャー職を廃止した人事評価制度『Natura』導入を推進。事業・組織双方でミッションである「つぎのアタリマエ」づくりを目指す。
1.印象に残った秋山さんの発言
( )内は私の解釈に基づく補足です
(上場のプロセスについて)
・全社員に上場することや、今どういうフェーズにあってどんな動きをしてるのかもオープンにしていた。上場プロジェクトも手挙げ制でチャレンジできるようにした。
・証券会社や東証の審査の際に、理解してもらうのにかなり時間がかかった。(部署間で)兼務していたりすると部署同士の牽制によってガバナンスを効かせることが難しいという話になる。そもそも何がどう働いていればガバナンスと言える?→こうだから兼務していてもガバナンスがとれているんですという説明工数に時間がかかりました。一方で、1つ1つ説明していくと理解してもらえて、審査は通っていける。プロセスとしてできたのでよかったのかな。
→上場についてはこちらで詳しく書かれていました。
自律・自走できる人が幸せになる組織ってどういうのだろう?を突き詰めていった。
共有していただいた特徴
①ビジョンシート
全社員のキャリア観やビジョンを半期に1回シェア。
②ワーキンググループ
社員が主事業の他に20%のリソース(つまり週一日)を使ってまったく異なる業務に参加できる制度。やっていく中で、(比率が)50%、80%になることもあるように変化して行った。
③マネージャー不在で上下関係なし
人事評価制度「Natura」
④あらゆる戦略は組織全体で議論
半期に1回、事業や組織にまつわるロングミーティング。100人規模もしばしば行われる。
⑤情報共有
ログにいたるまで徹底的に開示する文化
⑥活躍するための基礎づくりは会社で提供
法務、IT/データサイエンス、財務、思考・議論プロジェクトマネジメント
中途は最近増えてきている。条件というよりその人と働きたいと思ったか。ネットプロテクションズの環境にいたときに違和感がないかをベースにしている。部署や人によって基準自体が変わってくる。
2.賢州さんコメントで印象に残ったこと
10社あれば全部違う。これが進化型組織の面白いところ。
オレンジは、簡単にいうと現場の代わりに経営者がなんとかやる。現場の代わりに間接部門がやる。役割を分化させることによって仕組みを回す。もう1つが責任者を置く。数値目標を果たせなければ。部長は課長に結果責任を求めると結果責任を一人ずつ置いていく発明をした。安定的にやるには抜群だった。オレンジによって人が疲弊したりイノベーションが生まれにくくなる弊害があった。
それと違うやり方として生まれたのがティール。よくある誤解が、マネジャー全部取っ払ったらいいんですね。組織には専門的な仕事、幅広い視野の仕事の2つがある。(全部取っ払ってしまうと)幅広い視野の仕事をする人がいなくなるのでそれによってバラバラになったりうまくいかない構造になる。両方できるようにしていきましょう。さらにいうとそこに結果責任と命令責任をおかない。現場が主役の中で幅広い仕事で活躍する。組織において1人の場合もあれば、分業するパターンもある。あくまで責任を持つのは現場。
【引用】どのように組織は移行していったのか?
お話を伺って、プロセスも気になったので調べたところ、マネージャー不在で上下関係なしという人事評価制度「Natura」の導入がスムーズに進んだ背景には土壌づくりとも言える様々な取り組みがありました。2つの取材記事を引用しながら無理やりまとめてみました。
よく「制度リリースしてから大変だったでしょ」と言われるのですが、実はそこよりもリリース前に約5年かけて地道に社内文化をつくってきた時の方が大変でした。
NPの創業からこれまでをフェーズ分けすると、以下4つに分けられるのですが、ちょうど③の変革期にあたる時のことです。
① 創業期(2001年~2007年)
② 拡張期(2008年~2012年)
③ 変革期(2013年~2016年)
④ 飛躍期(2016年~)
引用記事はこちら。
(1)移行の土壌その1〜MVVの策定及び採用について〜
典型的なヒエラルキー組織として戦い抜いてきて、社員が50名近くになった2013年頃に、必要性を感じ、全社員をチームに分けて約1年近くかけMission・Vision・Valueをまとめあげていく。
↓
他にも新しい取り組みをスタートさせ始めた約2年ほどで、ビジョン策定に関わった社員の内、半分近くが辞めてしまう。
今だから話せることですが、当時は内心かなり焦りました。また、退職者の中には創業期や拡張期といった苦しい時代を一緒に戦ってきたメンバーもいたので、精神的にも本当にしんどい期間だったように思います。
引用記事はこちら。
↓
辞める人を止めるのではなく、ビジョンに共感してくれる人の採用をがんばることへマインドを再セット。
組織の半分の仲間を失う。そんな大きな変化を受けても、ブレずにこの組織改革をやり通せた背景にあったのは、「つぎのアタリマエをつくる」という会社のミッションでした。
引用記事はこちら。
ビジョンに共感した方だけが残ったことで、その後のカルチャーの浸透度は急激に高まりました。会社の採用方針や発信メッセージが定まり、当社のカルチャーにフィットした人材を採用できるようになった結果、新卒の定着率も24%→90%超まで改善することができたのです。
引用記事はこちら。
(2)移行の土壌その2〜マネージャーの意識改革〜
Naturaでマネージャー職を廃止する前段階として、③の変革期に組織を「逆三角形型」に変更したことがありました。具体的には従来の組織図を正反対にして、「マネージャーはメンバーのwillを叶える人」と定義し直したのです。マネージャーに求められるものが180度変わったため、ここで辞めてしまった方も正直います。
(3)移行の土壌その3〜横断的な関係づくり〜
例えば、部署横断、年齢横断、役職の横断の取り組みが以前から行われていたことが挙げられます。主業務とは別に一般的に人事や経営企画がする仕事を若手メンバーに任せることで彼らの成長機会をつくる「ワーキング・グループ制度」にしても、部署を越えて働く文化を醸成することに貢献していました。
※補足
ワーキング・グループ制度は2012年スタート
引用記事はこちら。
上記は、いずれも秋山さんのインタビューを基にしていますが、代表の柴田紳さんが語られているものも見つけたのでリンクを載せておきます。いずれも柴田さんの組織づくりへの想いが垣間見える箇所があったのでよろしければご覧ください。
さいごに
やはり今回もボリューミーとなったので、続きます!次回は、コスト改善コンサルティングと組織開発コンサルティングを提供しているRELATIONSです。
追伸その1、
もっと知りたい方は、ネットプロテクションズのwantedlyに色んな方・色んな仕組みについての記事がアップされていますのでぜひご覧ください。また、人も募集されているそうです。(「つぎのアタリマエをつくる」ってすごくいいミッションですよね!)
追伸その2、
ティール組織について学びたい・深めたいという方は嘉村賢州さんが代表理事をつとめているホームズビー主催の"ティール組織ラボ"の情報をご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
