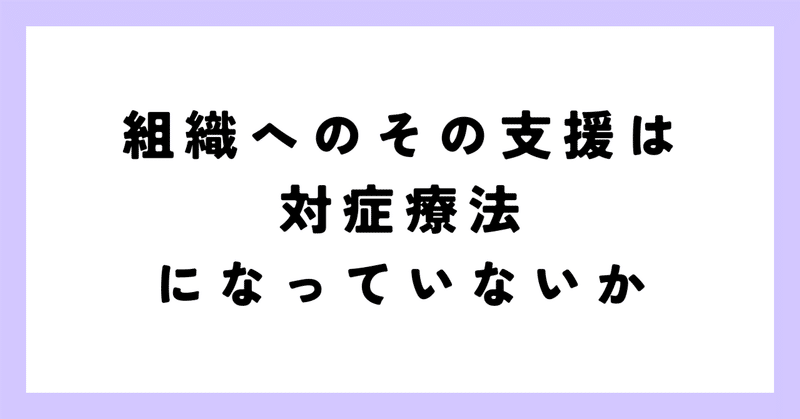
組織への「その支援」は対症療法になっていないか。
「痛みを軽減する」
とだけ書くと推奨されるべきことのように思えますが、
こと、個人や組織において「起こるべき変化がちゃんと起こる」ためには目を背けれるほどに痛みを軽減するのではなく、ある種ちゃんと怪我してもらって「痛みに直面してもらう」ことが重要だなと思うのです。
以前とある組織に伴走していた時のことです。
それまで一定期間担ってきた適切・効果的だったサポートが、ある段階から、まさに対症療法的になっていて、私の果たしていた役割(ロール)自体が、適応課題の一部となってしまっていたことに気づいた時がありました。
(期間を経て、私の立ち位置もより中心人物になっていったので、その前進があったが故に適応課題の一部となれた、とも言えそうです。)
このことに気づいてから意図的に立ち位置を変えたことで、とあるマネジャー的メンバー、そしてその上司的存在である経営者(その組織は役職による上下関係があるわけではないのでこのような表現になっています))はそれぞれ今までにないレベルで痛みに直面することとなりました。
その結果、短期的・表面的にはそれぞれに強い負荷がかかりましたが、そのおかげで、健全な破壊が起こり、重要な意思決定がなされるに至り、組織の本質的な変化が大きく前進することとなりました。
個人の根本的な変化を邪魔するものは、変化のプロセスにある当人の「現実逃避を生み出す誤ったプライドの使い方(もっとシンプルに言えば、起こっている出来事を私が起こしたと認められていないということ)」であり、
その「使い方の修正」を妨げるのが、周囲で関わりのある人による対象となる状況・人物に対する「自分のザワついた心を落ち着けたいという、あくまで自己防衛的な欲求がもたらす介入行動(それを支援だと思い込んでいる)」と言えるでしょう。
この両者はいずれもが、自身の本音とつながることができていません。
だからこそ、紐解けない、スムーズに流れていかない、停滞感がある状況になってしまうのです。
また、そういった状況の自覚があり、語られているならまだしも、これらをないことにし、自己納得し合って、現実に目が向けらられないまま、騙し騙し進めていくというケースも決して少なくないように思ます。(個人においても、組織においても。まぁ、それが悪いというか、ある種の寄り道に思ても必要なプロセスとも言えますが)
いわば自身の気持ちをないことにして、機械のように扱うと言えます。
これも対症療法であり自由に変えることができるはずなのですが、長く続くと常識といった変えられないと思い込みやすいものといった認識が育まれていくのも興味深いです。
そして、この個人に関する話は先に述べた組織にもそのまま当てはまると言えそうです。
今回話題に出している件(私が伴走した組織)で言えば、
・私が「とあるマネジャー的メンバー」と十分な信頼関係を育めていた。
・そもそもで言えばその直属の上司ともいえる経営者の方が組織内で起こっていることは自分が直接関与していなくても自分に原因があると健全に捉えることができている人だった。
・その組織では関係性を大事にする一方で、相手への直言(伸び代についてのフィードバック的な意味合い)を避ける傾向が強い文化だったため、私以外にそういった話題を伝え合うケースがほぼなかった。
といった上で
・私が果たす役割、立ち位置を変えた(特定の範囲において経営者の方の助けになるようなとメンバーの間に入る介入を減らした。その結果、経営者の方のストレスが健全に増えることとなった。)
・私が「とあるマネジャー的メンバー」と一緒に仕事をする中で感じた本音(私が主語となっている、感じていること)を本人に率直に伝える方針に変えた(かなり率直に言い、相手もショックを受けていた)
といった介入をしたことで、プロセスが促進されていったという見立てをすることができると思います。
このあたりはさらに分析して解像度を高めたいところです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
