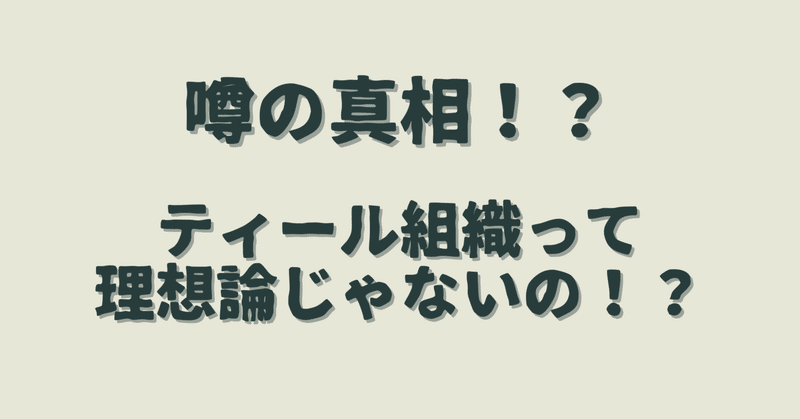
ティール組織は本当に理想論なのでしょうか?〜噂の真相シリーズ〜
はじめに
最近見る機会はかなり減った気がしますが、一時期SNS上でティール組織にまつわる色んな疑問・疑念がよく見られました。この記事では、これらについて「本当かどうか」を原著者であるフレデリック・ラルー氏の言葉と照合することを通じて探っていきます。以前取り上げたテーマはこちら。
今回は、そのシリーズで「ティール組織って理想論なんじゃないの?」という疑念に対して書いてみたいと思います。
書かれている内容が理想論だけではない理由
「ティール組織」の「はじめに」にこんな内容が書かれています。ㅤ
『私はこの二年間、人類の次の発達段階に適合するようなモデルで運営されているパイオニア組織を調査してきた。
『調査対象となる組織の場所やセクターは問わなかったが、少なくとも100人の従業員を抱え、新しい発達段階の特徴をかなり備えた組織構造、慣行、プロセス、文化を最低五年以上維持していることを条件とした』ㅤ
『調査した十二の組織は、私の定めた基準をはるかに上回っていた。多くの組織が長期間(三十〜四十年)にわたって新しいモデルで経営され、従業員の数も数人ではなく数百人、そして数千人に及ぶこともあった』
『パイオニア組織は互いの存在を知らず、独力で実験をしていた。セクターも規模もさまざまであるにもかかわらず、相当の試行錯誤の末、驚くほど似たような組織構造と慣行にたどり着いている。これに気づいたときには興奮を覚えずにはいられなかった』
『つまり、この世の中に新たな組織モデルが現れようとしているようなのだ。しかも実例があるので詳細を語ることができる。なぜならば、それらは机上の理論でも理想でもなく、従来よりも高い発達段階の意識に基づく、現実の、極めて具体的な組織運営方法だからだ。』
つまり、「ティール組織」に書かれている内容は妄想・空想の理想論ではなくさまざまな組織への取材をもとに書かれたもの、となります。
書かれている内容が理想論に思えてしまう理由
ティール組織そのものについては以下のように書かれていました。
・著者がティール組織という時は「組織の構造、慣行、文化的側面の大半ではないが、多くがティール段階の意識に合っている」ことを意味する
・調査対象企業のうち数社はほとんど純粋にティールだった。大半の組織は一部の分野では一貫してティールの行動に従ってきたが、ほかの分野ではオレンジやグリーンのパラダイムに基づいて行動しているという、ブレンドだった。また、このようにティールの要素が一部欠落していたとしても、どの組織でもティールと呼べる組織のあり方となっている。
「はじめに」の引用にも書かれていることからティール組織とは著者の持つ何らかの基準を上回っている組織のことを指しているといえるでしょう。
その基準が何かは分かりませんが、著者は書籍のPart3でティールの原則・構造・慣行・文化に従って、新しく組織をつくるか・既存組織を変革するための必要条件について書いています。
重要かつ唯一の変数は経営トップと組織のオーナーがティールの世界観を養い、精神的な発達を遂げていること(業種、組織の規模、地理的条件や文化的背景は重要ではない)
上記をさらに掘り下げると、経営トップには重要な役割がいくつかあるそうです。
・ティールの組織構造と慣行のための空間を維持すること。
・自主経営・全体性・存在目的の模範となること。
少なくともこれらの必要条件を満たしている&経営トップが2つの役割を果たしているというのがその基準と言えるかもしれません。
ただし、著者は「ティール組織をつくりたい」という人に対して「コンセプトは忘れてください。それは心の奥底の想いではありません」と伝え、コンセプト先行で進めようとするリーダーに対して警鐘を鳴らし、変革を求める本当の理由(現場での個人的な痛みなど)に意識を立ち返らせるように働きかけているようです。以下の2つの動画参照。(この動画が何かを知りたい方はこちらの記事を参照ください)
このことからティール組織とはあくまでもコンセプトであることが分かります。
書籍には著者が導き出した変革のための共通項として具体的なステップのように思える内容も書かれていたり、事例の隙間を埋めるような著者の考察を補足する引用も登場します。
すごく大雑把ですが、書籍「ティール組織」に書かれている内容を図にしてみました。書籍ではこの図の全てについて書かれていますが、黄色に囲まれたところが特にティール組織が1つの体系・1つの型のように見えてしまうポイントだと私は捉えています。
注)以下の図の内容が書籍の内容のすべてを表しているわけではありません。

そのため、読み手に「”要は”ティール組織という1つの正解を実現するための方法が書かれている本なんだ」と受け止められても仕方ないように思いました。
この点に関しては著者自身が調査で追求しようとした問いの中に「この組織モデルを体系的に説明することは可能なのか?」というものがあるため、そのように整理されて当然かも。(p18参照)
だからこそ、この点を指して「理想論が書かれている!」と言われてしまうと、ある意味当たっていると言えそう・・・。
また、図中の黄線内の内容に基づいて(言い換えれば、著者の直接的な支援によって)実際にティール組織が生まれた事例があるかは私の知る限り知りません。(ちゃんと調べなきゃ・・・)
そのため「理想論」の反対が「ここに書かれている内容に基づいて再現することができる」という意味だとしたら紹介されている事例企業以外の内容についてはまだ理想論と言えそうだなぁと思う次第です。
ちなみに、ここに書かれている内容に基づいて自社の構造、慣行を変え、うまくいっている日本の中小企業(グループ全体で約500名規模)を知っているのですが、その企業をこの書籍でいうティール組織と呼べるかどうかは、著者が直接調査しない限りは判断できないと思うため、上記の意見に至っています。また、そもそもティール組織かどうか判断すること自体、意味がないでしょう。最も大切なことは、その会社・組織の経営者・働く人々にとって望ましい状態が実現することですから。
さいごに
では、まとめます。ティール組織は理想論なのか?そうじゃないのか?
私の結論は、、、、
『理想論ではないと言い切るための条件が「"再現性が実証済みの"体系的なノウハウであること」だとしたら、ティール組織はまだ理想論の範疇にあると言えるでしょう』
です。
とはいえ原著が発売されてから約9年が経っていますので海外の情報を踏まえると書籍に基づく事例は出てきているかもしれません。
ただ、著者がそうしてきたように理想に希望を見出し「本当にできるとしたら」という疑問・疑念の先へ進もうとする人にとっては参考になる叡智がたくさん詰まっている本だと言えるので、個人的には強くオススメします!
最後に、日本において著者のまなざしにできる限りに忠実に「ティール組織」に関する基礎的なことを学びたい方にオススメの講座を紹介して終わります。
書籍「ティール組織」解説者の嘉村賢州さんが手がけ、講師もされているティール組織ラボ概要編(3H)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
