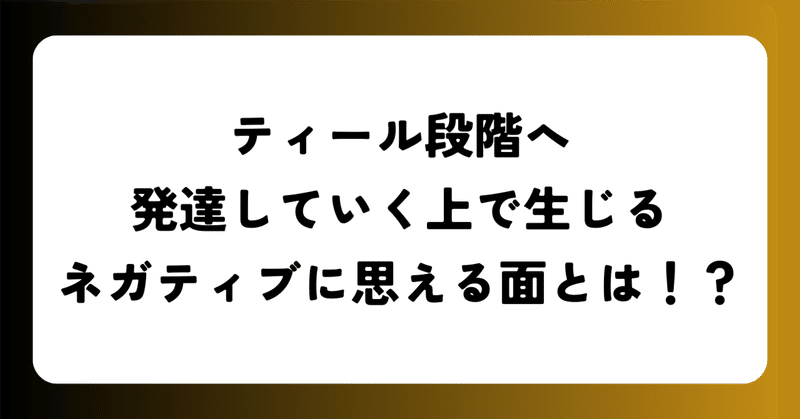
ティール段階に発達していく上で生じるネガティブな面を「あえて」取り上げてみた
はじめに
久しぶりに手に取りました。
初めてこの本を読んだ時に「ティール組織」の文脈において自分が無意識にオレンジよりも、グリーンよりもティールの方が優れているという印象を抱いていることに気づくことができました。
ふと、「なぜそんな印象を持ったのだろう?」という問いが生まれたので、改めて、ティール組織日本語訳を読んでみたのです。
その結果、思ったことは成人発達理論自体をどのように取り扱うのかについては以下のような慎重な言及がありつつも、
『進歩には段階があるという現実が問題なのではない。そこにある階段を私たちがどう見るか、なのだ。ある段階がその前の段階よりも「良い」「優れている」考え始めると面倒なことになる』
『むしろ、世界に対処するうえでの「より複雑な」方法なのだ、と解釈する方が有益だと思われる』『どの段階にもそれぞれの光と影、健全な面と不健全な面がある』
「ティール組織」自体の弊害(厳密にいうとそれ以前のパラダイムに重心がある人にとっては不快だったり、何も魅力を感じないという意味合いが強い)について触れられていないことによって、ティール組織が一番いいかのような印象を持ってしまいがちなのだと思いました。
ので、この記事では、あえて、経営者という個人にとって自身のパラダイムがティールへ移行していく中で生じる弊害・苦悩・病理について書いていきたいと思います。
ティールパラダイムへの発達プロセスの中で起こることとは?
概要
インテグラル理論の日本における第一人者である鈴木規夫さんが書かれた『人が成長するとは、どういうことか ーー発達志向型能力開発のためのインテグラル・アプローチ』の中で、以下のような箇所が出てきます。
各発達段階は、過去の発達段階の限界を超えて創発する「偉業」であるだけでなく、まさに新たに獲得されたその卓越した能力ゆえに、過去の発達段階には存在しなかったより深い苦悩や病理を生み出すことになるのである。その意味では、発達とは単純により幸福になることではなく、それまでには経験することができなかったより質的に高い光と深い闇を経験できるようになるということなのである
高次の発達段階に到達するとは、定義上、既存の発達段階を特徴づけていた思考や欲求を「卒業」するということであり、それゆえに、目標とする発達段階に歩みを進めていく中では、今、自己を衝き動かしている欲求そのものを放棄し、超越していく必要がでてくる。
段階的な発達は、心理的な死と再生を伴うプロセスであるために、しばしば体験者を深い精神的な危機に陥らせることになる。
『個人は、それまでに自身を支えてくれていた精神的な基盤を失い、この世界の中で生きていくための意味や物語をあらためて再構築していくことを求められる。すなわち、そこでは、いわゆる「実存的危機」と言われる混乱や混沌や苦悩が経験されることになる』
ティール段階が直面する闇とは?
ティール組織に書かれている「ティール」の記述と鈴木規夫さんが書かれているものは完全一致していませんが、重なりはありますので大まかな理解を助けるものとして読んでもらいたいです。ここでは、鈴木さんの書籍から引用します。
『後慣習的段階(グリーン〜ティール〜ターコイズ)は、それまでの発達段階と異なり、時代や社会の支援や理解をほとんど得られない状態に恒常的に投げ込まれることになる』
『そうした在り方は、ある意味では、「無法者」になるということでもある。そして、そのために常に時代や社会の無理解にさらされるだけでなく、攻撃や迫害に見舞われる可能性を背負うことにもなるのである。』
<その理由>
『人類史においては、社会の集合的意識の重心を超えた意識を確立した人たちは、時として流刑や処刑の対象となっている。社会が、思想の統制や情報の検閲を通して、自己の成立基盤を維持しようとするのは、21世紀においても変わりはなく(実際に、世界中に、未だに厳しい言論統制体制を敷いている国家が多数存在するのは周知のところである)』
『思考というものが本質的にそれを支える前提条件に依存するものであり(例:価値観、世界観)、そして、そうした前提条件そのものが究極的にはその時代や社会の中で共有されている「虚構」であることを明確に認識できてしまう』
『その結果として、自己の存在意義そのものを失うような感覚を背負いこむことになる。』
『こうした感覚はいわゆる「実存的危機」として知られているが、後慣習的段階とは、まさにこうした実存的な課題と正面から対峙することを求められる発達段階となる』
映画「もののけ姫」に学ぶその特徴
書籍の中で後慣習的段階(グリーン〜ティール〜ターコイズ)の段階の特徴を体現する例として映画「もののけ姫」のアシタカが紹介されています。
『この物語を通して、アシタカは自らが死の呪いを背負わされた存在であるということを常に意識しながら生きていくことになる。』
『死の呪いを受けることを通して、アシタカは故郷を終われ放浪の旅に出ることになる。同じ物語を共有する人々とともに育んできた共同体における立場や役割を剥奪され、この世界の中に一人の素のままの個人として投げ出されることになるのである。』
この2つは上記でも紹介した「闇」にあたるかと思いますが、「果たす役割」についても記述があります。
『アシタカの行動の特徴として非常に興味深いのは、物語を通じて、彼が実に多様な関係者と誠実に対話をすることである。また、単純に会話をするだけでなく、そこで生活を営む者たちの心の内に潜む想いに心を寄り添わせ、その真実と尊厳を理解しようとするのである』
『全ての関係者たちが自らの「物語」に基づいて状況を認識し解決しようとするのに対して、アシタカは「森と人とが争わずに進む道はないのか」と一貫して全体の調和を志向した探求をする』
『物語においてアシタカを動機づけるのは、自らにかけられた死の呪いを解きたいという欲求であるが、また同時にそれはそうした呪いをこの世界に生み出した原因そのものを解決したいという欲求にも通じている(具体的には、アシタカの故郷を襲撃したイノシシを邪念に狂わせてしまった原因そのものを解決したいという欲求)』
もののけ姫を成人発達理論のレンズで捉えたことがなかったので、この例示は興味深かったです。
ティール的組織を目指そうとした経営者が言っていたこと
ここまでは概念的な内容をお届けしてきましたが、1つ具体的な事例を紹介します。
手放す経営ラボという先進的な活動体があります。このラボでは所長である坂東孝浩さんがご自身の経営に悩まれたことがきっかけで「ティール組織」が出版される前から日本国内の先進事例を多数取材されてきました。
そんな坂東さんが2017年にティール的経営の先駆的実践企業と名高いブラジルのセムコ社の代表リカルドセムラーの来日イベントに参加されました。その懇親会でセムコ社が日本で有名になるきっかけとなった書籍『奇跡の経営 一週間毎日が週末発想のススメ』を読み、実践してみたけど失敗して元の経営スタイルに戻したという経営者の方に多数会ったそうです。

その方々と話した結果、『これはやり方として捉えるのではなく、例えていうならキリスト教から仏教に宗教を変えるようなものだ』と確信し、その覚悟で以て自身の経営スタイルをガラっと変える決断をされ、道なき道を傷つきながらも進んできました。(その様子はラボのブログに赤裸々に生々しく、綴られているので気になる中小企業の経営者はぜひご覧ください)
私は、その後2020年に出会い、約2年間、旅路(さまざまなプロジェクト)をご一緒させてもらい、そのプロセスでティール的組織に興味のある経営者のお話を多数聴かせていただきました。
その結果、取り組みを進めていく中で突きつけられる、選択が迫られるシーンにおいて、前進する決断ができるのは、目の前の現象に違う意味を見出そうとできるのは、最初からあるいは途中でも「やり方ではなく自身のあり方そのものに影響がある」と肚をくくった方か、すでに必要な発達を遂げられている方なのだぁと実感しました。
さいごに
今回の記事ではあくまで「ティール組織」の書籍に書かれている内容をもとに書きました。この書籍は2014年に出版されたのですが、原著者のフレデリック・ラルーは、その後2018年に更なる実践探究の結果を合計131本ものビデオシリーズとして公開しています。
そのシリーズの中では、例えば「これを単に組織の旅だと考えて自分自身が変わろうとしないならこの旅に出ないことをおすすめします。もう一度言います。もしこの旅は組織の変革のためだけのもので自身の大きな成長機会でもあると考えていないなら旅を始めないでください。」というような今回紹介する内容に通ずる、その道で生じる影(のように思える側面)について色々な角度から触れられています。
言い換えれば、このビデオシリーズまで目を通すと、ティール組織が一番いいかのような印象は持たない、ということです。
ですが、日本で10万部以上売れた書籍に対して、このビデオシリーズまで読んだ人は限りなく少ないと思えるため、あえて紹介することを通じてビデオシリーズ自体に興味を持ってもらえる人が出てくればいいなと思いました。
今回は、「ティール」にまつわる影・病理(のようにしか思えないこと)について個人の内面という側面から取り上げましたが、それ以外の側面については過去にこんな記事を書いたのでよければご覧くださいませ。
その他、書籍「ティール組織」にまつわる社会的考察について書いた記事はこちら。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
