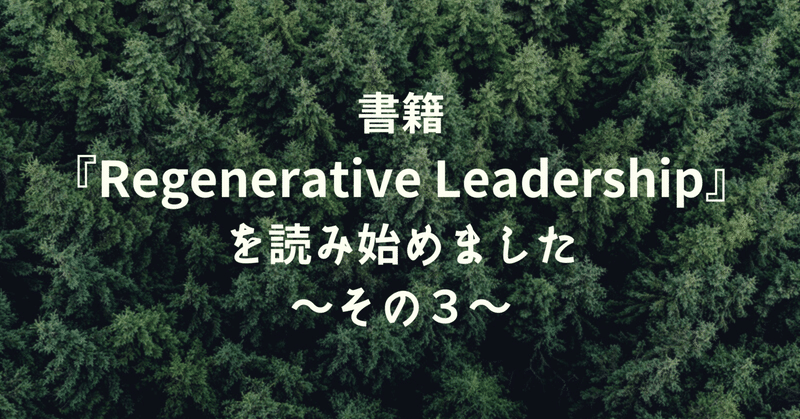
「Regenerative Leadership」Chapter3を読みました
はじめに
書籍「Regenerative Leadership」を友人たちと読み進めています。前回からだいぶ時間が空きましたが続編となるChapter3"The Dawn of a New Leadership Era(新しいリーダーシップの時代の幕開け)"を読んで感じたことを書きます。
前回の記事はこちら。
Chapter3の内容pick up
※以下の文章はすべて原著をDeepL翻訳にかけたものを抜粋しています。
・今日、次のステージのリーダーシップや組織意識が出現している。例えば、以下のような点からそのようなことが見てとれる。
McKinsey & Coの2018年1月のレポートでは組織を機械として捉える考え方から、生命システムとして捉える考え方の重要性が強調されている。
投資マネジャーのJay Bragdon氏:生命システムの方法論と生命を肯定する文化を取り入れた組織が、機械論的な組織を一貫して上回っていることを探っている。「従業員が声をあげ、何が起こるかに関与する企業は、ほとんどの決定がトップで行われる伝統的な管理型企業よりも明らかに優位に立つ」と述べている。
元マッキンゼーのコンサルタントであるフレデリック・ラルー氏の「Reinventing Organizations」がリーダーや実践者たちによって世界中で広く取り上げられ、人気をはくしている。
・CSR、持続可能性、サーキュラーエコノミーは、脇役の話題ではなく、戦略的要請の中核をなすものとして認識されている。
世界最大の投資家であるBlackRockのCEO、 Larry Fink氏「すべてのビジネスリーダーに、今後5年以内に、すべての投資家は投資するすべてのビジネスについて環境と社会的ガバナンス(ESG)の基準を考慮するようになるだろう」
・筆者たちは従業員、顧客、サプライヤー、資源、投資家、社会、環境といったエコシステムと常に関わり、共創し、革新することによって、刻々と変化するビジネス環境を迅速に察知し、対応することができる新しいタイプの組織が出現していると考えている。→この新しいタイプの組織は、"生命システムとしての組織"と呼ばれる。
・組織を機械論的アプローチではなく生命システムアプローチに移行していくには、リーダー自身の意識を分離からシフトさせていく必要がある。
・この意識のシフトの参照モデルとしてクレアグレイブスのスパイラルダイナミクスが紹介されている。※特に、1階層目(ティア1)のオレンジとグリーン、2階層目(ティア2)のティールに焦点を当てている
オレンジの意識レベル
今日のビジネス思考に浸透している。よい人生を送ること、勝つためにプレーすることが主な方向性。
機械的な論理に基づき、還元的な分析を優先。
オレンジの組織のメタファーは機械。
オレンジのリーダーシップの意識は、競争に勝つ、それが必須であるかまたは直接ボトムラインに影響を与えない限りは持続可能性や倫理面を気にしない。
グリーンの意識レベル
グリーン思考は共同体意識を促進し、人間の平等感を回復することによって、人類を欲や利己主義から解放しようとするもの。
リーダーシップは、ステークホルダーの価値を実現するために、従業員の並々ならぬ意欲を引き出す人間中心の文化に重点を置いている。
リーダーシップにおけるEQと共感の重要性を認識している。
グリーンの組織のメタファーは家族。
Tier2の意識
組織は生きている・学習している適応性のあるシステムとして認識されている。
地球上のすべての生命は相互に関連し、依存し合っているという本質的な理解があるため、サステナビリティはビジネスのミッションを実現する上で不可欠な要素。
Tier2の意識の核となる価値観
内なる正しさ、自己学習、生命を肯定する目的意識、自己とシステムへの意識、私たちの本質を開花させるための条件整備に対する自己責任、すべての生命とのつながりの感覚
組織文化、オペレーション、サステナビリティのアプローチは、より自己組織的、機敏かつ流動的、地域のニーズや変化する状況に依存するようになる。リーダーシップはすべての階層に分散し、誰もが組織の文化・風土・運営、そして持続可能性を活性化させる責任を負っている
(ティール組織著者の)ラルー氏のいうティールは、グレイブス氏のTier2の第1レベルに相当します。
・Tier1→2へのステップチェンジは、変容・世界観の画期的な変化。芋虫から蝶への変態のように、古いやり方を手放し、心の中で可能だと分かっていることに心を開くことが必要。
・Tier2の意識はリジェネラティヴリーダーの意識と同じ。
・リジェネラティヴリーダーシップの意識は、以下の3つで構成されている。
①システムシンキング
システム全体における部分の相互関係を理解し、すべてのシステムが他のシステムの中に入れ子になっていることを理解する思考法。オットー・シャーマーの言う「オープン・マインド」に関連している。
②システムアウェアネス
システムと私たちの関係を変化させることを意味する。システム全体で常に変動しているダイナミクス、目に見えない暗黙知の流れ、フィードバック、関係性のエネルギーを考慮する。オットー・シャーマーの言う「オープン・ハート」に関連している。
③エコシステミックアウェアネス
私たちが属しているすべての入れ子状のシステム(人間や人間以上のもの)の全スペクトルに対して自分自身を開放するときに到達する。人間と自然のダイナミズムを統合し、自然から切り離されるのではなく、自然と同調するようになる。オットー・シャーマーの言う「オープン・ウィル」に関連している。
「組織内のすべての人が Tier 2 の意識で活動していることを期待することはできません。したがって、私たちは、人々、チーム、そして組織全体が、いつオレンジ、グリーン、またはティア2のマインドセットからより多くを引き出しているのかに気づくことができるようになる必要があります。組織の重心はどこにあるのか、そしてそれが全体にどのような影響を与えているのか。ある場合には、チームはオレンジモードに、またある場合にはグリーンモードにするのが賢明かもしれませんが、組織というリビングシステムが包括的なリジェネラティブリーダーシップの意識に支えられている限り、それは可能です」
『「リジェネラティヴ」という言葉は、生命が絶えず自己を更新し、新しい形へと超越し、刻々と変化する生命条件の中で繁栄するための条件を整えることを意味します。』
『生命の論理を妨げるのではなく、むしろそれを助けるもの』
『従来のCSRやサステナビリティの概念を超えて、現在の考え方が生み出す負の影響を減らすことを主目的とするものではなく、むしろ、まったく新しい考え方、ビジネスやそれ以外の分野での「新しいあり方」への移行を意味する』
『リジェネラティヴビジネスは、私たちの役割と目的を、本質的に獲得的な「自分のためだけのもの」というアプローチから、コラボレーション、共同創造、貢献のマインドセットへと変えます。』
Chapter3を読んで感じたこと
日本ではどうなの?
・世界で次のステージのリーダーシップや組織意識が出現しているという箇所が日本ではどうなのか?気になりました。以前こちらの記事で書いたように2018年に『ティール組織』が出版されて以降、日本の実践者による書籍の出版が少なくとも今に至るまで10冊販売されています。この意味では、新しい潮流が顕在化し、話題として扱いやすくなってきているとは言えそうです。
また、余談ですが私が調べた範囲によると昨今語られているティール的と見立てられる日本企業の事例は古くは1980年代に出版された名南製作所、前川製作所について書かれた書籍に見出すことができます。その後、2006年にセムラー社について書かれた2冊目の書籍である『奇跡の経営』が出版され、多くの経営者が手にとり衝撃を受けたと聞いていますので、この頃が第1次ブームと呼べるのかもしれません。
実際、同じく2006年にはセムラー社について書かれた1冊目である『セムラーイズム』の文庫版が出版されたり、日本において次世代型のリーダーシップや組織論について先駆的に提唱された元SONY上席常務の天外伺朗氏が『マネジメント革命 「燃える集団」を実現する「長老型」のススメ』の出版を皮切りに、人間性経営学シリーズを出版していきます。また、天外氏の書籍でロールモデルとして紹介された株式会社ヒューマンフォーラム創業者の出路雅明氏の書籍『ちょっとアホ!理論 倒産寸前だったのに超V字回復できちゃった!』もこの年に出版されています。
ちなみに、上記で紹介された企業は出版された当時、従来のCSRやサステナビリティ・それらを越えたリジェネラティヴな取り組みという文脈で紹介されていません。リサーチ不足の中の仮説ですが、日本においてニューパラダイムのリーダーシップや組織体制と、リジェネラティヴビジネス(サーキュラーエコノミー)はまだ距離があると言えるのかもしれません。(とはいえ海外がどうであるかはまだ知らないです。ちなみに、どちらとも重なっている事例としては『ティール組織』で取り上げられているパタゴニアがあたります。)これはこれで日本における環境ビジネスの変遷というテーマで扱っても面白そうです。組織体制という点で調べた訳ではありませんが、サーキュラーエコノミーに先駆的に取り組んできた企業と言えそうなユーグレナは2005年、日本環境設計は2007年の創業と、第一次ブーム(仮)の時期が似ているのは興味深いですね。
リジェネラティヴリーダーを知性的に捉えるためには?
・リジェネラティヴリーダーとは?について書かれている内容では、成人発達理論の1つであるスパイラルダイナミクスが参照されていたり、U理論も紹介されていて概要の紹介に留まっている印象のため、質感について理解したい場合は一番は著者に質問することですが、少なくともそれぞれの書籍にあたる必要があるなぁ=ある程度の前提知識が必要で、読者を選ぶ書籍に思えるなぁ。
4つの領域の統合へのアプローチ〜私の場合は?〜
・機械論から生命論へシフトするために必要と言われる左脳と右脳、自身の内面と外面、男性性と女性性、人間と自然という4つの領域の統合について、私はそれぞれ統合への取り組みをしてきたのか?過去の棚卸ししてみたいと思いました。
振り返ってみると内面と右脳については、大学時代の就活で夢を見つけた時の自分は活用していたように思います。しかし、社会人になって働き始めてからは環境の影響もあり、一気に外面・左脳優位になり近視眼的になり、その苦しさからの解放を求めて社外へコミュニティを求めたと言えるでしょう。
その結果、出会った、あるコミュニティは同世代の若者が多数集まっていましたがコーチングを学び、コミュニケーションのベースに置いていたり、マインドフルネスを言い換えたような"今、ここを生きること"について学び実践を支援するような環境でした。
その中で、内面や精神性、男性性と女性性といった領域についての情報にも多く触れるようになりました。また、主に学びをもたらしてくれていたコミュニティリーダーは途中からハワイ島で生活するようになり、その教えも自然の摂理から受け取ったものが増えていきました。その意味で住んでいたのは都会ですが自然について学ぶ機会もあったと言えます。
このように振り返ってみると、会社員になりたての2007年から2010年までの間で、統合が必要な4つの領域について学んだり実践者に触れられる環境(コミュニティ)にいたのですね。今思うとそれぞれの領域をバラバラに学ぶのではなく横断的に学び触れられることができる環境だったのがよかったです。
おわりに
実は、読んで感じたことのPartはしばらく浮かばなかったんです。そのため、寝かせに寝かせてこのタイミングでの投稿となりましたが(汗)結果として、自身の過去の棚卸しや2020年頃にやったリサーチを活用する機会になり、こう着地するのか!?という驚きと面白さと、少なくとも納得感のあるレベルの記事を出せてよかったという気持ちでいる、今ここです。
長文、最後まで読んでいただきありがとうございました。
続きはこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
