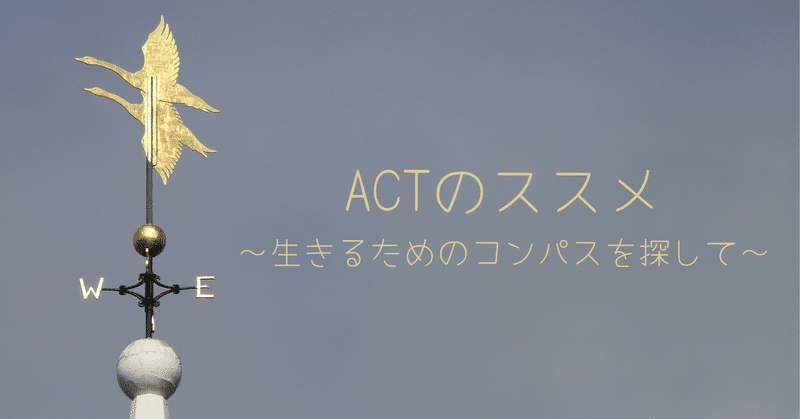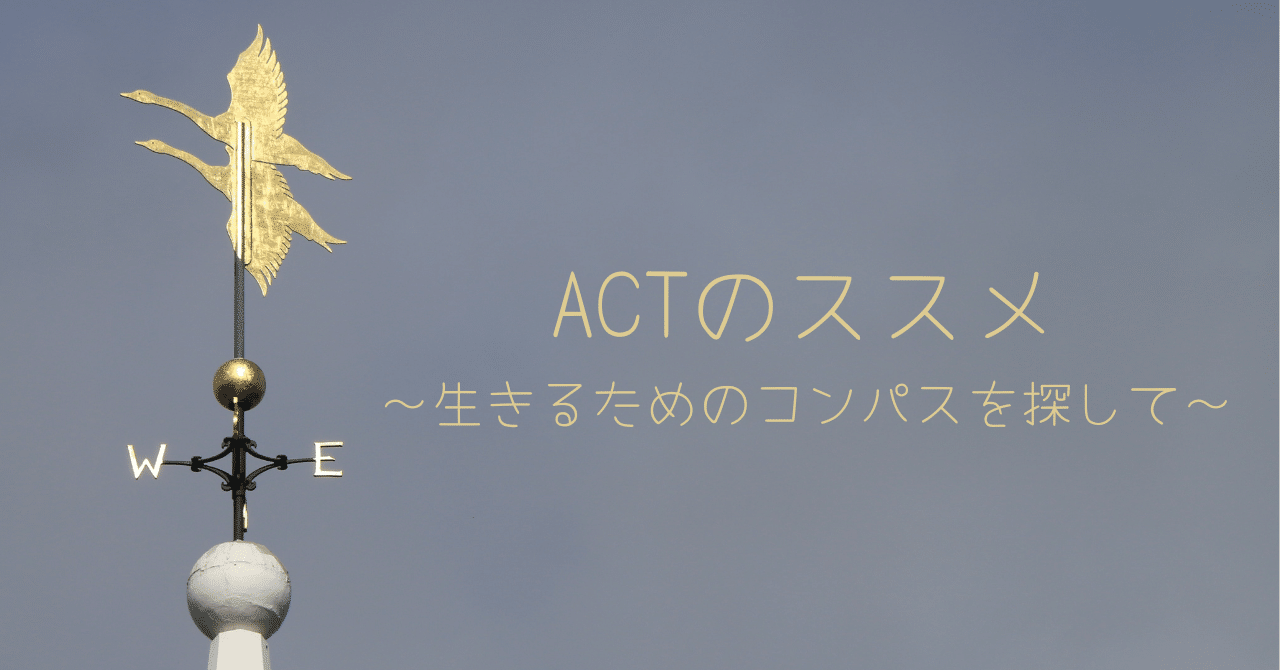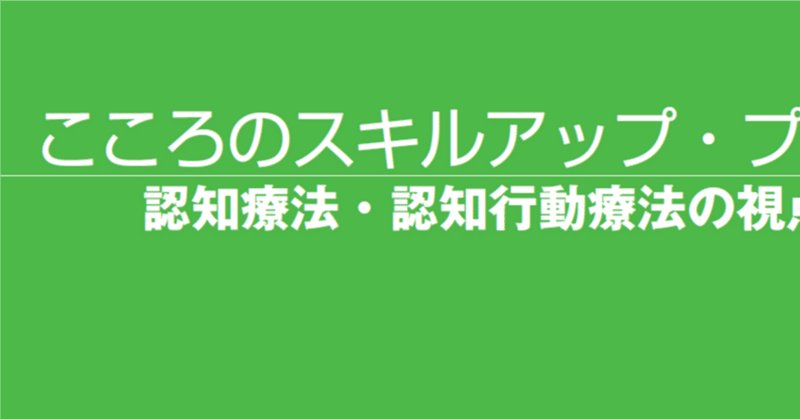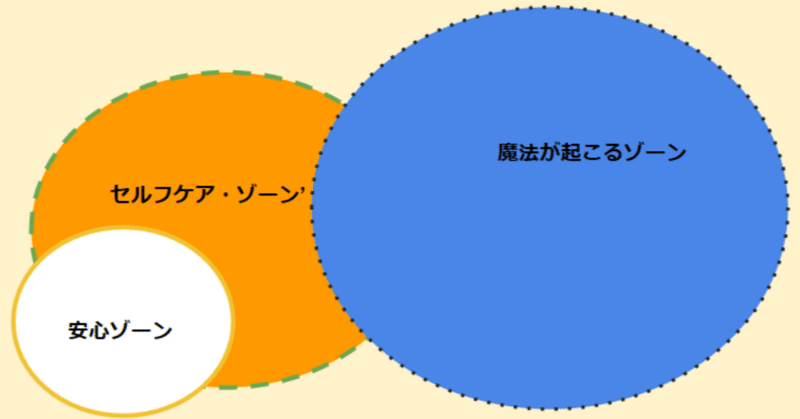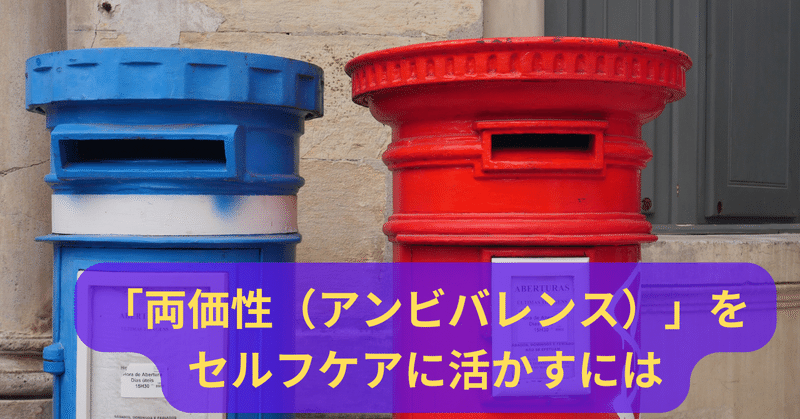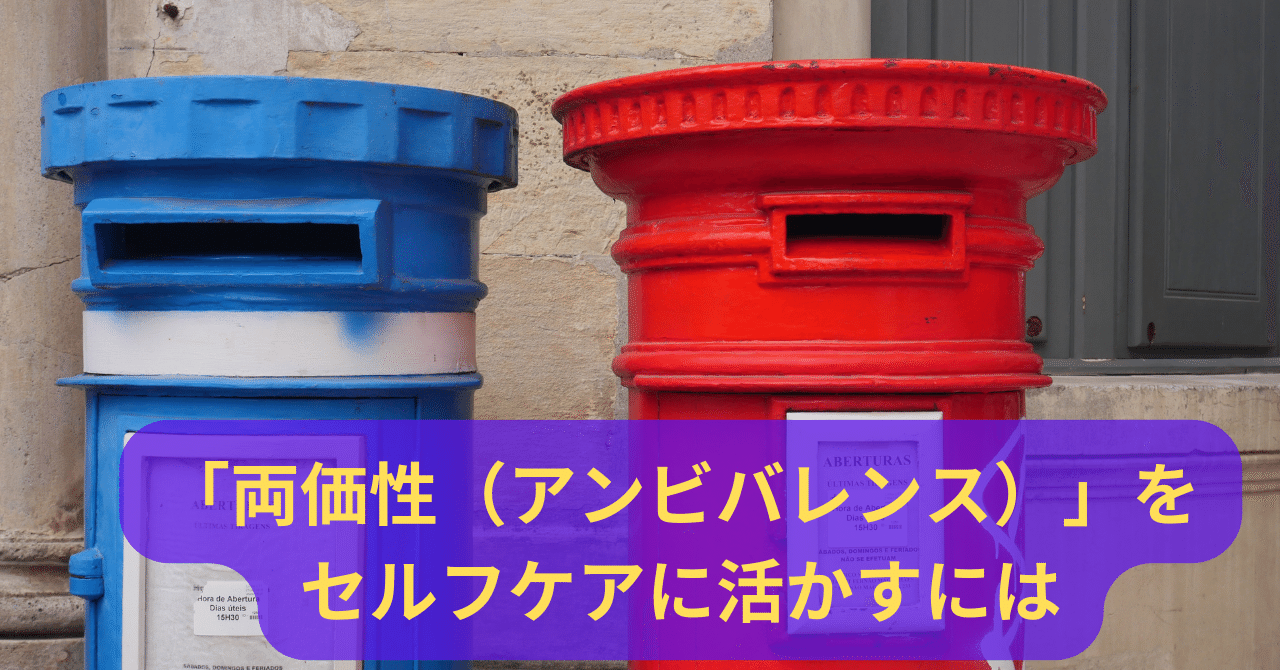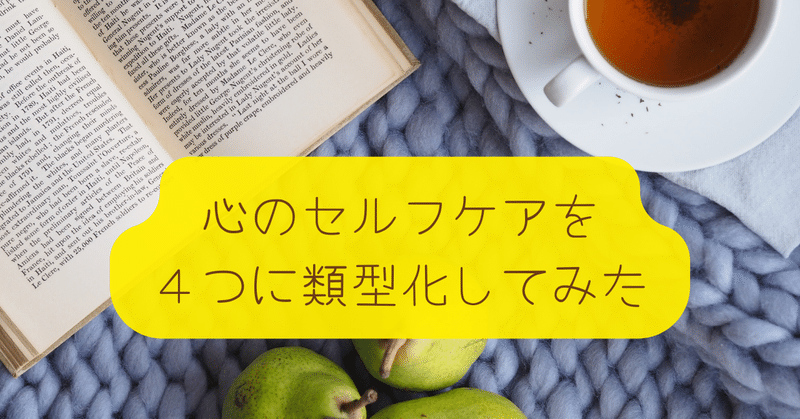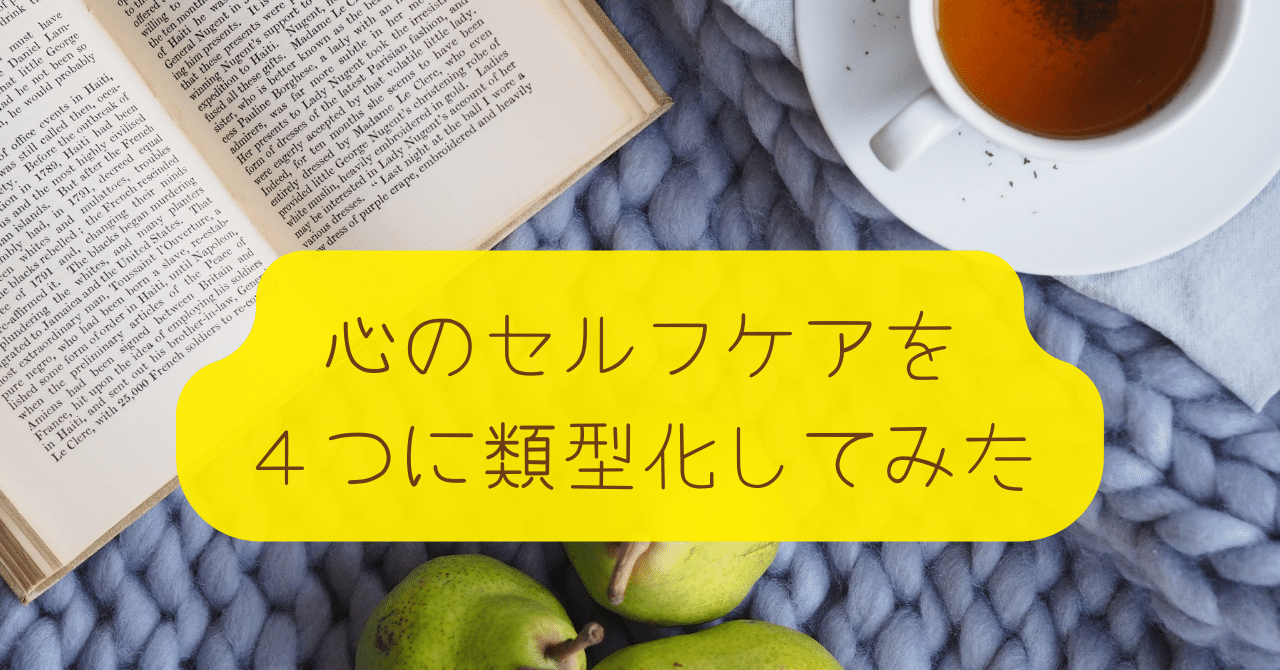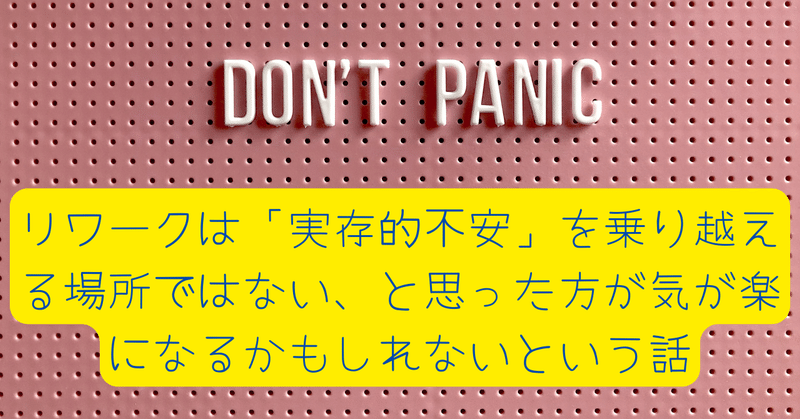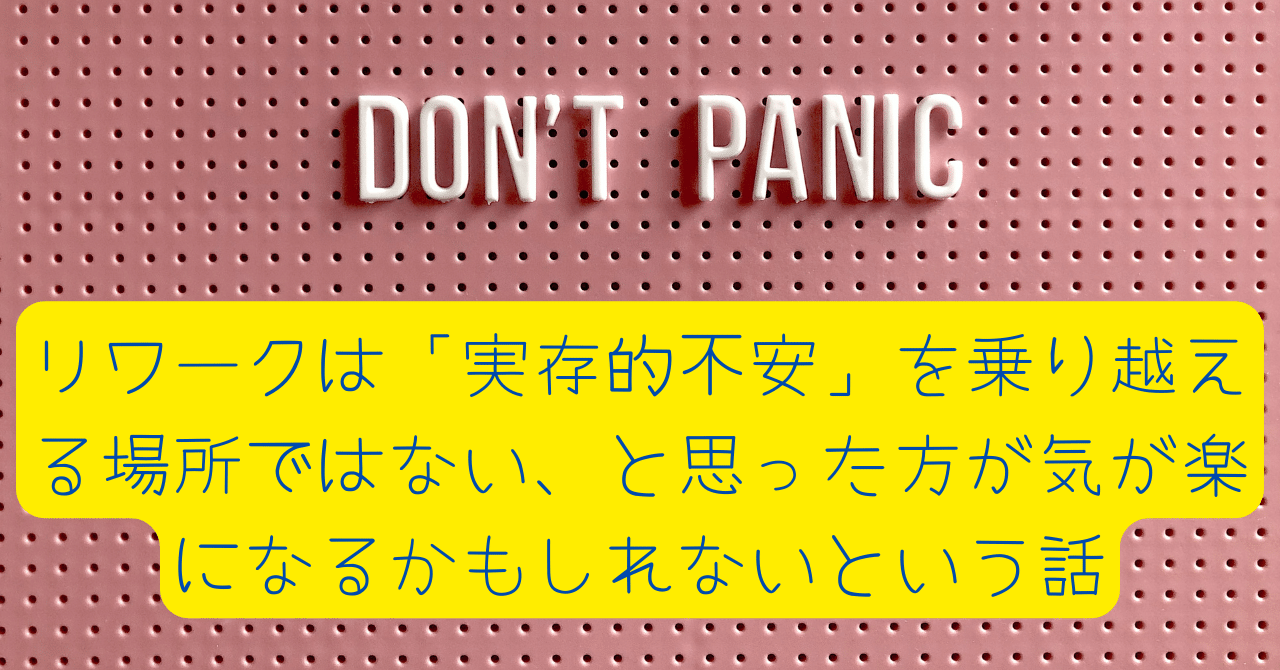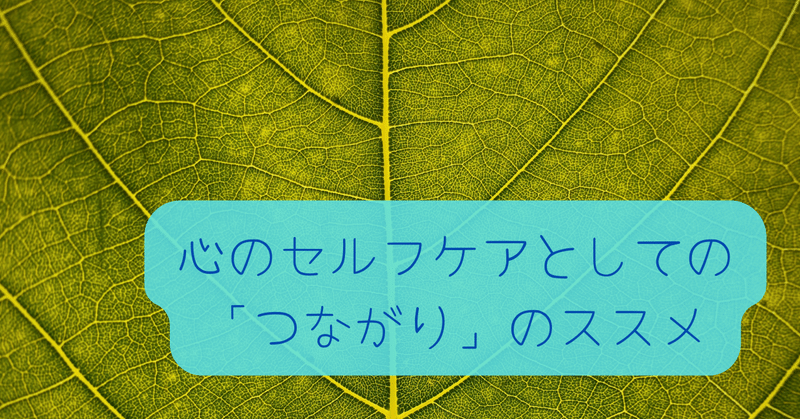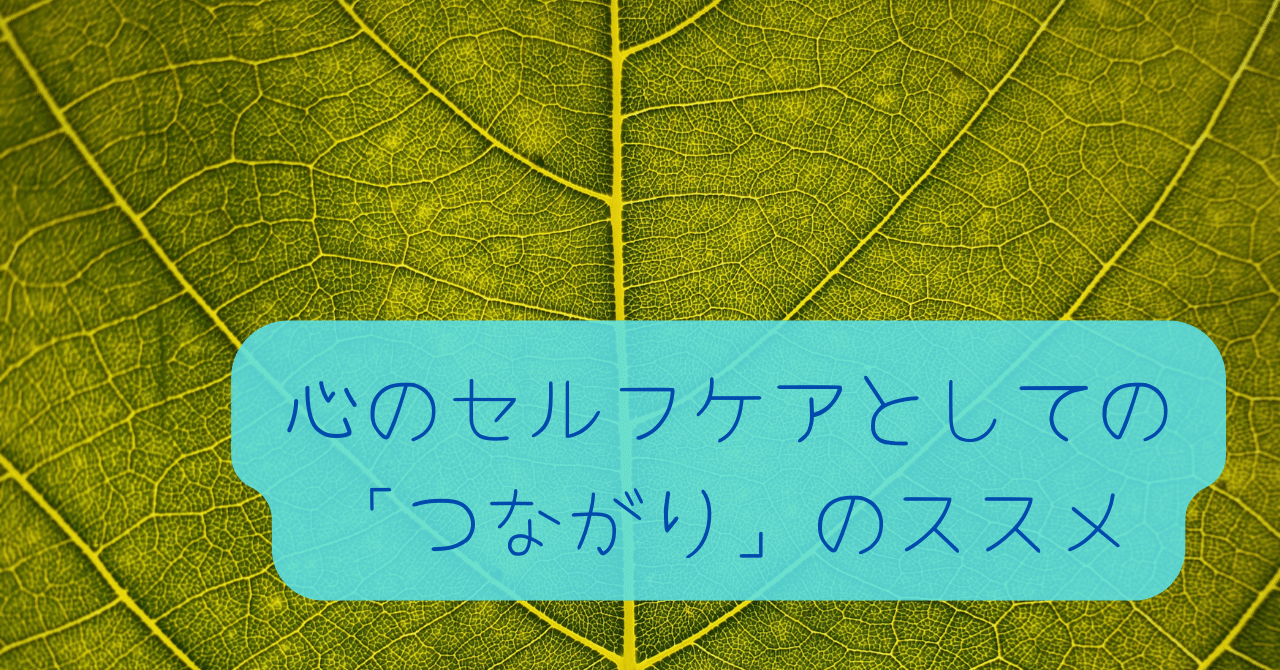最近の記事
- 固定された記事

【後編】自己分析は「言い訳づくり」のために行うべきではない?:ACTにおける「体験の回避」と「変容のアジェンダ」「創造的絶望」の考え方について
こんにちは、すぱ郎です。 今回の記事は前回の記事の続きになりますので、前回の記事をまだ読まれていない場合はそちらから読んで頂ければと思います。 前回は心理療法の1種であるACTにおける「体験の回避」に関する自身の経験を交えた紹介をさせて頂きました。今回はその「体験の回避」を助長するような影響を及ぼすと言われる「変容のアジェンダ」という言葉を紹介します。 ※注 休職直後で何よりも休養が必要な時期の方などは、前回や今回の記事はあまり参考にされない方が良いと考えます。あくま

【前編】自己分析は「言い訳づくり」のために行うべきではない?:ACTにおける「体験の回避」と「変容のアジェンダ」「創造的絶望」の考え方について
こんにちは、すぱ郎です。 リワーク時代に作っていたスライドを読み直していて、少しドキッとした内容のものを見つけたので、自戒も込めて紹介してみようと思います。書いてみると予想以上に長くなったので、今回を前編にして、2回に分けて投稿したいと思います。 心の病気になって休職したりした経験のある方は、多かれ少なかれ休職を契機に 「どうしてこうなってしまったんだろう」 「何が原因でこうなったんだろう」 といった事を自分なりに掘り下げて考えた経験があるのではないかと思います