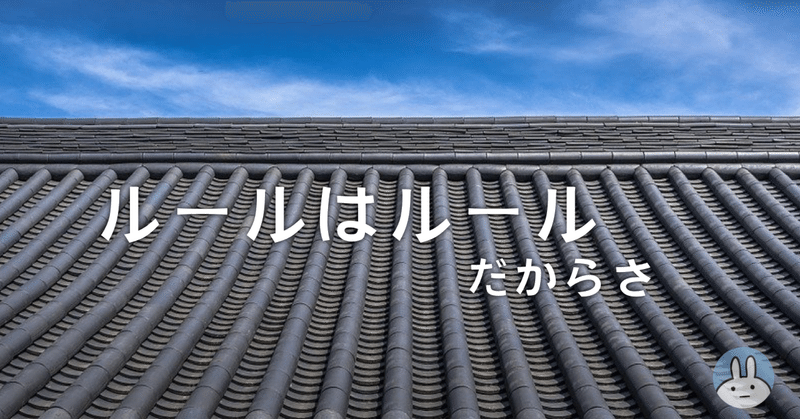
ルールはルールだからさ
ルールは絶対っていう話、最近よく耳にするようになりました。スポーツを見てても一連の騒動をみてても。 特に個人的に明確な意見があるわけではないのですが、今日は気の赴くままに #飲みながら (飲んでないけど)ルールについて雑談してみたいと思います。
優先席に思う
ルールと言うと真っ先に「優先席」が思い浮かびました。まずはとっかかりに優先席の話から始めようと思います。
優先席ってとても優しいルール。お年寄り(や困っている人)に優先的に席を譲るためのルールです。昔はシルバーシートなんて呼ばれてましたけど、もう生まれる前から当たり前にあるので、優先席に否定的な意見を持っている人はもしかしたら少ないかもしれませんが、わたしはこの優先席って実はあんまりスキじゃないんです。だって、困っている人がいたら助けてあげましょうっていうのは、ルール以前に人としてどうあるかの問題で、むしろそういう行為があたりまえの社会であってほしい。ルール化するとね、その先は優先席ではお年寄りに席をゆずら「なければならない」、逆に優先席でなければ席をゆずる必要はない、って極論に行き着く。それでもルールに従っているわけですから、誰にも文句言われる筋合いはありません。
腰の悪そうなおばあさんが電車に乗り込んできた。席を専有していた若者がぼそりと一言。「席に座りたけりゃ、優先席に行けよ。」
仕事で徹夜続きで疲労困憊の若者がいた。そこに登山帰りの元気そうなおじいさんが電車に乗ってきて「優先席なんだから席を譲りなさい」と催促する。
大道廃れて仁義あり
年齢やルールに関係なく必要な人に与えられるものを与える優しさがあったなら、疲れている人にしばらくの仮眠をとらせてあげたりして、最寄りの駅にきたらまた誰かがそっと起こしてくれる、そんな優しい世界があってもいい。
人の心が荒むからこそ、やれ仁義だ道徳だルールだとヤイヤイいわなければいけなくなる。
ルールは作ったあとの合意が大事
ルールはそれを一生懸命考えて作る人がいるのだけれども、作るだけじゃダメでそれを守りましょうねっていう合意形成がないといけません。
それが民主主義の本質なんですけど、民主主義ってみんな選挙で多数決をとってルールなりしくみを「決める」ことだと思っている。だから、選挙で結果が出たらおしまい。
でも、民主主義の本質は決めた結果がどうであれ、決まったことは「反対票を入れた人も」ちゃんと社会の一員としていっしょにルールを守りましょうねという合意形成のしくみなんだ、とわたしは思う。「だからおれはあのとき反対したんだ!」なんて言い訳はそもそもナンセンスなわけです。
悪法もまた法なり
そのことに気づくと、この言葉の重みがだいぶ違って感じられるんじゃないか。ルールはルール!ルールは絶対!というのは簡単だけど、そこには同じ社会の一員としての合意形成の視点がすっかり抜け落ちているような気がするのです。
ルールに従いさえすればよい
やれルール化しろ、守らないやつは罰せよ、と狂ったように主張したがります。不安や怒りからくるこの主張の行き着く先は、誰にでも有効で綿密なルールの整備と、厳罰化。。。この無限ループです。ルールが整備されれば、わたしたちはいちいち煩わしいことに悩まされることもないし、ルールに沿ってさえいればよいのだから、全てをルールのせいにして過ごせばよい。それはある意味正しい。
それならば、わたしたちの生活全てをルール化してしまえばよいではないか、と思ったりしたことはないだろうか。
例えば、わたしたちに最適化されたAIがあって適切な行動をレコメンドされたらどうだろう。朝7時に目覚ましがなる。ゆっくりとコーヒーを飲んで、9時に会社に行って上司に「◯◯◯」と報告することが決まっていて(そうすれば怒られる心配はないし)、上司はそれをみて「◯◯◯」だと評価することが決まっている(そうすれば部下を嫌な気分にさせることもない)。この時間にこの道を通る(嫌いな人と合わなくてすむ)ことが推奨されて、決まった時間に決まった人と合って決まった食事をして、お決まりの小洒落たセリフを発したりする。これに従わない場合は状況に応じで懲罰が課される。でもこの通りに生活すればあなたは余計な不安に煩わされることなく平穏な一日を過ごすことができるでしょう。サルでも暮らせる素晴らしき社会ができあがる。
信号機を撤去したブータンの王様
昔ブータンで交通量の多いメインストリートに信号機を設置したら、それをみた王様が怒ってすぐに信号機を撤去した、なんてことがあったらしい。都市化したわれわれ日本人からすると、高度に成熟した都市の効用がわかっていない、やれやれ、、、なんてちょっと文明人きどりで上から目線の思いがよぎったりする(笑)
ただ、もうちょっと真剣に考えてみると、人間が機械にコントロールされるのか、人間が機械をコントロールするのか、人の意思や選択の尊厳はどこにあるのか?という問題で、その理念に対する思いが日本人のそれよりもブータンでは強く表れているということです。人はより「自律」的に生きるべきだというのが、ブータンの王様の主張なのでしょう。
これは確か養老孟司先生が言ってたんだけど、ルールに従えばよい(思考する必要がない)という都市化が進んだ文化と、自律的に行動せよ(各々が状況に応じて思考錯誤する)というブータンの文化ではどちらが人として高度な要求をされているかといえば、後者じゃないかと。
だからこそルール化はしないほうがいい
わたしは原則的にルールというものは100%守られるべきだと思っています。以前、仕事を疎結合化するなんて記事の中でルールについて述べたことがありますが、ルールってやっぱり100%守らなければ効果は薄い。90%守られるルールって実はあんまり意味がないんじゃないかみたいなことをわたしはシステム導入や業務改善のお仕事の経験から思ったりします。
多様化する社会のなか個人が些細なことに煩わされず、自由な社会生活を享受するためにも、高度な社会基盤には適切なルールはあってよい。でもだからこそ、「何をルール化するのか」がとても大事になってくる。だってルール化したからには守らなきゃ意味がない。でもルール化することで実はわたしたちの主体性というのは失われていく。昨今、ルール化や厳罰化を求める人々は主体性を失った思考しないサルと化してしまっているのじゃないかと思わずにいられないこともしばしば。
ルールは守らなければいけない!。。。だからこそ、ルール化はできればしないほうがいい。
ルールを守らせること
ちょっと話が横道に逸れてしまうかもしれませんが、ルールって人間の本性から生まれる真理などではなくって、社会のなかでみんなと折り合いをつけるための方便でしかありません。その方便としてのルールをどのように守らせるのか。その「運用」の話にも少し触れたいと思います。ルール違反をしたときの罰や裁きの話です。
これは内田樹先生の受け売りですけども、誰かが何かの損害をもたらしたときに責任をとれ!なんて言葉がよく聞かれますが、どのような損害も起きてしまったことを復旧することはできても、「なかったこと」にすることはできません。
例えば、あなたの持っていた大事な結婚指輪が盗まれて売りさばかれてしまったとします。そのとき、その指輪と同じものを買ってあなたに返すことはできるかもしれません。しかし、あなたが負った心の傷を「なかったこと」にすることはできませんよね。捕まった犯人が厳しく裁かれたところでその事実は変わりません。つまり起こってしまったことに対してどのように裁かれようともそれを完全にチャラにすることは原理的に不可能であるということです。
目には目を歯には歯を
この言葉はやったらやりかえせ!ってことだと理解している人も多いと思いますが、これは「同罪刑法」と呼ばれるもので、起こした罪と同等の報いを受けたなら「それ以上の責任を遡及してはならない」ということです。責任の押し付け合い、負の連鎖を起こさないための戒めです。親を殺されたからと相手の妻を殺す、その報復にと兄弟を殺し、やがては子供を殺す、、、そうやって永遠に続く負の連鎖を止めるための法なんです。
罪を完全にチャラにすることはできないわけですから。さもなければ報復は無限に続いてしまう。
罪に対してわたしたちができること
ですから、裁くという行為は「公」であるのが望ましいんです。むしろ、そうでなくてはなりません。個人が裁きを下すと、また報復合戦になってしまいます。だから昔のマサカリを持った死刑執行人は黒い布で顔を覆っていたんです。あれは素顔を持った「個人」ではなく顔を持たない「公」の執行だからです。
一方で、裁かれた罪を「赦す」行為もまた必要です。罪は先ほど述べたとおり「なかったこと」にはできません。それは赦されることではじめて振り出しに戻るんです。この赦す行為というのは反対に個人でなければなりません。公にあなたを赦しますと言ったところで、罪は消えないし癒えることもありませんから。赦しはとても個人的なものでしかありえません。
すると、わたしたちにできることってなんだろう?
もうおわかりだと思いますが、正義を振りかざして罪を犯した者を糾弾したところで世の中が好転することはまずないでしょう。裁きは顔を持たない「公」の何かが合意形成のもとに厳密なルールに則ってただ執行されればよい。一方で、わたしたち「個人」にできることはどこまでいっても、その「罪を赦すこと」。それだけしかないのです。
自律を促すこと
ダン・アリエリー教授がある実験結果を紹介してました。目の前に不正を起こしたくなるような甘い誘惑があるとき、それを制御するために厳しいルールを設けることは一定の効果がある。でも、もっと効果があるのはその人の良心に語りかけることなんだそう。
その人がどういう思想や宗教観をもっているかなどに関係なく、人は多かれ少なかれ良く生きたいと願っていて、その心にリーチするほうが人は自律的により善い行動を選択するようになる。
それは例えば、カンニングを辞めさせるためにルールを厳罰化するのではなく、試験の前に聖書を読むとか(聖書を目につくところに置いとくだけでもよいみたい)、意図的に「愛」「道徳」「正義」みたいなワードを試験官との会話にまぜこむとか、そういったことだけで不正は激減したりする。
自律の文化とグローバリズム
またちょっと横道に逸れますけども、海外に行くと驚くほど違った宗教観や文化をもった人たちの集まりなのだと実感することがあります。実際に海外で生活してみると、異なるバックグラウンドをもった相手の主張や個性と折り合いをつけ社会として先に進むためにはどうすればよいかということが歴史の中で吟味され、それが教育や生活習慣にまで浸透しているのだと感じると思います。それぞれの国や文化にはそれぞれの「折り合いの付け方」が存在しているということだと思います。
田坂広志先生がどっかで書いてたんですけど、罪や罰を恐れて行動規制をする欧米と違って、日本人の行動原理は「恥」を恐れるが故に自己を律する(自律)という文化にもとづいた美意識なのだと。
それを聞いたときにハタと思ったんです。わたしはかつて「同調圧力」みたいなものに嫌気がさして日本から逃げ出した経験があるんですけども(笑)帰国して思うのは、同調圧力なんてものはハナからなくって、実は日本の自律的な意識を欧米に見習ってルール化しようとしたことで生まれてしまった罪の意識だったんじゃないか。
電車で困っているおばあさんがいたら、相手を慮る美意識からただ席を譲ればいい。でも、相手を慮るというあたりまえにあった習慣がルール化されたとたん、それはおしつけがましい「同調圧」とも取れる罪の意識に変わる。ルールでないものをルール化しようとしたことで起こっている誤謬ではないか。あぁ、だからわたしは「優先席」のルールがあまりスキじゃないのかと、そんな風に腑に落ちるところがありました。
自律性というのは、もっと個々に多様で自由に満ちた意識であっていい。
多様化とグローバル化の矛盾
これもグローバル化によって起こった時代の洗礼なのかもしれません。やれ「多様性」だ「個性の尊重」だと主張する一方で、わたしたちは強大なグローバリズムのもと規格化されることがより高度で文明的だという観念のなかで生きています。もちろんそれは高度に発展する都市社会において、ある意味では正しい。
ただ、人間の自然な個体としての世界と意識の世界が切り離され、わたしたちは発展の下にその意識だけが「同種」の人間というくくりで規格化されてゆきます。同種の人間の住む地域性はどんどん失われ、いまやパリもニューヨークも東京も同種の景色を持つようになりました。それはむしろ多様性とはほど遠い「画一性」の中で新しい社会というのは構築され続けているように見えます。
将来わたしたちの社会はより高度な発展をもたらすために、より厳格化したルールのなかで個人の自由が保障されてゆくのだろうか。または、個人や文化の成熟の中で自らの自由を自ら律する方向に回帰してゆくのだろうか。どちらがいいとか、正しいとかいう答えはありませんが、そこにはまだ見ぬ未来への選択の余地が残っています。
さらりと書くつもりが、あれもこれもと長くなってしまいました。きりがないので、そろそろ締めくくります。これから新しい世代がどういう世界を望むのか、結論はありませんが考える一助になったらうれしいです。
りなる
参考
#ルールはルール #自律 #文化 #哲学する
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
