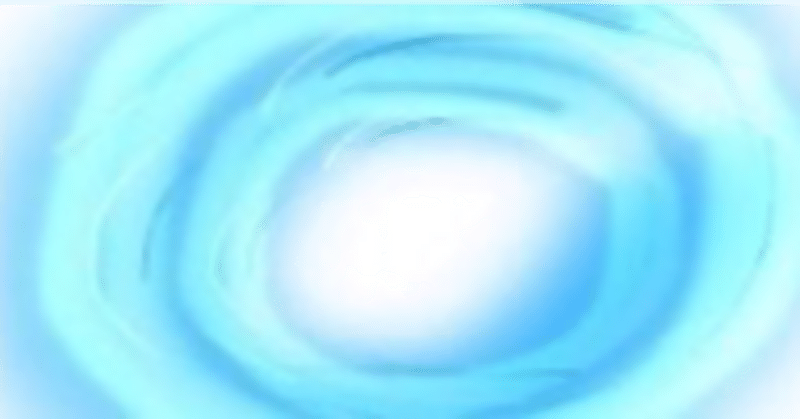
客観的な信仰は存在するか(前編)
本日は、脱会のステップシリーズからは少し脱線しまして、
「客観的な信仰は存在するか」というテーマで少し書いてみます。
私は、エホバの証人というキリスト教系の宗教団体に所属していました。
何かの宗教を信じる姿勢を信仰と言いますが、
この信仰とはどこまでいっても主観的なものにならざるを得ないのではないかと
最近強く思います。
今日はこの「信仰」について少し考えてみたいと思います。
信仰の定義
エホバの証人では、信仰とは「理性的なものである」と教わります。
その根拠となるのが、次の聖書の一節です。
信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。
シンプルであるものの、なかなか理解の難しい聖句だと思います。
ちょっと分解してみます。
信仰とは、、
① 望んでいる事柄を確信すること
であると同時に、
② 見えない事実を確認すること
だということになります。
まずは、動詞の部分から見てみましょう。
信仰とは、「確信する」「確認する」ことである。
それぞれを辞書で引いてみます。
確信…かたく信じること。信じて疑わないこと。
確認…はっきり認めること。また、そうであることをはっきりたしかめること。
つまり、信仰とは、
1、信じて疑わないことであり、
2、その根拠をはっきり確かめること
によって成立すると言えます。
ここまでよろしいでしょうか。
それでは次に目的語(〜を)の部分を考えます。
信じて疑わないのは「望んでいる事柄」であり、
はっきり確かめるのは「見えない事実」です。
望んでいる事柄とは、
エホバの証人で言うところの
「楽園の希望」「復活の希望」「エホバの主権が立証されること」などが
挙げられるでしょうか。
他方、見えない事実とは、
神や天使といった霊的存在が確かに存在することや、
聖なる力(聖霊)があること、祈りが聞かれること
聖書が神の霊感を受けて記された書物であること
などがあると思います。
整理すると、
神の存在や、聖書の神聖性という見えない事実を検証して得られた信念を土台として、(後半部分)
その聖書に約束された様々な将来の希望がきっと起こるだろうと信じ続ける(前半)
これが聖書的な信仰の定義となりそうです。
だいぶ冗長になってしまっておりますが、
定義を決めておかなければ、話を展開していくことが難しいので。。
今回は、この定義に沿って話を進めていきましょう。
見えない事実を確かめる
さて、まずは「見えない事実を確かめる」という点ですが、
初っ端から問題にぶつかることがお分かりかと思います。
見えない事実をどうやって確かめるのか?
ということです。
神が存在することや、聖書が神からの書物であると
どのように確かめられるでしょうか。
もちろん、エホバの証人でもこうした疑問に対する答えは用意されています。
例えば、神の存在に対しては、
・世界には必ず始まりが必要であるから神は存在する
・生物の生態や体の構造などを観察することで、偉大な設計者である神の存在が前提される
・惑星の配列などの秩序を見ることで、それらが偶然生じたのではなく、意図的に創造されたものであると分かる
といった説明があります。
しかし、ここには二つの壁が存在します。
一つは、
それぞれの理由として、神の存在が”要請される”だけであり、
その存在を証明するものにはなっていないという点です。
例えば、
確かに、「存在するものには始まりがあるのだとすれば、全ての始まりがなければならない」という理屈は筋が通っています。
しかし、では全ての始まり=神になるかと言われれば、そうだとは言い切れません。
現に、宇宙の始まりはビッグバンとすることだってできてしまいますし、そうした考えが主流です。
※ビッグバンを神が起こしたと考えることもできるではないかと思われるかもしれません。しかし、これ自体もそう説明”できる”というだけで、そうであったと結論することはできないのです。
このように、現実の事象から、神の存在を認めようとするためには、
どうしても単なる論理的帰結+αが必要になってしまいます。
もう一つの壁は、
なぜ
神=聖書の神
であると断定できるのかという点です。
仮に世界の始まりとして「神」が存在したとして、
なぜそれが聖書を書かせたものと同一の存在であると言えるのかを説明できません。
世界には無数の宗教が存在しており、
それぞれが創造神を認めています。
なぜ、未開の土地に根付いた宗教の創造神ではなく、
聖書の著者としての神が唯一の創造神と断定できるのでしょうか。
それは、西洋中心主義という歴史的・政治的要因による帰結だと言える可能性だってあると思います。
それでは、見えない事実を確かめることはできないのでしょうか。
いえ、そうではないと思います。
「立場を決める」ということ
先ほど、私は神の存在を認めるためには、
論理的帰結+αが必要であると述べました。
結論から言えば、
この「+α」が信仰の核になる部分なのではないかと思うのです。
分かりやすく説明します。
例えば、私たちは原子を肉眼で捉えることはできません。
しかし、「原子」というシステムを用いることによって、世界の様々な現象に対して説明がつきます。
また、「時間」というものについてはどうでしょうか。
時間は目に見えません。
もっと言えば、時間というものは昼と夜の周期、
季節の移り変わりを区切るための”便宜的発明”であり、
その存在を証明できる類のものではありません。
しかし、私たちはそれらを当然のものとして受け入れていますし、
それこそ存在するものとして受け入れています。
これも一つの信仰ではないかと思うのです。
つまり、
「これこれが存在する」という立場を取る
これこそが信仰ではないかということです。
もっとも、原子や時間を存在すると決めるというのは、
特に代償があるわけではないのに対して、
神が存在するという立場を取ることによって、生き方に制約がかかってきます。
(例えば、他の神を崇拝できないなど。。)
つまり、信仰には、
「私は神の存在を信じる」という主体的なステップが欠かせないのであり、
逆に言えば、
事実だけを並べて、信仰にたどり着くことはできないのではないかと思うのです。
これがタイトルで提起した「客観的な信仰は存在するか」という質問の意味です。
実は、キルケゴールというデンマークの哲学者は
「信仰は主体的なものである」と述べていました。
たとえ諸事実が出揃ったところで、「信じる」
平たく言えば「コミットする」という段階がなければ、
信仰へと至らないのではないでしょうか。
また、キルケゴールは信仰を結婚(愛すること)に例えています。
この人と結婚することにしようと思った時、
その人でなければならない客観的な理由などは存在しません。
もちろん、その人が結婚相手としてふさわしい理由をいくつか挙げることはできるでしょう。
性格がいい、価値観が合う、見た目がタイプだ、などなど
しかし、いくら理由を挙げたとしても、その人と結婚すべき絶対的な理由はありません。
ただ、「私はこの人と結婚するのだ」という決意によってのみ、先に進むことが可能になります。
まとめます。
・いくら客観的事実を集めても、神の存在などを証明することは難しい(それが神でなければならない、もっと言えば、聖書の神でなければならない絶対の理由にはならない)
・信仰は、それら事実がいわば”ある程度”集まったところで、「私は信じる」と立場を決定する跳躍によって生まれる
この点を踏まえた上で、信仰のもう一つの定義を考えます。
長くなってしまったので本日はここまでにして、次回続きから参りたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
