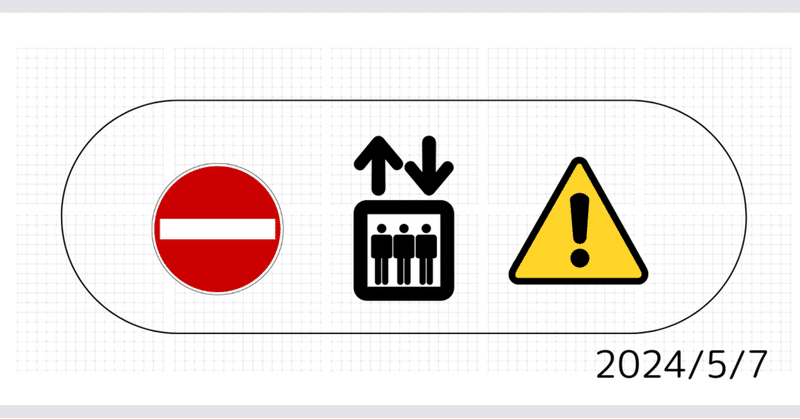
ピクトグラムの起源と魅力
こんにちは。れごです☺️。
記号って、わかりやすくてシンプルで伝えたいことがパッと伝わる素晴らしいデザインが多いから大好きなのですが、
身近にある記号と言えば、ずばりピクトグラムでしょう!
記号の中でも特にピクトグラムには魅力的なデザインが多い!
というわけで今日はピクトグラムについて深堀りします!
それではいきましょう!
初代ピクトグラムは東京オリンピックにあり?!
東京オリンピック2020の開会式のうち、5分ほどの短い時間で行われた『動くピクトグラム』。
面白くて完成度の高いパフォーマンスが記憶に残っている人もいると思います。
この演出を監修したのは世界的なパントマイムパフォーマーの『が〜まるちょば』のHIRO-PONさんです。
弟子のGABEZの2人とともに自らも舞台に立っています。なんと中の人だったんですね。
ところで、ピクトグラムの発祥は東京オリンピックだったことをご存知ですか?
2020年?いやいや、1964年の東京オリンピックです。
当時は現代ほど外国人観光客が多くなかったので、多言語案内掲示板がほとんどありませんでした。
そこで、東京オリンピックのデザイン専門委員会の委員長だった勝見氏が中心となり、当時の若手デザイナー11人でオリンピック競技などを含めた全39種類のピクトグラムを作りました。
オリンピックで多くの外国人の目に留まったことに加え、デザインナーがピクトグラムの著作権を放棄したため、誰もが自由に使えるようになって世界中に広まる大きなきっかけになりました。(デザイナーさんたちありがとう!)
グローバル化した時代背景によってピクトグラムが生まれたのですね。
デザインのメリット・デメリット
そもそもピクトグラムは何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号の1つで、2色で表されることが多いです。
よく似たものにアイコンがありますが、ピクトグラムと比べると言葉の補足や事前知識が必要なものもあります。(2色とは限らずカラフルなものも多いですね。)
それに比べピクトグラムは必要な情報をひと目で理解することができるため、便利なコミュニケーションデザインであることがわかります。
ピクトグラムのデザインの特徴をまとめると:
メリット
ひと目で意味がわかる

色によって何を訴えたいのか、直感的に判断することができる

シンプルな絵柄が多く、多少距離が離れていても判断できる

日本語がわからない人でも意味が通じる
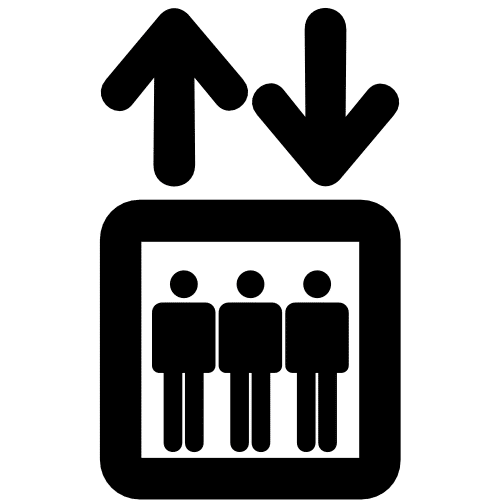
デメリット
正確に伝わらないことがある
文化・風習に依存することがある
ピクトグラムは全世界の人に向けたものが多いから、誰でもわかるようなシンプルなデザインが多いですね。
パーツが少ないからその分本質を付かないと意図を伝えられないところが難しいけど、どのピクトグラムも美しくできていると思います。
突然ですがピクトグラムクイズ!
Q:非常口のピクトグラムはなぜ緑色か。

ヒント:

☆☆☆
A:その通り!緑色は炎の中で視認性が高い反対色だからです。
早くわかりやすく意味を捉えられるように考え抜かれたデザインなのですね。
確かに見るだけで楽しいし、どのピクトグラムも初見でなんとなく言いたいことがわかるところがすごい。
視覚言語の祖、オットー・ノイラート
先ほどピクトグラムは東京オリンピックで生まれたと書きましたが、視覚言語自体はさらに40年以上前からありました。それがアイソタイプです。
アイソタイプはオーストラリア人のオットー・ノイラートが作りました。
きっかけはノイラートが戦争経済学の第一人者であったことから「ドイツ戦争経済博物館」の館長に任命されたこと。
展示物が大量の戦争経済情報であったため、ノイラートはものを持たない博物館としてグラフィカルな統計図を展示の中心にしました。
彼はこの展示物には読解するためのルールが必要だと考えていました。
そして新しい知識を身につけ始める初期段階では、絵はことばよりもコミュニケーションに有効な手段であると考えていたため、
教育を受けられない人にもわかるように視覚する方法を考えました。この独自の手法をウィーンメソッドと呼びます。
彼は統計を単に線や棒で表すのではなく、車に関するものは車のシンボル、産業なら工場のシンボルを使って実際の統計図表に登場させました。
ノイラートは絵文字を考案した上に自らがデザインし適応していく方法も考えています。
さらにウィーンメソッドは版画家のゲルト・アルンツと大学で数学を修めたマリー・ライでマイスターらの協力を得て発展し、最終的にアイソタイプ(ISOTYPE)という名に変わり世界中に広まりました。
ISOTYPEはInternational System of Typographic Picture Educationの頭文字を取ったもので、「国際絵ことば教育システム」と訳せます。
アイソタイプは絵文字どうしを繋げることで単に単語的意味ではなく別の意味を表したり、組み合わせてことばを修飾したり、繋げて文章のように意味を膨らませることができます。
これがアイソタイプが絵ことば(ISOTYPE)と呼べれる所以でした。
ノイラートは言語に続くものとして、どの言語とも一致する補助言語として視覚表現が世界基準で必要としていると確信していました。そして生まれたものがアイソタイプなのです。
今日ではピクトグラムと呼ばれる種類の絵文字の祖として視覚言語を表現するキッカケと方向性を示した重要な事例となりました。
☆アイソタイプを始めピクトグラムなど視覚言語の意義はここにあると思います。今の世界は視覚言語で溢れています。視覚言語は記号らしく見てわかりやすいことと、言語らしく組み合わせて新たに意味を作れることどちらも持っているところが一番の魅力だと感じました。
調べていてとても面白かったです!最後に参考元があるので気になったら読んでみてください。
それではまた!
リンク先が貼れなかったのでこのまま書きます。対処法が間違っていたらコメントで教えてください🙇♀️
https://tsunagaru-design.jp/archives/479
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
