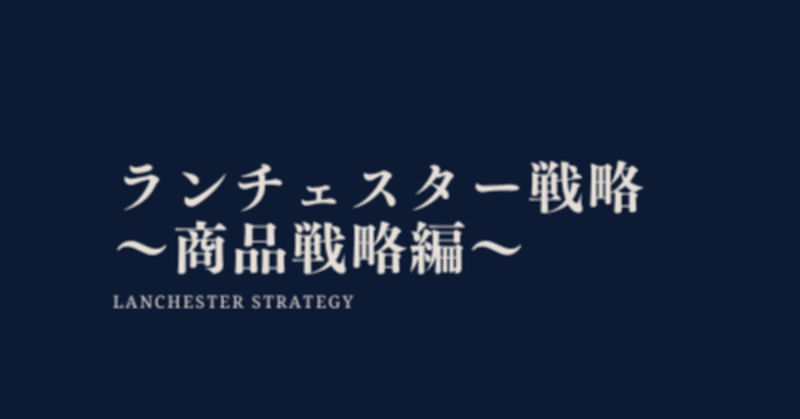
戦略好き必見 ランチェスター戦略【商品戦略編】
いつも記事をご覧いただきありがとうございます。
Biz Craftです。
今回ご紹介する記事は弱者のための戦略で有名なランチェスター戦略について、商品戦略にフォーカスして解説いたします。
時折noteで例えを用いてイメージしやすくなるよう心掛けました。
なお本記事は以下の方に有益となるかと思います。
✅戦略好きな方
✅経営に興味がある方
✅これから副業・起業を考えている方
ランチェスター戦略とは?
ランチェスター戦略の起源は、第一次世界大戦時のイギリスの航空工学者フレデリック・W・ランチェスターによる戦闘力の数値化の研究から生まれました。
彼は戦闘形態によって戦闘力の計算式が異なるという法則を発見しました。
この法則は後にビジネスに応用され、市場シェアや競争力の分析に使われるようになりました。
このランチェスター戦略は、日本では企業コンサルタントの故田岡信夫氏が紹介したことで広く普及しました。
ランチェスター戦略には弱者と強者の戦略があります。
弱者の戦略は、第一法則に従って一騎打ちのような局地戦や接近戦を行います。
弱者は強者には数の面ではとても敵いませんから、数ではなく質を高めることで強者に対抗します。
具体的にはビジネスの領域を絞ったり、差別化、一点集中、陽動作戦を行ったりします。
一方、強者の戦略は第二法則に従って広域戦や遠隔戦を行います。
強者はすでに数で優っているので、さらに多くの市場や顧客を獲得することで弱者を圧倒します。
具体的にはマス広告や新製品を打ち出したり、総合力でゴリ押ししたり、誘導作戦を行ったりします。
ランチェスター戦略は、弱者でも強者に勝つ方法を見つけることができるメリットがある反面、デメリットもあります。
デメリットとしては、市場や競合の変化に対応できない可能性や、戦略の選択や実行にコストがかかることなどが挙げられます。
またランチェスター戦略はあくまで理論であり、実際のビジネスにそのまま適用できるとは限りません。
「ランチェスター戦略に頼りすぎると、市場や顧客のニーズに応えられなくなる可能性もあります。
そのためランチェスター戦略を適切に活用しつつ、柔軟に対応できるようにすることが重要です。」
☝※ここは是非強調しておきたいポイントです。
1.商品戦略の概要
利益の源泉である商品計画を立てることは最重要ポイントとなります。
商品の種類によっては、資金の投入量や営業手法が変わったりします。
ですから、どのような商品を中心にして展開していくのかという商品計画を立てることが重要になってきます。
そのためにまず必要なのは、なぜその商品を選択したのか、その目的をはっきりさせることです。
何となく決めたり、周りがやっているからなどの理由では自分らしい商品を作ることができません。
noteで例えるなら、ウケのいいテーマ記事を何となく選択するのではなく、自分独自で実践したノウハウを織り交ぜたりするなどです。
目的を決めたら次にすることは、情報収集です。
情報収集の対象先は以下の5点です。
・顧客
・競争相手
・社内
・サプライヤー
・社会環境(政治・経済・社会・技術)
自社だけで考えた商品は、往々にして販売先とのズレが生じてしまいます。
また、商品自体が技術的に陳腐化していたり、法律規制の対象になっていたりしますので、絶えず外部環境の情報収集は欠かせません。
同時に自社の内部環境を知ることも重要です。
その際には以下の問いを投げかけると、自社を客観的にとらえる上で有効です。
「主力商品の市場占有率はおよそ何%を占めていて、利益率の推移は伸びているのか下がっているのか?」
➡これをnoteの共同マガジンで例えると、
「自分の記事は全記事中何%を占めているのか?スキ率とフォロワー増加率の推移は伸びているのか?」
「商品のライフサイクルは導入期・成長期・安定期・衰退期のどの段階に位置しているのか?」
➡これをnoteで例えると、
「自分の書いているテーマは、テスト期・スキ数好調期・スキ数安定期・スキ数減少期のどの段階なのか?」
では以下から具体的な商品戦略の説明に入っていきます。
2.商品の差別化
差別化した商品をゼロから生み出すのは至難の業です。
ですからまずは新聞・雑誌などのメディアから差別化に成功した先行事例を複数集めましょう。
そして次に自社だったらそれをどう応用するのか考え続けることが大事です。
私も仕事柄、他社のホームページや業界紙などで独自のカラーを打ち出している会社の情報を参考にすることがあります。
時間はかかりますが、こうやったらどうだろうかなどのアイデアが湧いてくる時があります。
それをすかさず自社の環境に落とし込み、実行可能なのかどうかの検証を行うようにしています。
3.商品を細分化する
自社の№1の商品を見つけ出すには、商品そのものを市場全体で見るのではなく、商品を顧客側に立って考えてみることが大切です。
例えば「用途・価格・コンテンツ内容・デザイン」などを細かく分けて考えていくと競合が見落としている点に気付くことがあります。
つまり先行事例の構成要素を分解して、構成部分を変えてみる。
それだけでも差別化につながる可能性があります。
noteで言えば、今活躍しているクリエイターさんの成功要因を分解してみて複数の要素を抽出してみる。
そしてその要素を自分独自の強みに置き換えてみる、などでしょうか。
4.強い競争相手がいない商品を重視する
せっかく自社に最適な№1の商品を見つけたとしても、既に強い競争相手がいたら消耗戦になってしまいます。
他社との類似品や模倣されやすい商品では、数やインパクトの面でいずれ負けてしまうのは明らかです。
強者が知らないニッチ分野や参入するメリットがない商品に的を絞りましょう。
noteでも同じ話題を提供しているクリエイターさんは多く、初心者は知名度やクオリティの面では到底敵いません。
ですから、あくまでも強者がいないテーマにこだわり続けることが差別化のポイントになります。
5.弱い商品、強くなれる見込みのない商品をカットする
商品数が多くなると、自社内で管理しきれなくなりますし、経営資源の分散が起こります。
ですから定期的に商品の点検をし、基準に満たない商品は思い切ってカットしましょう。
こうすることで一つの分野に時間を投入することが可能になり、ライバルとの差をつけることが可能になります。
noteでいえば長く継続してきたけれども、スキ数、スキ率がほとんどない記事やマガジンなどは、一度こだわりを捨ててスッキリさせましょう。
そうすると残った主力テーマに注力することができるようになります。
6.1位を目指す商品は一つに絞る
自社独自の強い商品を作るには、重点商品を1つに絞ることが肝要です。
既に複数の商品がある時は、初めの商品を確実に強くした後で、次の商品に移りましょう。
これはマーケティングでいうところのフロントエンド、ミドルエンド、バックエンド商品に似ています。
まずは核となるメイン商品で1位にならなければ、次の商品に移ることは出来ないですし、紹介することもできません。
まずは重点商品でブランド化を図り、信頼と実績を積み重ねましょう。
noteでいえばメインテーマで確実にリピーター読者を定着させた後で、次のコンテンツを作ることなどが当てはまるでしょうか。
7.1位の商品ができるまで忍耐強く続ける
せっかく強い独自の商品を計画しても、それが実現するまでには長い時間がかかります。
途中であきらめない忍耐力が必要となります。
一見、戦略とは関係ないように思える要素ですが、結果がどう転ぶかは短期間では分かりません。
ですから中長期的な視野で状況を見据え、定期的に見直しを図ることは戦略以外のなにものでもありません。
またこれはどんなことにでも必要な、最低限の能力と言えると思います。
例えばnoteやXなど何でもよいのですが、今フォロワー数が万単位、インプレッション数が多大な影響力を誇っている方も、最初は弱小アカウントだったに違いありません。
今の部分だけを切り取るから、敵わないなと思い途中で諦めてしまうのです。決して一部分だけを見ないようにしましょう。
まとめ
以上、ランチェスター戦略の商品戦略編を解説いたしました。
なるべく一般論だけでは終わらないように時折noteなどの例を持ち出してみましたが、いかがでしたでしょうか?
商品=コンテンツと置き換えれば、ランチェスター戦略は有効に活用できるのかもしれません。
しかし冒頭でも申し上げたように、戦略はあくまでも理論ですから実践を通して身に付けないと意味がありません。
理論⇔実践の繰り返しで初めて戦略が生きてくるのだと思います。
私もこうして記事を作成しながら、今後も強い商品作りを心掛けていきたいと思っています。
次回は客層戦略をご紹介する予定です。
ここまで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
本記事が何かのお役に立てれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
