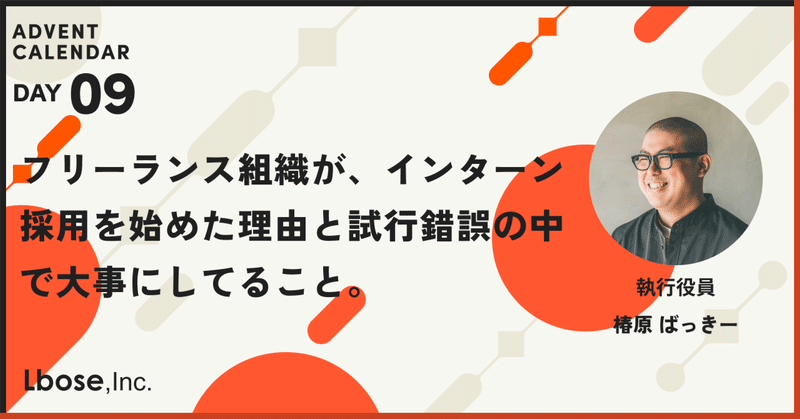
フリーランス組織が、インターン採用を始めた理由と試行錯誤の中で大事にしてること。
どうも、株式会社エルボーズの椿原です。
弊社は、場所や時間をこえて人が仕事できる環境、またそのような環境で人が繋がりコラボレーションすることで社会に新たな価値を生み出していける環境をつくっていきたいと考えているスタートアップです。
2017年で創業しましたが、当時からフルリモート・フルフレックス組織だったので、2020年に熊本へ本社のみを移して活動しています。


ちなみに、このnoteは、弊社のアドベントカレンダー9日目の記事です。
学生インターンの採用を考えている〜という経営者や採用担当者の方向けに、弊社が学生メンバーの採用を始めた理由や、学生の採用や育成に関して何を大事にしているか?など書いてみたいと思います。
はじめに
現在、弊社では3名の優秀な大学生が働いてくれています。

(採用担当)

(マーケティング担当)

(マーケティング担当)
冒頭から発信の伝わりやすさのために「インターン」と書きましたが、社内では社員やフリーランスのメンバーと区別などはありません。
同じようにコミュニケーションしており、それぞれがプロとして業務を担当し、責任をもって活躍してくれています。
ちなみに、新卒採用は行なっていないため、基本的には、大学卒業後はどこか他社へ就職していくことを前提とした雇用です。
アドベントカレンダーの一環で、学生メンバー3人が書いてくれたnoteも最後に貼っておきますので、もしよければそちらもご覧ください。
新卒採用しないのにインターン採用をする理由
いくつかの課題は絡みあってるのですが、一番感じていた課題は、組織の同質性・多様性に関する部分です。
弊社は、フリーランスの集まりから拡大したような会社で現在もフリーランス・復業の方が多数参加しており、20代後半以降で一定経験のあるメンバーが多め。
また、「"誰と、どこで、何をするか"を、もっと自由に。」柔軟な働き方ができるフルリモート・フルフレックスを2017年の創業時から導入しており、様々な働き方を経験してきた上でこのような環境がいいという方が多く、社員は子育て世代が多めです。
組織も拡大している様子を見ていると、多様性が下がり、同質性が上がり始めた感覚がありました。
「こんな組織にしたい!」「そのために、こんな方を採用したい!」という話があり、その対象となるような方が働きやすい環境づくりを進めていく引力も働きます。
組織の同質性が高いと、コミュニケーションが図られやすく、一体感も高まりやすくなる。そのため、マネジメントの統率もとりやすくなり、上司に対する支持や信頼感も高くなる…なども言われているのですが、デメリットもあります。
同質性が高い組織のデメリットとしては、組織として異分子に対する受容性が低くなりがち。それが進むと異なる考えや意見をもつメンバーが発言・行動しづらくなる可能性があります。
メリットもわかるが、執行役員として採用の責任者をやっている身としては、極端なアプローチではあるかもしれませんが、早い段階でデメリットの方を抑えておきたい。
で、事業拡大のためにお願いしたい仕事など考えたら、新卒社会人の方に副業などで入ってもらうより、ある程度まとまった時間で学生の方に入ってもらった方が相性良さそうだな〜考えました。
どのように学生と出会い採用したか?
こういうこともあるかもな〜と思いながら、学生イベントの会場としてオフィスを提供したり、意識高めな学生をイベントに誘ったり、地道なコミュニケーションを続けてました。
これ、多分あんまり再現性ないですよね。すいません、次いきます!!笑
採用で意識していること
採用と育成の話を書く予定なのですが、まずは採用にあたっての話。学生とか置いといて、スキルや経験がないor少ない方を採用するとすれば、今なにができるか?より、現状からどこまで成長できるか?が重要です。
その観点で、採用段階で意識していることは下記の3つ。
現状に関して渇望感があること。
たまにオフラインで会えること。
近い世代の同僚をつくること。
まず、弊社はフルリモート×フルフレックスの組織なので、基本的に業務は各自が自宅などがやるわけですが、各々が自己管理できることを前提に働き方の裁量権をメンバーに委ねています。
そのとき、学生の方だと「今後のキャリアが不安なので、もっと成長しなければいけない」「別の場所で働いてたけど思うように成果を出せなかった」のように、エネルギーを持っていてくれた方が一緒に仕事しやすいです。
その上で、「会わなくても業務はまわるんだけど、数ヶ月に一回飲みにいける」とか「競い合い、教え会える同期がいる」という状況を作れた方が、特に仕事の経験が少ない学生メンバーだと、精神衛生的に健全に気持ちよく一緒に成長していけることが多いなと感じています。
まだまだ試行錯誤の途中ですが。笑
育成する上で意識していること
こちら、一度書き出してみて、学生メンバーに「他になんかあると思う?」と聞いてみたら、最終的に10ありました。笑
で、10あるものを1つずつ説明しているとめちゃくちゃ長くなるので、大きく4つに整理して書かせていただきます。
概要?だけ先にいうと、ゴールを設定し、それに近づけるよう一緒に考え、一緒にアクションしていくという話なのですが、弊社でのインターンの場合「量質転化」の精神で、インプット量・思考回数・手を動かすことなど、どれも徹底的に回数や量を重視します。
では、それぞれ書いていきますが、まずはこれ。
中長期的な人生として目指すものも一緒に考える。
ゴールの設定ですね。別に大学生のメンバーだけにやっていることではないですが、中長期的にどうなりたいか?どうありたいか?が粗くともあればそれで良いですし、なければそれを考えるために今なにをするべきか?を一緒に考えます。
このゴール設定も変化していく前提の仮設定です。私もですが、多くの人は自分「好きなこと」「得意なこと」なども、その時点で知っている・見たことある・体験したことあるものの中でしか考えてないので、人生経験が増えたら変化するのは当たり前だと考えています。
なので、定期的に話しながら「やっぱ、あれは違うかも?」とかも大歓迎で、常に中長期的なゴールをアップデートし精度を上げ続ける。
ゴールを設定したら、次は情報のインプットの話です。
まずは大量の情報をインプットをしてもらう。
社会や業界における一般論と、自社の話を分けて伝える。
1の質問に対して10の情報量を返す。
興味ありそうな領域の話題を一方的にシェアし続ける。
ゴールに向けてアクションするためにも、業務に参加し活躍するためにも、それを下支えする絶対的な知識量は必要です。
極端な話、業務の中で日常的にでてくる専門用語やメソッドなどを知らないと会話にも入れません。
弊社の場合、チームに参加して最初1-2週間は徹底的に情報のインプットに時間を使っています。
業界のこと、担当することになるマーケティングや採用などに関すること、自社のことなど、ネットの海にわかりやすい動画やドキュメントも多数公開されていますし、自社のNotionも多数のドキュメントがあるので、それを徹底的に読み込んでもらう感じですね。
その上で、調べてもわからない単語や「業界の一般論だと◯◯のようですが、自社だと△△△のようで、これなぜですか?」みたいな質問を思いついたときに書き出してもらって、ひたすらに私が回答し続けます。
そのとき、1の質問に対して「それに関して、自社の場合は、□□□みたいな経緯があって、今は×××と考えている」みたいなもの10の量で回答。
弊社の場合、事業は現状toBですが、例えば、彼女らがキャリアとしてはtoCの事業に関わってみたいとすれば「うちとは関係ないけど〜」と、そちらの彼女らが興味ある領域も参考に紹介。
業務の中で、まったく違う領域の話が参考になるというのも普通にありますし、自分が興味をもってる領域からだとインプットの吸収率も上がると思っているので、本当に日々大量の情報を渡します。笑
まっさらな状態の大学生が持ってる知的好奇心やスポンジのような吸収力に期待。
ゴールを設定し、ベースとなる知識を確保したら、次は行動です。
できるだけ早く何かの役割と責任を持ってもらう。
高速&大量に手数を出し、高回転の試行錯誤をする。
プロ意識を求め、プロとしてコミュニケーションする。
余白を渡し、挑戦の機会をつくる。
こちらは、量質転化を基本ではあるのですが、合わせて「自分ごと化」して当事者意識を持てる状態をつくれるよう意識しています。
量が質を生み出すとしても、ただ手を動かすだけではダメで、早期に高品質なアウトプットを生み出すためには、思考や仮説検証を高速高頻度で回転させることが重要です。
初期は各種アクションのKPIを成果ではなく、アクション数にもってもらうことが多く、手を動かし続けないといけない状況を作ります。
なので、1つ1つのアクションに関して使える時間は限られているのですが、責任や挑戦の機会を持ってもらうことで、その短時間の思考の質を上げれたらという思いです。
最後は、これです。
小さな成長も伝え、小さな違和感も声かける。
本当に日々、急成長・急変化していくので、思ったら思ったときに伝えるようにしています。
成長でいえば「専門用語モリモリの会議で普通に会話できるようになってる」とか、そういうのからですね。自分では気づきづらい部分もあると思うので、伝えるの大事です。
違和感の話で言うと「なんか最近チャットの返信遅いな」とか、「いつもチャットで返信するのにスタンプだけの反応増えたな」とか、「いつもより作業の進みが遅い」とかですね。
これ、早期で把握したいのは働きすぎやメンタル不調。
「体調を崩してるというわけでもないけど、なんか調子良くない」みたいな状態などで、本人が思い当たる原因や改善できそうか?などを聞いておくの大事だと考えています。
本人も気づいてなかったり、本人からはどうしても言いづらかったりするので、フォローしたり業務量を調整したり、先回りです。
おわりに
書き終えて思いましたが、採用や育成の話「学生だから」「インターンだから」とかではなく、スキルや経験がないor少ない方を採用して育成するとすれば…という話を書いただけな気がしますね。笑
事業の成長にも貢献してくれてるので、組織としてもありがたいのですが、ちょっと個人的な話を書きますが、「自分のため」で頑張るのは、エネルギーを出し続けるために限界があると感じることが増えました。
本当にまっさらな状態で、将来に希望を持ち、知的好奇心や成長欲をもってきてくれる人達との仕事は活力をもらえます。「この人達のためにも、良い機会を提供したい」という想いが、最後のもうひと踏んばりの力をくれます。ありがたいです。
大学生であれば、まだご両親に助けてもらってる部分がある人達も多いですし、これからのキャリアに影響を与える重要な期間、学生生活の貴重な時間をいただくことへのプレッシャーはあります。
引き続き、真摯に向き合っていきたいと思います。
では、実際に働いてくれてる3人の学生のnoteを貼っておきますので、よかったらこちらもご覧ください。
また、弊社では絶賛採用強化中ですので、少しでも興味を持っていただけましたらぜひwantedlyにてご連絡ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?


