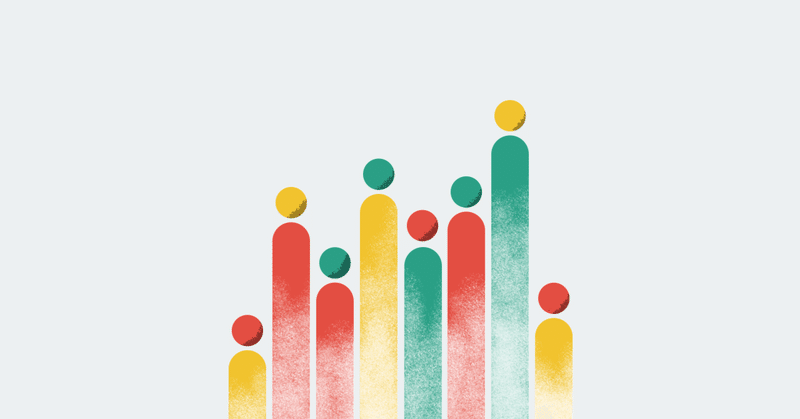
決着をつけないから次が見えてこない話。
経済の専門家ではないのですが、人口がどんどん減少している日本の経済の成長率は、前年比で減少になっていくはず、と考えています。海外から稼いでくるにも、昭和の日本ほどの技術力や製造する力の国際的優位性を失ってしまっている平成・令和では、資本的収支は別として、成長は無理と思います。
事実、日本は経済成長率2%が目標でこの十数年、政府や日銀で日本経営が行われてきたのですが、達成できませんでした。そもそも前年比で成長するという固定観念を、捨てる必要があると感じるわけです。
未達成や、ダメだったとき、失敗したときには、気づいた時にそれを認めて次に進むことが大切と感じています。本当に成長したいとき、まずは認めることだと思います。
現状は、波風が立たないようにしているのか、「もういいや。」と現状肯定や維持になっていると感じます。つまり「決着」をつけられていないということです。認識できないと次への学びにはならず、時間の使い方でいうと「時間の消費」であり「時間の投資」にはならなかったということになります。そこで私流の結論は、この数年を振り返ると経済成長率2%は、今の日本の仕組みでは不可能なのだと認識することに至りました。
これはキャリアのお話にも通ずる部分があります。キャリアプランも低成長もしくはマイナス成長を前提に考える必要があると思います。さらには、職業選択において日本ではなく海外で働く、というキャリアプランも出てくると思います。
最近、Twitterも、Facebookも、Amazonまでもが、人員削減。事業収益で賄えない人件費は人員削減をする。ダメなら結論を出して次に進む、決して先送りしないアメリカという感じでダイナミズムを感じます。
日本は、法制度上、簡単に社員に辞めていただくことはできません。実際、人員削減にあたっての個人面接、胃が痛む経験をしたこともあります。立法府、法律家、経済の専門家なども含めて、雇用の流動性を労使であらためて構築する必要あると感じます。
「リスキリング」を実のあるものとする労使関係を真剣な経済取引として成立させるためにも仕組みとしても必要な改革と思います。
以上
≪参考資料≫
・ 人員削減・対話型AI、激動のIТ業界:「日経MJ」2023/3/1
・ GAFA大量人員削減でも高度人材は「年収2億円超」、熾烈な獲得競争に日本は勝てるか/野口悠紀雄 一橋大学名誉教授ダイヤモンドオンライン2023/1/26
・・・R5/03/14・・・
