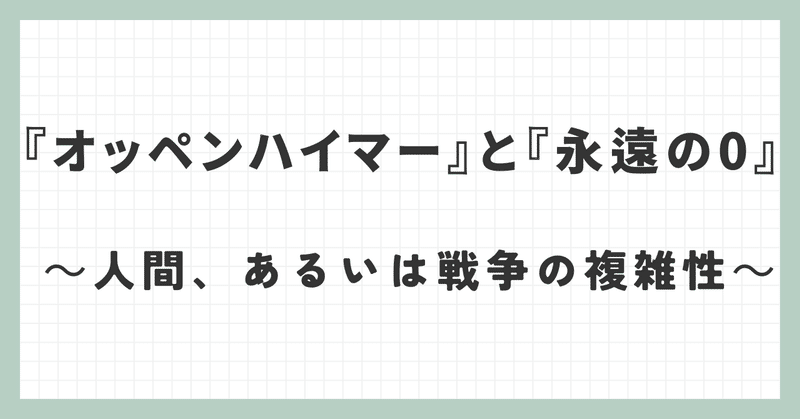
『オッペンハイマー』と『永遠の0』 ~人間、あるいは戦争の複雑性~
映画『オッペンハイマー』のノーラン監督は『ゴジラ -1.0』を絶賛している。また、『ゴジラ -1.0』の山崎貴監督も『オッペンハイマー』を絶賛している。
山崎貴は『オッペンハイマー』を「悪い人間、素晴らしい人間を決めつけていない、その両方が渾然一体となっている」と評しており、ノーラン監督も同様のことを語っている。
そこで思い出したのが同じく山崎貴が監督した『永遠の0』だ。
山崎貴監督作品は原作の大筋はそのままだが「本質」を大きく改変していることが多いので原作を知っている人はいったんそれを忘れて以下を読んで欲しい(なお私も原作は読んでいない)。
本作のストーリーを簡潔にまとめると、主人公が特攻隊員だった祖父(宮部)について調べていくうちに、優秀な戦闘機乗りであると同時に優しい人間であり、自分の家族が不幸にならないよう配慮した上で同僚の命を救うため特攻におもむいた事を知るというものだ。
「特攻隊員だったが優しい人間だった」「他の人間を救うために自身が犠牲になる」という大筋自体は珍しいものではない(ただ細部にところどころ工夫が凝らされており、映像表現は『アルキメデスの大戦』と同じくすごいので観る価値はある)。
だがストーリーについて、ラストのラスト、奇妙なシーンがある。特攻で米艦艇に突っ込む直前、宮部は歪んだ笑みを浮かべるのだ(なおこれは原作には無いシーンらしい)。もちろん宮部は「これでアメリカ人を殺せるぜヒャッハー!」と思うような人間ではない。
これに関しては(ノーテンキに特攻を賛美する人間でも)疑問に思った人が多いようで、検索すると沢山の考察ページが出てくる。以下のページにも色々な考察が載っている。
「これで楽になれると思ったから」「家族の元に帰れる(どういう意味?)」といった説が多いようだが、それなら「穏やかな笑み」になるはずだろう。
ある程度説得力があるのは「悲しみのあまり(現実逃避のため)笑うしかなかった」というものだ。だがそれならもっと自暴自棄な笑みになるのではないか。
「ニヤリ」とした笑みになった理由を最も説明できるのは「戦闘機乗りとして戦いの喜びが表出した」というものだろう。だが、敵兵が死ぬことさえ避けようとした宮部が死ぬ直前とは言えそんな事を考えるだろうか。
しかし、これは確かに「正解」に近いかもしれない。ラスト直前のシーン、宮部はその卓越した飛行技術で米軍の攻撃を掻い潜り、米兵も驚愕の声を上げる。
宮部がそうしたのは意識的なものではなく「本能的」なものだったのかもしれない。だがその時彼は気づいてしまったのでは無いか。特攻を批判し自分の命を引き換えにしてでも同僚を守ろうとした自分さえ、飛行技術(=敵兵士、人間を殺すための技術)を磨いており「普通の作戦」「普通の戦争」は当然のものとして受け入れていた人間だったのだ、と。そして飛行技術を「活かして」自分とともに大量の米兵を殺そうとする直前、自分も同じ穴の狢に過ぎない事を自覚してしまった彼は自嘲するしかなかったのではないか。
オッペンハイマーの「複雑さ」はまた別の種類だと思うが、宮部もまた「善人」としての性質を大きく持ちながら「戦闘狂」でもある複雑な人間だった、あるいは戦争によってそうならざるを得なくなったのだ。
以前の記事でも書いたように、『ゴジラ -1.0』におけるわだつみ作戦では十死零生(必ず死ぬ)の特攻を否定するのみならず「一人の死者も出さない」ことを目標としそれを実現する。それは特攻のみならず「戦争」そのものを否定するために必要だったのかもしれない。
P.S.
余談だが、『オッペンハイマー』を「オッペンハイマーを擁護している!」と評する人間、『ゴジラ -1.0』を「ナショナリスティックな作品」、そして映画の『永遠の0』を「戦争賛美」と評する人間が多いが、あまりにも「誤読」する人間が多い。
サポートいただけると記事を書く時間や質問に回答できる時間が増えます。
