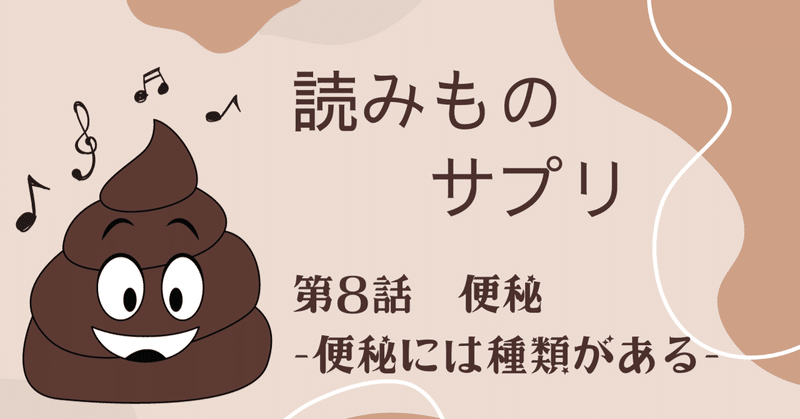
体と薬と健康と・・・第8話 便秘②
~便秘は3種類あるんです~
健康コラム『読み物サプリ』。
第5話・第6話の「腸活」の流れから、第7話からは「便秘」の話をしています。一般的な便秘には3種類の便秘があるということに触れて終わっていましたよね。
▼第1回目は「なぜ便秘になるのか」をテーマにしています
そこで今回は、その3種類の便秘
弛緩性便秘
習慣性(直腸性)便秘
痙攣性便秘
についてお話しさせていただきます。
話の中で「S状結腸」や「直腸」という大腸の部位の名前が出てきますので 下の図で、どの辺りのことかご確認ください。

弛緩性便秘(しかんせいべんぴ)とは
弛緩性便秘は大腸の機能が低下して、大腸の運動(蠕動運動:ぜんどううんどう)が悪くなり、うんちが通常よりも長い時間、大腸内に留まるようにななることで、水分が過剰に吸収され、便が硬くなり、排便が困難になって便秘になります。
原因としては食物繊維の摂取量が少ないことや、排便でいきむときに使う腹筋が弱くなることなどで起こります。

運動をあまりしない方やご高齢の方、野菜などの食物性繊維をあまり摂らない方に多く見られるようですね。
あまりひどくない場合の対処法として、食事で食物繊維を意識して摂るようにしたり、寝る前に出来るストレッチをしたりすることがおススメ。

これだけでも軽い腹筋運動になります。続けやすいので、運動不足の方はチャレンジしてみてください。
ちなみにこの軽い腹筋運動は、私が第2腰椎破裂骨折で入院していた際に腰に負担をかけずにできる軽い腹筋運動ということで、理学療法士の方が教えてくれたものです。
習慣性便秘(しゅうかんせいべんぴ)とは
習慣性便秘は、直腸(ちょくちょう)まで便がきているのに出ない便秘なので、直腸性便秘ともいいます。
このタイプは習慣的に便意を我慢する方や、下剤や浣腸を乱用している方によく起こります。学校や仕事などで、トイレに行きたくないと思って便意を我慢したり、トイレに行きたくても行けない環境でついつい我慢してしまったりということが多い方に多い便秘ですね。

この便秘は、日常的に我慢することが習慣になって起こっているので、朝トイレに行く習慣をつけることと、併せてトイレタイムに時間的ゆとりを持つように心がけて、排便の習慣をつけることが大切です。
その上で朝食はしっかり食べて、食物繊維と水分もしっかり摂るといいでしょう。
痙攣性便秘(けいれんせいべんぴ)とは
痙攣性便秘は、自律神経のバランスが乱れ、大腸の緊張状態が続き、腸管に痙攣性の収縮が起こります。特に、直腸の前の「S状結腸」での痙攣性の収縮が持続すると、直腸までのうんちの輸送が妨げられて便秘となります。

痙攣性の便秘の主な原因は「ストレス」。
そのため、改善方法としては日常生活におけるストレスの要因からの離脱が基本です。困難な場合は薬物療法などがありますが、この場合は病院での診療が必要ですね。
注意しなければいけないのはこの痙攣性便秘の場合は、便秘の解消として市販されている「刺激性の下剤」を使用すると、腹痛などの症状を悪化させることになるので、使用するべきではありません。
便秘薬については、次回に詳しくお話しさせていただきます。
まとめ
今回お伝えした、3種類の便秘についてまとめておきます。

以上、第2回目は「便秘の種類」についてでした。
少しマニアックで難しかったかもしれませんが、一言で「便秘」といっても種類があることを知っていただければと思います。第3回は、「便秘薬」についてです。お楽しみに。
記事が参考になった!面白かった!という方は
スキ💛を押していただけると、記者の励みになります。
(すでに押していただいた方はありがとうございます)
▼執筆している薬剤師
