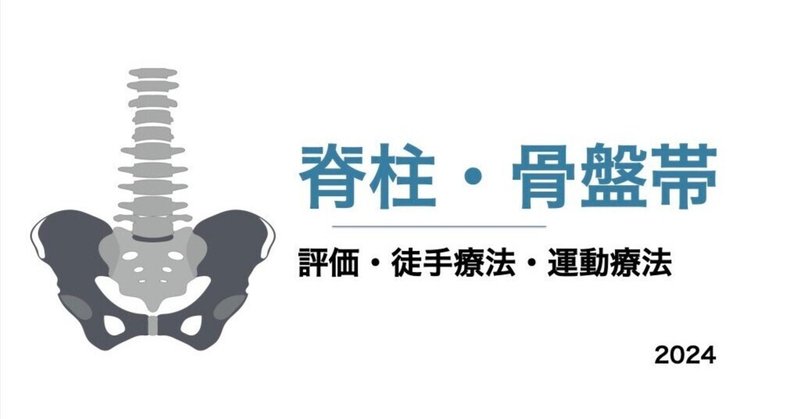
脊柱・骨盤帯の評価・徒手療法・運動療法
2024.3-2025.2 投稿予定記事
3月 姿勢観察と動作評価
姿勢制御能力改善のための姿勢改善エクササイズ
4月 股関節の評価・徒手療法・運動療法
ヒンジ動作の改善(股関節屈曲・内旋制限に対するアプローチ)
5月 脊柱・骨盤帯の評価・徒手療法・運動療法
大殿筋機能改善のポイント(股関節伸展制限に対するアプローチ)
以降の投稿予定記事はこちらから
●記事の購入について
思考の整理のマガジン(500円/月)を定期購読していただくことで、購読開始月以降の投稿記事(2回/月)を全記事見ることができます。
購読開始月以前の過去記事は個別でのご購入(500円/1記事)となりますので、月1回以上記事をご購入させる場合は定期購読がお買い得となります。
1.脊柱の重要性
脊柱に付着する筋は遅筋線維が多く、身体の位置を適切に受容し、適切な位置に修正するために必要な固有受容器が豊富であることから、姿勢制御能力を高めるには脊柱に付着する筋群の柔軟性・筋機能を保つ必要があります。
遅筋は脊柱を安定させる役割を担い、脊柱の伸展運動では多裂筋が脊柱を分節的に動かし、長肋筋や広背筋は大きな力発揮を可能とすることから運動制御能力を高めるには、各筋の機能を高め役割分担できるようにすることが重要となります。
脊柱の弯曲と力発揮
脊柱の分節的な運動の低下は、脊柱全体の可動性低下を招き、脊柱の役割の1つである緩衝能力の低下を招くことになります。
脊柱は3つの弯曲があることで衝撃を吸収できるとされています。
ニュートンの第3法則|作用・反作用の法則
物体に対して力を加えるとそれと同等の力が返ってくるとされており、地面を押せばその力の分だけ地面から反作用として力が返ってくる。
その反作用の力を吸収できることでその動作は成り立つことになる。

脊柱は3つの弯曲(頸椎前弯・胸椎後弯・腰椎前弯)を有しており、その弯曲によって緩衝しているとされています。
脊柱弯曲が減少することで、力を発揮(作用)させようとした際に受ける力(反作用)を脊柱の弯曲によって緩衝することができなくなるため、筋出力が制限させることになります。
そのため脊柱の可動性を保ち、筋出力を発揮しやすい状態を保つことためにも、体幹を機能させる最初のStepが、脊柱の可動性を改善することから始めます。
脊柱の可動性を獲得することで、抗重力伸展運動がスムーズとなり、体幹に対して垂直負荷を加え体幹筋を機能させるトレーニングを行うことができます。
2.仙腸関節の構造的安定性と機能的安定性
ここから先は
¥ 500
よろしければサポートお願いいたします!
