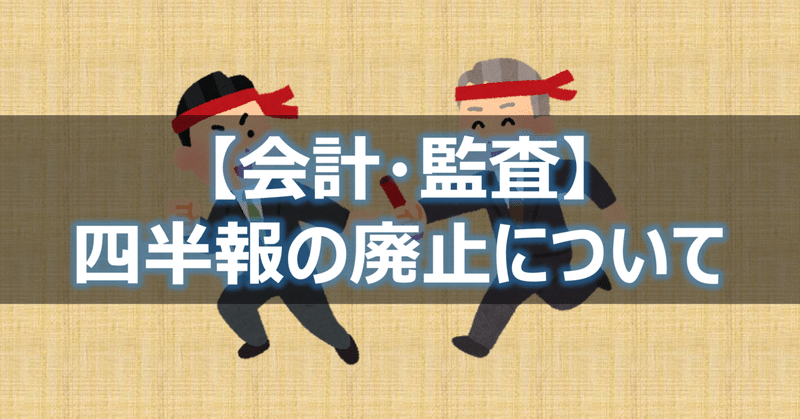
【会計・監査】四半報の廃止について
こんにちは、りんりんです!
今回は会計・監査関連の情報共有として、昨今話題の四半報の廃止について執筆してみたいと思います。
たまたま調べる機会があって色々見ているうちに、一本書けそうだなと思い立って筆を取ることにしました。
「うち変則決算なんだけど、四半期報告書はいつから廃止?」
「半期報告書って四半期報告書と何が違うの?」
「短信のレビューって必須なんだっけ?」
...etc.
こんな疑問に応えられるようなnoteに出来ればと思います。監査法人の皆様や上場企業経理の皆様の参考になりましたら幸いです。
また、もし記載内容に間違いがあったら、コメントでご教授いただけますと幸いです…!
※内容は筆者個人の見解に基づくものであり、特定の組織の公式見解ではないことにご留意ください。
1. いつから適用されるの?
企業会計基準第 33 号「中間財務諸表に関する会計基準」は、4/1に施行される運びとなりましたが、新法への移行は決算月がいつであるかにより異なります。
決算月毎の適用時期の違いは、ASBJの「企業会計基準第33 号「中間財務諸表に関する会計基準」等の概要」に記載の図表3が、非常にわかりやすくまとまっています。

私が思う注意すべき点は、移行タイミングの違いはもちろんのこと、2Qの報告書について、四半期会計期間が4/1を跨いでいたとしても、旧法に基づく開示がされるケース(四半期報告書として開示)と新法に基づく開示がされるケース(半期報告書として開示)があるという点です。
2. 短信に対する監査人のレビューは必須?
結論から申し上げると、「1Q・3Qは原則任意、2Q・通期はこれまでと同じ」となります。
原則というのがミソで、会計不正等により、財務諸表の信頼性確保が必要と考えられる場合には、監査人によるレビューが義務付けられることとなります。
具体的な要件も定められておりまして、日本取引所グループの「四半期開示の見直しに関する実務の方針」によると、以下の項目となります。
(義務付けの要件)
①直近の有価証券報告書・半期報告書・四半期決算短信(レビューを行う場合)において、無限定適正意見(結論)以外の場合
②直近の有価証券報告書において、内部統制監査報告書における無限定適正意見以外の場合
③直近の内部統制報告書において、内部統制に開示すべき重要な不備がある場合
④直近の有価証券報告書・半期報告書が当初の提出期限内に提出されない場合
⑤当期の半期報告書の訂正を行う場合であって、訂正後の財務諸表に対してレビュー報告書が添付される場合
※①・③について、直近の有価証券報告書・半期報告書・四半期決算短信(レビューを行う場合)・内部統制報告書の訂正を行う場合で、要件に該当する場合も対象
※④・⑤については、財務諸表の信頼性の観点から問題がないことが明らかな場合を除く
また、このレビューの義務付けがいつまで続くかというと、義務付けの要件に該当した後、次に提出される有価証券報告書・内部統制報告書において、①〜④の要件に該当しない場合に解除されると定められています。
要件該当後すぐの四半期短信や半期報告書で無事に無限定適正意見が出たとしても、少なくとも年度末までは解除されないということです。
3. 1Q・3Q短信はどう変わった?
1Q・3Q短信ついては、開示の内容に一部変更があります。
変更内容については、日本取引所グループの「四半期開示の見直しに関する実務の方針」p.10に記載の表が、非常にわかりやすくまとまっています。

レビューの有無の記載のほか、投資家からの要請を反映した形で、注記の拡充が行われています。
なお、レビューに関しては、適正表示と準拠性に関するものがあります(旧法の四半期報告書レビューは適正表示の枠組みです。)。適正表示の枠組みと準拠性の枠組みの違いについては、監基報200第12項(13)に書いてありますので、必要に応じて下記ご参照ください。
1Q・3Q短信では、JPXが開示を求める上記の事項以外については省略が認められており、開示省略を行う場合は準拠性に関するレビュー、開示を省略しない場合は適正表示に関するレビューとなります。
肝心のレビュープロセスの違いと保証水準などは、同じく日本取引所グループ「四半期開示の見直しに関する実務の方針」に記載の下記図表が参考になると思います。


4. 2Q・通期の短信は?
法定開示が存続することを理由に、2Q・通期については、現行の取り扱いが維持されます。特に変更はありません。
ただし、以下2点については留意しておいた方がよろしいかと思います。
①開示資料名が2Qは「中間決算短信」ではなく、「第2四半期(中間期)決算短信」とするいること。
→1Q・3Qも短信が開示されることから、それらとの連続性を踏まえて、このような取り扱いとなっています。
②2Q・通期短信は、レビュー・監査の対象外であること。
→1Q・3Qにおいて、レビュー義務付け要件に該当したとしてもレビュー対象外となります。
5. 四半期特有の会計処理は?
ASBJ「企業会計基準第33 号「中間財務諸表に関する会計基準」等の概要」によると、四半期特有の会計処理等については、概ね旧法の取り扱いを踏襲する形となっている旨が記載されています。
ただし、一部の会計処理については、別個に検討が行われております。どれも「まあそうなるよね」という取り扱いとなっておりますが、ひとつひとつちゃんと説明すると引用先と同じ文章量が必要になってしまうので、ここでは項目の列挙のみとし詳細は割愛します。
気になる項目については、文末にある参考文献リンクから、原文を読んでみていただければと思います。
本会計基準等は、(2)開発にあたっての基本的な方針に記載のとおり、中間財務諸表の作成にあたり必要となる会計処理について基本的に四半期会計基準等の会計処理に関する定めを引き継いでいるが、中間財務諸表において期首から 6 か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とすることに伴い差異が生じる可能性がある次の項目について個別に取扱いを検討した。
(ア) 原価差異の繰延処理
(イ) 子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日
(ウ) 有価証券の減損処理に係る中間切放し法
(エ) 棚卸資産の簿価切下げに係る切放し法
(オ) 一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理
(カ) 未実現損益の消去における簡便的な会計処理
6. 監査はどう変わる?
特に重要な点は、JICPA「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める四半期財務諸表等に対する期中レビューに関するQ&A(実務ガイダンス)」の”Q2:東証短信レビューに適用するレビュー基準等”に記載されている項目です。

金商法の期中レビューと、それ以外の期中レビューでは基準が変わると書いてあります。
これ、要は、中間レビューはレ基報第1号、Q1・Q3はレ基報第2号が適用されるということです。
半期報は金商法に基づく開示ですが、決算短信はJPXの開示規制に基づく開示です。先述の通りQ1・Q3の開示書類は短信のみですので、金商法に基づいた開示はそもそも無いわけで、任意/義務・適正表示/準拠性は関係なく、当然にレビュー基準2号を用いることになるというわけです。
参考文献
ASBJ「企業会計基準第33 号「中間財務諸表に関する会計基準」等の概要」
https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2024/2024-0322.html
日本取引所グループ「四半期開示の見直しに関する実務の方針」
https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/quarterly-disclosure/index.html
JICPA「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める四半期財務諸表等に対する期中レビューに関するQ&A(実務ガイダンス)」
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240328gac.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
