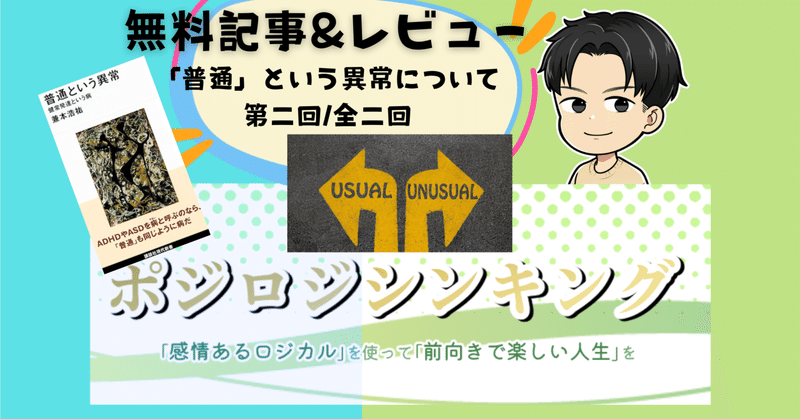
「普通」という異常
前回は「普通」との付き合い方や「普通」との距離の取り方についてご説明をしました。「普通」って何なの?という点についても言及してみますので、ますはそちらをご一読いただければと思います。
今回は第二回ということで、以下の書籍を参考にしつつも、
「普通」が持つ異常性について考察していきたいと思います。
ちなみに、本著のamazonレビューの低評価は内容が理解しづらかったというもの。これは心理学的な専門用語や哲学的な用語を絡めて説明をしているので、初学者が置いてけぼりにされたということでしょう。
このあたりのわかりづらい説明は本記事ではバッサリカットします。
「普通」という異常について
「大きな物語」と「小さな物語」について
専門用語はあまり使わずに話を進めたいのですが、
本著では、「大きな物語」と「小さな物語」が繰り返し使用されます。
しかし、それほど難しい意味ではありません。
「大きな物語」=「皆が信じることのできる思想や考え」であり、
〇〇主義と呼ばれるようなものであったり、イデオロギーと呼ばれるようなものです。
「小さな物語」=これはもっとスケールの小さなもの。
要するに、個人やグループごとにいろんな価値観があってもいいよね、という発想に繋がります。
かつての「普通」たち=「大きな物語」
本著では、「旧来の普通」だったものについて三つに場合分けをして言及していきます。すべては「大きな物語」との関係性において語られます。
①中二病的な人々:「大きな物語を乗り越えられる」と信じる人々
中二病的な人たちは、「明確な仮想敵」をつくりたがる。いわゆる、共通敵という言い方もできるかもしれません。
中二病はネタとして使われがちですが、最近でいえば、「陰謀論者」と呼ばれる方々もこのカテゴリに含まれるでしょう。
陰謀論を唱えている方々が、日常生活について問題をきたしているかといえば、実はそれなりに普通に日常生活を送っているケースが多いのではないでしょうか。
②不安と葛藤しながら、強引に未来を信じる人々:「大きな物語に不安を抱きながら」も信じようとする人々
本著では神経症的な人々と語られます。ある意味で「空しさ」と日々格闘しつつも、それには気づかないように、わざと「思考停止」に陥りがちな人々とも言えます。
新しい価値観に対応できずに、「ただわからなくて怖いから」という理由だけで、否定に回りがちです。そして、自分が「怖がっている」ということもなかなか認められません。
日常的には「色・金・名誉」などのわかりやすい価値に飛びつきやすく、目移りもしやすいです。
実はこのカテゴリの方々ってすごく多くないですか?
特に40歳以上ではこのカテゴリに含まれる方はかなり多いような気がしますね。私の肌感覚ですが。
③かつての企業戦士:「大きな物語に取り込まれ一体化」する人々
②のタイプの人とすごく近いですが、②のタイプと異なり、神経症的な不安は抱いておらず、ただ、目の前のことを必死にこなしているというタイプの方々ですね。
もちろん、うじうじ悩んでも何も解決しないのは事実なので、結果として目の前のことをこなすしかないのですが、人間ときには立ちどまって考えることも重要です。
しかし、目の前を突き進めば大丈夫という妄信で突き進んでいるところもありますので、ふと、価値観がぐらついたときに弱く、うつ病になりがちです。企業戦士の退職後の老後うつも完全にこのカテゴリでしょう。
加えて、わりと一つの道をシンプルに進んできているので、価値観が多様化していく時代には柔軟な対応ができずに問題を起こしがちです。
政治家や役人、企業のトップ、芸能人などの著名人が定期的にやらかし発言をしたりすることもこのカテゴリでしょう。
たしかに、「普通」だけど、異常かも?
前節で三パターンについて言及しましたが、どれも、なんだか「普通と言えば普通な感じがする」し、「異常と言えば異常な感じがする」って思いませんか?そうなんです、普通なんだけど、異常なんですね。
前回の記事でも触れましたが、そもそも、普通というものは絶対的なものではなく、あくまで平均値を基準としてマジョリティというカテゴリに含まれる人々の価値観や考えがベースになって出来上がるものが普通なんですよね。逆に言えばそんな感じで、普通なんてものは「かなりアバウト」なもの、もっと言えば、「雑なもの」とも言えます。
現代の「普通」=「小さな物語」へ
さて、かつての「普通」について先ほど言及しましたが、現代的な「普通」についても次は言及したいと思います。
思想が好きな方ならきいたことがあるかもしれないポストモダンという単語、これって要するに、「絶対的な価値観なんてものはないよね」みたいな感じで「大きな物語」が崩れさっていったことを表しています。
そして、無数の「小さな物語」が生まれる。まさに現代的ですね。
これは経済面で、少品種大量生産から多品種少量生産へと切り替わっていったことともマッチします。
そして、承認欲求の時代=「小さな物語」へ賛同を求める時代へ
現代はSNSが広く普及したことから相互承認が簡単に行えるようになりました。それゆえ、現実世界で承認欲求が満たされなければ、ネット空間にそれらを求めることができます。
そして、現代人の多くは、「現実世界」ないしは「インターネット」を通して絶えず承認欲求を満たしているとも言えます。
あるいは、ここで逆転現象が起きているかもしれません。
承認されたことが「実態になる」
つまり、「承認されたことが物語になる」とでもいうべきでしょうか。
それゆえ、一昔前の知識人からすると、現代のこのムーブメントは「空虚」なものに見えるかもしれません。しかし、只中にいる私たちからすると、特段空虚には映りません。
それは「普通の在り方」が時代とともに移り変わるからです。
今を生きる我々はどうするべきなのか?
まずは、「普通の異常性」を認識するべきでしょう。
「普通の異常性」を認識できれば、「大きな物語」を妄信することもなくなりますし、「承認欲求」に過度に拘泥することからも解放されます。
しかし、大きな問題として横たわるものは、
「その時代の普通」は時代意識として、その時代を生きるための「インフラ」のように存在しているということです。
ですから、「その時代の普通」と距離を取って生活することは困難とも言えます。インフラですから、「その時代の普通」は生活の糧ともなりえるわけです。SNSでの評判が仕事に繋がり、企業の口コミになり、インフルエンサーを生み出すような時代なのですから。
だとすれば、「普通」をある種のツールとして使用する。あるいは、インフラとして利用する。「普通」とはそのような少し冷静な付き合い方をするくらいが実はちょうどいいのかもしれません。
きっと、二十年後の「普通な人々」からすれば、
私たちはきっと「過去の普通」であり、「異常なはず」ですから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
