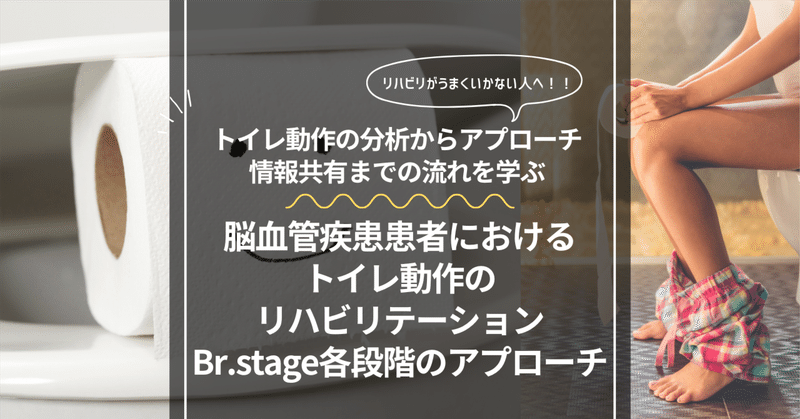
脳血管疾患患者におけるトイレ動作のリハビリテーション:各Br.stageごとのアプローチ方法 〜トイレ動作の動作分析から情報共有までの流れを学ぶ〜
こんにちは、理学療法士の嵩里です。
前回のコラムではBr.stageごとの特性と、次のstageへの課題について説明しました。
>>>脳血管疾患患者におけるトイレ動作のリハビリテーション:Br.stage各段階の特性と課題 〜トイレ動作の動作分析から情報共有までの流れを学ぶ〜
今回は、前回の内容を踏まえて各Br.stageごとのトイレ動作改善のアプローチについてお伝えします。
stageⅠ
弛緩性麻痺のため筋収縮は認めず、ADL場面での麻痺側の使用は難しい段階です。今後のADL動作獲得のために、以下のようなアプローチが考えられます。
連合反応を利用した麻痺側の促通
連合反応とは、非麻痺側を随意的に動かした際に麻痺側の筋収縮が認められることをいいます。次の段階であるstage IIへ回復していくために、この連合反応を利用していきます。促通では麻痺側と非麻痺側を視覚で確認しながら同時に動かすことが重要となります。
非麻痺側の廃用予防
非麻痺側の下肢筋力を評価することは、退院時のADL能力を予測するために有用といわれています。今後、車椅子移乗や起立動作を行うためにも筋力トレーニングを行い廃用予防を図っていきます。
関節拘縮を防ぐ
足関節背屈は起立動作、手指伸展は手すりやズボンの把持というように、関節可動域の維持はトイレ動作獲得に必須となります。手指・上肢・下肢ともに可動域練習を行い、拘縮予防に対してのアプローチを行います。
stage II
stageIIでは連合反応または随意収縮を認める段階になります。そのため、連合反応と随意収縮のどちらが出現するかで、以下のようにアプローチ方法が異なります。
II-1随意収縮がなく連合反応あり→連合反応を利用した麻痺側の促通
II-2随意収縮あり→関節運動を伴わない随意収縮での麻痺側の促通
stageⅢ
stageⅢでは随意的な共同運動が行える段階になります。グレードとしては4段階あるため、分離の評価を行い不十分な共同運動を促通していきます。
屈曲、伸展の一方が出現。ただし不十分
屈曲、伸展の一方が十分で他方が不十分
屈曲、伸展のどちらも出現。ただし一方のみ不十分
屈曲伸展のどちらも十分
上肢
屈曲共同運動が出現すると、麻痺側でズボンを上げる動作の補助が行えます。伸展共同運動が出現すると、ズボンを下ろす、シャツをズボンに入れるといった、下方リーチが行えるようになります。
手指
集団屈曲が出現すると、ズボンや手すりの把持が行えます。しかし手指を伸展し難いため、実際のトイレ動作では手指伸展が行えるstageⅣの分離が必要となります。
下肢
集団屈曲運動が出現すると、端座位で靴や装具を履くために下肢を挙上することができます。集団伸展が出現すると、起立で麻痺側が参加できるようになります。またズボンの上げ下げに必要な上下運動(スクワット)が可能となります。
stageⅣ
stageⅣでは共同運動パターンから脱し関節ごとの分離運動が行えるようになります。トイレ動作の中ではどのような分離運動が必要か、対象患者さんではどの関節の分離運動が不十分なのかを評価し、促通していきましょう。
前腕(回内外)
回内が行えるとシャツをズボンに入れる、回外が行えると手洗いが容易となります。
肩関節
背中に手を回す動作です。ズボンの後ろを自身で修正することができます。
肘関節
肘関節を伸展したまま肩関節を挙上できます。手すりを把持するためのリーチ動作が行えます。
手指の集団伸展
把持した手すりやズボンから手を離すことができます。また手洗いがさらに容易となります。
膝関節、足関節
起立時に足を引くことができるため、上半身重心を足底へ移動し起立が行いやすくなります。
stageⅤ
stageⅤではより複雑な分離運動が行えるようになります。
上肢では肩関節外転位での肘伸展、手指では球握り、下肢では股関節内旋方向の促通を行います。
StageⅥ
stageⅥでは協調的な動きが可能となります。トイレ動作に関しては実用的に行える段階です。ですがスピードや巧緻性求められる場面になるとぎこちなさが出現します。トイレが近く切羽詰まった状態でもトイレ動作が行える巧緻性があるか評価し足りない所を促通していきます。
まとめ
各Stageごとに介入方法が異なる
Stageに合わせたトイレ動作の課題が異なる
Stageを適切に評価し、段階に合わせた介入が必要
参考文献
平野恵健 回復期リハビリテーション病棟に入院した脳卒中重度片麻痺患者の退院時ADL能力に及ぼす因子の検討 理学療法科学 30(4): 563–567, 2015
岡田一馬 脳血管障害片麻痺患者の回復期における基本動作能力の変化 行動リハビリテーション 第6巻 2−7頁(2017年3月)
末廣健児 トイレ動作について考える 特集身のまわり動作と生活関連動作を考える 関西理学8:7-11,2008
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
