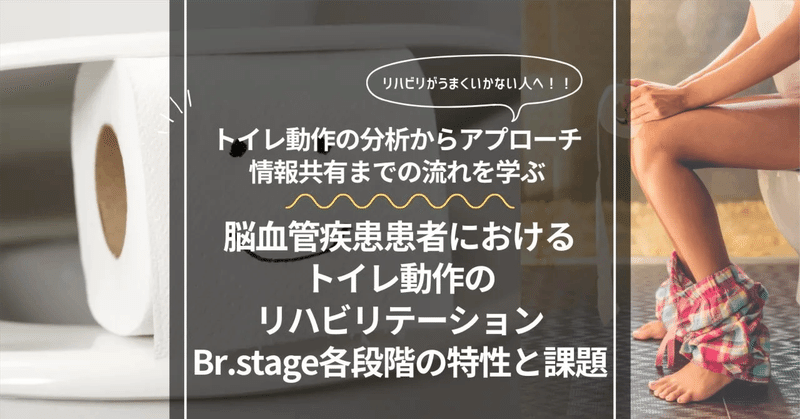
脳血管疾患患者におけるトイレ動作のリハビリテーション:Br.stage各段階の特性と課題 〜トイレ動作の動作分析から情報共有までの流れを学ぶ〜
作業療法士の内山です。前回は手指の巧緻性についてお伝えしました。
>>>脳卒中患者のトイレ動作を考える、手指巧緻動作の必要性 〜トイレ動作の動作分析から情報共有までの流れを学ぶ〜
今回は、脳血管疾患受傷後の方を例に、Br.stageの各段階における特性と次のstageへの課題について説明していきたいと思います。
各stageの詳細
### stageⅠ
**特性:** 弛緩性麻痺
**課題:** 連合反応による筋収縮の促通、麻痺側単体の随意収縮の出現
この段階では、筋収縮が連合反応も含めて全く出ない時期になります。そのため、stageⅡへの課題として、連合反応による筋収縮の促通と麻痺側単体の随意収縮の出現が挙げられます。
◎トイレ動作でできること、できないこと
できること:麻痺側を使用することは難しい。
できないこと:動作全般が難しいため、ROM拡大や随意収縮の出現に向けて機能向上を図る。
### stageⅡ
**特性:** 連合反応、最小の随意運動の出現
**課題:** 共同運動パターンの促通と出現
この段階では、Ⅱ-1レベルで健側の関節運動による連合反応の出現、Ⅱ-2レベルで麻痺側の随意収縮が出現し始めます。そのため、stageⅢへの課題として、共同運動パターンの促通と出現が挙げられます。
この時点では、ベッド上でのリハビリが中心になっていくことが多いので、トイレ動作には一見関係がないように思われます。しかし、両上肢での下衣着脱や立位保持などを考えると、この段階からトイレ動作を意識した介入は必要になっていきます。
◎トイレ動作でできること、できないこと
できること:麻痺側を使用することは難しい。
できないこと:動作全般的に難しい。座位保持や体幹のコントロール機能の向上に向けて、下肢の共同運動パターンの獲得を目指す。
### stageⅢ
**特性:** 共同運動を随意的に行える
**課題:** 分離運動の促通
この段階では、共同運動パターンを習得することで、上肢・手指・下肢の各関節を一色単にまとめて動かせるようになっています。しかし、ADL動作で使うためには各関節が分離して動く必要があります。そのため、stgaeⅣへの課題として、分離運動の促通が挙げられます。
◎トイレ動作でできること、できないこと
できること:伸展共同運動パターンを利用して、下位の着脱動作の補助に使用することができる、トイレットペーパーを切り取る際に蓋の部分を押さえる。
できないこと:手すりの把持、陰部の清拭、自力での立位保持など細かい動きが難しいため、各関節の分離運動を促通していく。
### stageⅣ
**特性:** 痙縮の減少と分離運動の出現
**課題:** より複雑な分離運動の促通と協調運動の出現
この段階では、共同運動パターンから各関節の分離した動きができるようになっていきます。しかし、この段階では、支持側の関節を屈曲位で固定し運動側の分離運動を行うなど複雑な協調運動はまだ困難な状態であります。そのため、stgaeⅤへの課題として、より複雑な分離運動の促通と協調運動の出現が挙げられます。
◎トイレ動作でできること、できないこと
できること:下衣の着脱で麻痺側手指を使用できる、麻痺側上肢での手すり把持、自力での立位保持。
できないこと:清拭動作が全ての範囲は難しいため、体幹をコントロールした状態で巧緻動作を行う練習を積極的に促していく。
### stageⅤ
**特性:** より複雑な分離運動、協調運動の獲得
**課題:** 速さの強弱がある状態での分離運動、協調運動の促通
この段階では、分離運動は出現し始めており支持側の関節が屈曲位に限らず、伸展位の状態でも運動側の関節が分離して動かせるようになってきます。しかし、運動のスピードに強弱がつくと代償動作が出現したり、分離運動が上手くできないことがあります。そのためstageⅥへの課題として、速さの強弱がある状態での分離運動、協調運動の促通が挙げられます。
◎トイレ動作でできること、できないこと
できること:動作全般で麻痺側を使用できる。
できないこと:速さの強弱がつくと、動作が稚拙になる可能性がある。
### stageⅥ
**特性:** 速さの強弱がある状態での分離運動、協調運動の獲得
**課題:** ADLの場面での使用
この段階では各関節を分離して動かすことができる状態になっているため、麻痺側を実用的にADL動作で使用できます。
◎トイレ動作でできること、できないこと
できること:動作全般を通して麻痺側を使用できる。
できないこと:特になし。
まとめ
stageごとの特性を理解し、次のstageへの課題を把握する
stageⅠ~Ⅲまでは代償動作が出ても良いので、関節運動を出していく
stageⅣ~Ⅵは、代償動作に気をつけながら分離運動を促通していく
トイレ動作の分析から評価・アプローチ、情報共有までの流れを学びたいなら、、、
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
