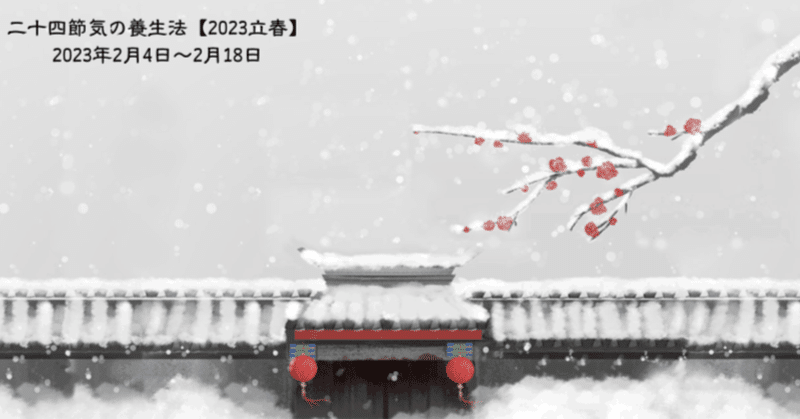
二十四節気の養生法【2023 立春】
2月4日から雨水の前日の2月18日までが「立春」です。いよいよ春ですね。暦便覧には「春の気たつを以て也 」とあります。
二十四節気では、「立春」は一年の始まりと考えます。「立」は始まりという意味で、閉蔵といって万物が閉ざされていた冬から、万物が蘇る春の始まりを示しています。始まったとこなのですぐに万物が蘇るわけではありませんが、まだ凍った土の下では小さな芽が今か今かと生温かい春風が吹くのを待っています。少しづつ昼間が長くなり、太陽も暖かくなり、気温や日照、降雨量が増えることを感じられるようになります。
テレビで「暦の上では今日から春」などと言い、「こんなに寒いのに春と言われても実感がわかないな」と愚痴りたくなりますが、天地を覆い万物を支配する「気」は、冬の「寒」から春に気に変わっています。

昨日は節分で、豆まきをして鬼を追い払い、恵方を向いて恵方巻を黙って一本丸かぶりした方も多いでしょうか? 恵方巻なんて知らないよとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、恵方巻はともかくとして、立春は二十四節気では一年の始まりと考えます。運気学でも立春を一年の始まりの日と考えるので、お正月に初詣に行きそびれたという方は、本日以降に恵方(ご自宅から向かって南南東)にあるお寺でも神社でも教会でもモスクでも…ご自分のパワースポットに出かけて良い気をいっぱい補充して今年一年の健康を祈念してください。
禅寺では立春の日に玄関に「立春大吉」と書いて玄関や門に貼る習慣があります。四文字とも左右対称なので、表からみても裏から見ても同じように見え、入ってきた鬼が勘違いして出ていくという厄除けの意味があるそうです。
今月の癒しの庭園 「旧三井家下鴨別邸」
今月のお庭は下鴨にある旧三井家下鴨別邸をご案内します。場所は京都の賀茂川と高野川が合流し、ここから南が鴨川となる出町というところの北側、下鴨神社(糺の森)の南側にあります。
この辺りも普段よく車では通っているところですが、なかなか中を拝見する機会が無く今回初めてお伺いしました。
出町の三角州から下鴨神社の参道につながる左手に入り口があります。

旧三井家下鴨別邸は、三井財閥の創業家で三井十一家の共有の別邸として明治時代に建築されたそうです。江戸時代の呉服商だった三井家が信仰していた「顕名霊社」がこの地に遷座され、神社をお参りする際の宿舎や休憩所として明治期に整備されたそうです。主屋は「木屋町別邸」から移築されたそうですが、望楼のある木造の三階建て建物が簡素な中にも威厳を誇っています。今でも高層建築の少ない京都では、ここの3階からでも大文字や比叡山、東山連峰などかなり広い地域が見渡せるでしょうね。
門を入ると邸内に入る広い通路があり、すでに豪商の邸宅の趣を感じます。

通路を通って左に曲がると、玄関棟があり、そこからお屋敷内に入って見学することが出来ます。
建物は玄関棟と主屋、その奥に茶室の3棟があり、その前に整備されたお庭が広がっています。伺った時は1月末に降った雪のなごりが残っていました。

建物の中は豪商の邸宅らしく一階にはお庭を眺められる広いお座敷があり、お天気の良い日など軒先に座ってのんびりお庭を眺めていると、池に流れ落ちる心地良い水音が耳を癒してくれるでしょうね。豪商になった気分でお昼寝でもしたいところです。
あと5日ほどすると七十二候「黄鶯睍睆」となりウグイスの初鳴き声も聞こえてくるでしょうね。

春は桜、秋は紅葉、夏は青紅葉や雨上がりの緑鮮やかな苔、そして寒い冬には雪景色など、四季折々のよく手入れされた庭園を眺めて目を癒されながら、カフェも設けられており一保堂さんのお抹茶と上生菓子のセットや小川珈琲のケーキセットなど味覚も愉しめます。

三井家がここを所有する前からあったとというお茶室。慶応4年(1868年)ごろに出来たものだそうで、廊下で繋がっていますが主屋とは離れていて独立していて2種類の茶室があり、にじり口や丸窓、梅鉢型の窓が風情を添えており障子を開けるとここからのお庭の眺めも格別でしょう。
普段は公開されていませんがお茶会やお食事会などに借りることができるそうです。

庭園には苔が生え、下鴨神社の中を流れる泉川から取り入れられた小川から滝が流れ落ちるひょうたん型の池があり、庭園に立体的な美しさを生み出す築山やあちこちに配された灯篭、庭園の格を上げる巨大な鞍馬石の景石にも雪が残っていて冬の風情が感じられます。…と言っても冬の京都はめっちゃ寒い。

最近では温暖化の影響か京都でもあまり積雪はなかったのですが、久しぶりに市内でも10cmほど積もり、大文字がくっきりと浮き上がって見えます。
池面に逆さに映った望楼も素敵でした。

今回はお寺のお庭ではありませんが、明治、大正期の豪商の屋敷構えが良好に保存され高い歴史的価値があり重要文化財にも指定されていてとても素敵なお庭でした。
望楼や茶室は普段は未公開ですが、朝食プランやランチプランなどで上まで登って見学もできるそうです。
抹茶講座やヨガなどのイベントもあるそうですので、京都に来られる予定のある方はぜひお越しになってはいかがでしょう。
日常のストレスフルな毎日から少し離れて、少しの間だけでも非日常を感じることでストレスが癒されますね。また厳しい冬の冷たい気が、心身をピリッと引き締めてくれ清々しい気分になります。
皆さまもぜひ「花鳥風月」を愛でて、心を癒してください。なによりもの養生法です!
二十四節気の養生法【2023立春】
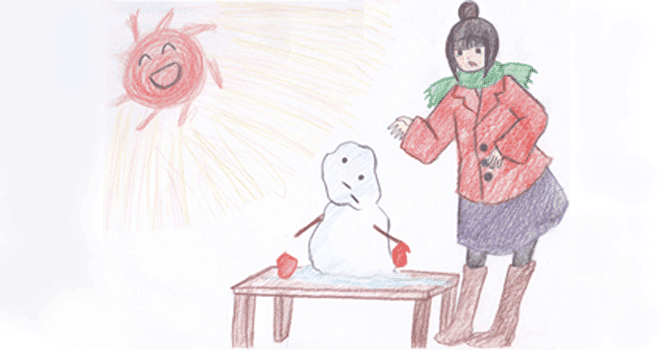
二十四節気って…?
一年の始まりですので、改めて二十四節気って…?ということについて学んでみましょう。「二十四節気」は、殷虚から出土した甲骨文字の研究から、3000年以上も前の殷代(紀元前17世紀~紀元前1046年)にはすでに出来上がっていたと言われています。
テレビやゲームなどがなかった古代の人は、太陽を観察して昼間が一番長い日を夏至、逆に夜間が一番長い日を冬至、その中間で昼間と夜間が同じ長さの日を春分と秋分があることを見出しました。これがいわゆる二至二分と言われ、この二至二分の中間点を、それぞれ立春、立夏、立秋、立冬の四立(しりゅう)と言います。
二至二分と四立を合わせて八節と言い、とても大切な節目の日となります。
二十四節気は、太陽の動きを基準とした太陽暦で、太陽黄経0度の時が春分でそこから1日1度ずつ進み、5日で5度進むと一候となり、さらに15度進んで三候になると一つの節になります。節が六つ合わさり一季となって、季が四つで四季となり一年が巡ります。

古代は月の満ち欠けを基準とした太陰暦が用いられていましたが、太陽の動きに基づいて毎年の農作業をすることが重要となりさらに正確に季節を知るために春秋戦国時代にはより細かく分割した二十四節気が生まれたと言われています。
二十四節気は、地球から見える太陽の位置を軌道にした太陽黄経と呼ばれる太陽が動く道(太陽黄道)があり、太陽はこの上を毎日1度ずつ動いて1年で一周しますが、その太陽黄道を24等分したものが二十四節気になります。
天文学的には、太陽が北緯23.26度の北回帰線に来た時を夏至、南緯23.26度の南回帰線に来た時を冬至として、一年間でこの両回帰線の間を行き来し、そのちょうど中間にあるのが0度の赤道で、赤道に来た時が春分と秋分になるのです。それが二至二分です。
少し話が逸れますが、北回帰線上に居ると、正午に真南に太陽が来た時、太陽の下に立っていても影が出来ない不思議な現象が起こります。日本は北回帰線より北に位置するので正午に真南に太陽が来ても日陰は出来ますが、台湾にはちょうど北回帰線の真上のところがあるので、そこに夏至の正午に立つと太陽が出ているのに影が無い不思議な現象を体験できるそうです。

なぜ冬は寒くて夏は暑いんだろう…?
当たり前のことですが、なぜかと問われたらすぐに答えられない方も多いような…確か中学校ぐらいで習ったような気もしますが…私もその一人。
それは太陽が正午に真南に来た時の角度で起こるのです。
夏至の頃には京都の南中高度は78.4度となりほぼ真上(90度)から陽が射します。そうなると太陽からの陽射しが強くなり暑くなります。
逆に冬至の頃になると京都の南中高度は31.6度の角度から陽が射しこむようになり、太陽からの陽射しが弱くなって寒くなるのです。

暑さや寒さは太陽高度の違いで起こるの…でした。上の絵のように真上に太陽があるほど陽射しが強いため暑くなり、逆に低い位置になれば陽射しが弱くて寒くなります。
下の図でわかるように、太陽の角度は、立春は冬至と7度ほどしか変わらないのでまだまだ陽射しがも弱いためにそれほど暖かくならないのです。
逆に、立秋は夏至と7度ほどしか変わらないので陽射しがまだまだ強いため暑さも変わらず涼しくならないのです。
暦の上では立春となって春が来たと言われても、太陽高度はまだまだ低く陽射しは冬至の頃と変わらないので、まだまだ寒いのです。
「暑さ寒さも彼岸まで」と言われる、春分・秋分になると南中高度は71.3度となり陽射しが強くも弱くもなくなって、ちょうど良いぐらいになるので過去60年間の平均気温を見ると15度ぐらいになります。
立夏の南中高度を見ると5月なのに夏至とほとんど変わらない高度になり、陽射しが強く、皆さまの嫌いな紫外線の量も一年で一番太陽高度の高い夏至とほとんど変わらないのですね。ですので春分を過ぎると紫外線対策をした方が良さそうですね。

春の気は「生」
中医学では、春夏秋冬の季節の変化に合わせて、自然界の気はそれぞれ生・長・収・蔵と変化すると考えます。春の気は「生」で、新しい生命が生まれるように動物たちは冬眠から目覚め植物は地中で過ごしてきた種が太陽を求めて地面から顔を出し始めるころです。
陰気は中央に向けて凝集するように働くので秋冬には植物も実が稔り種になって地中に貯蔵され春を待ち、そして春になって陽気が旺盛になってくると陽気は外に向かって発散するように働くので地面から新しい芽が芽吹き花が開き伸び伸びと生長していきます。
万物はこの自然界の気の変化に合わせて活動するので、私たち人間もこの気の変化に合わせて活動することが健やかに生きる養生法なのです。
秋冬は収・蔵する気に合わせて活発に活動して気を消耗したり浪費したりしないようにひっそりと過ごすことが養生法となりますが、春夏になるといつまでも内に閉じこもっていないで少しずつ外に向かって発散するように活動的に過ごすことが養生法になります。
とは言っても、まだまだ春が始まったばかりなので、いきなりトップスピードで走り回るのは無謀です。少しずつ自然界の気の変化に調和させながら自分のカラダの気も変えていくことが大切です。
冬は陰気が旺盛で、一方夏は陽気が旺盛で寒すぎたり暑すぎたりしますが、それなりに防寒対策や暑さ対策などをすることが出来ますが、春と秋は陰から陽へ、また陽から陰への大きな気の変化する時節なので暑さ寒さも変動が激しく気候も非常に不安定になります。自然界のこの激しい変化に心身もなかなか対応しきれず、同じように不安定な状態になりやすい季節です。
陰から陽への変化に対応できなくなるとカラダの陰陽も失調し、陰陽のバランスが乱れてさまざまな症状が現れやすくなります。
春の養生法
春三月…此謂発陳。天地倶生、万物以栄。夜臥早起、広歩於庭、被髮緩形、以使志生。生而勿殺、予而勿奪、賞而勿罰。此春気之応、養生之道也。逆之則傷肝、夏為寒変、奉長者少。
(黄帝内経素問・四気調神大論)
春三月(立春から立夏の前日までの三ヶ月間)は、これを「発陳」という。天地のすべてのものが生まれ栄える。夜は寝て朝早く起きて、庭をゆったり歩く。髪や服はゆったりして、志(目標)に心を向ける。生まれても殺さず、与えても奪わず、罰せずに誉める。これが春の気に応じた養生の道である。これに逆らえば「肝」を傷め、陽気が沈んだままになって夏に冷えの病になる。…と黄帝内経 四気調神大論に書かれています。
春は「陽」の気がどんどん多くなり、冬眠していた万物は活動を開始し、新しい芽が出て命が生まれる季節です。春の主気は「風」で、東から暖かい風が吹き山々を青く変えていきます。五行では「木」に属し気質は「曲直」と言って曲がりくねりながらも、根は地中を縦横無尽に広がり栄養を吸収し、幹は天に向かい、枝葉は横に横に伸び広がる特徴があります。

五臓では「肝」が木に配されますが、肝ものびのびと全身に気血を巡らせる働き(疏泄作用)があり、ストレスや怒りで寒の働きを低下させないようにすることが大切で、春の養生法は『疏肝理気』になります。
肝の主な働きは「肝主疏泄」と「肝蔵血」ですが、情緒をコントロールしたり自律神経を調える作用もあり、肝が傷むと情緒不安定や自律神経失調症などの症状が起こります。
春は職場や学校など環境が変わる季節でストレスも多くなり五月病や登校拒否、うつ病なども起こりやすいです。
うつ病は中医学では「肝鬱」と言い、精神疾患というより肝機能の低下と考えます。意外とストレス源は家族や職場など身近なところが多く排除しにくいので、出来るだけストレス源とまともにぶつからず、ストレスを溜めないよう、自分なりの上手な発散法を見つけましょう。

もう一つの春の養生テーマは『養陽防風 』です。春はよく風が吹くので「風邪(ふうじゃ)」による病気が起こりやすくなります。
風邪は百病の長と言われ、また素問 風論編には「風なる者は善く行りて数変ず」とあり風邪による病気や症状は多種多様だと書かれています。
風邪が侵襲して悪寒、発熱、咳、鼻詰まりを「傷風」と言い、湿と結合して「風湿」、熱と結合して「風熱」、乾燥と結合して「風燥」、寒と結合して「風寒」となるように他の邪気と結合しやすく、また病気の進行が速く変化しやすいのが特徴で全身あちこちに症状が出やすくなります。
出来るだけ早く対処し邪気を追い出すことが大切です。 アレルギー、蕁麻疹、感冒のほか、驚風や中風(脳卒中)も風病になります。
風と名のつくツボが4つあります。風門という門(入り口)から風邪はカラダの中に入って来て、風府を通って風池に溜まります。風市は風邪が集まるイメージです。これらのツボが凝ったり緊張して固くなると邪気が詰まり気血の巡りが悪くなります。ストレッチやマッサージで緊張をほぐし柔軟にして気血の巡りを良くすることで免疫力が高まります。

自然に調和して過ごしましょう
宇宙の摂理とか宇宙の原理原則に沿って暮らすことが健康の秘訣というのが中医学で考える養生法です。
難しく考えるのではなく、小学校の教科書にも載ってる程度のことで十分オッケー! 太陽は毎日朝になると東から登って夕方になると西に沈み、太陽が沈んだら月が入れ替わるように夜空をめぐり、その月もまた満月から少しずつ欠けて三日月になり今度は逆に満月に向かって大きくなり、そして日本には四季があり春夏秋冬と毎日雨の日や晴れの日などいろいろなお天気の日がありながら、少しずつ気候が変わっていくけど春⇒夏⇒秋⇒冬の順番は毎年変わることなく巡っている、ということが宇宙の摂理で原理原則です。
動物も植物もこの原理原則で生きており、私たち人間も自然界の一員として生活(生命活動)を営んでおり、ココロも含めたカラダすべてが自然界の気候の変化から様々な影響を受けながら生活しています。
春三月は、春の気に調和して暮らすことが、元気に健やかに過ごす秘訣だということですね。2000年以上前に書かれた「黄帝内経 四気調神大論」に従って暮らしてみましょうか。夏になっても夏バテしないで元気に過ごせるかも知れませんね。
京都伝統中医学研究所の"立春におすすめの薬膳茶&薬膳食材"
1.「滋陰養血」の薬膳茶&食材
■陰を補い血を養うオススメの薬膳茶&薬膳食材は、
薬膳茶では、「なつめ薬膳茶」、「カラダ潤しちゃ」、「健やか茶」、「増血美肌茶」など
薬膳食材では、「新彊なつめ」、「金針菜」、「竜眼」、「枸杞の実」、「松の実」、「マイカイ花」、「桂花」、「茉莉花」など
薬膳鍋セット「四物鍋スープ」、「手足冰凍改善鍋」、「冬の美肌薬膳鍋」は、薬膳食材もセットになってオススメ。
■肝を過剰を調えるオススメの薬膳茶&薬膳食材は、
薬膳茶では、「理気明目茶」、「なつめ薬膳茶」、「なつめ竜眼茶」、「からだを温める黒のお茶」など
薬膳食材では、「黒きくらげ」、「新彊なつめ」、「枸杞の実」、「竜眼」、「金針菜」、「紅花」、「マイカイ花」など
2.感冒におすすめの薬膳茶&薬膳食材
辛温解表…からだを温めて邪気を追い出す
「薬膳火鍋」、「手足冰凍鍋」、「からだを温める黒のお茶」、「なつめと生姜のチャイ」、「黒薔薇茶」、「紅花」、「竜眼」、「マイカイ花」、「桂花」など
辛涼解表…余分な熱を冷まして邪気を追い出す
「理気明目茶」、「五望茶」、「理気明目茶」、「菊花」、「百合」など
どちらのカゼにもおすすめなのが、やはり「なつめ薬膳茶」です。弱った胃腸を調え、気血を補い、疲れた体を癒してくれます。
3.漢方入浴剤
ヨモギがたっぷり入った「ほっこりポカポカあたため乃湯」もこの季節の養生にオススメ。ヨモギの香りが浴室中に広がり漢方の香りで癒され、ヨモギの成分が染み出たお湯にしっかり浸かってココロもカラダも温まりましょう。
中医学や漢方の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。
薬膳茶や薬膳食材などの商品は各ショップでお買い求めいただけます。
薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 https://www.kyotorakurakudo.com
京都伝統中医学研究所 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/iktcm/
京都伝統中医学研究所 ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/iktcm/
中医学や漢方の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。
次回は、2月19日「雨水」ですね。空から降ってくるものが雪から雨に変わる頃。少し寒さが緩んでくる頃ですね。
まだまだ寒い日もありますから、春捂と冬の養生もしてお過ごしくださいね♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
