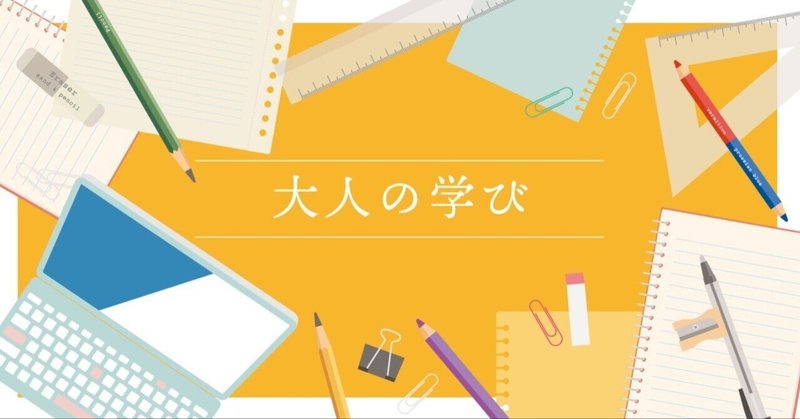
教育における「カリキュラム」とは、教育目的によって変わるもの
大学院で「カリキュラム」について学んでいます。
先日は、皆さんにカリキュラムの「定義」について聞きましたが、調べてみると、その定義は全く一定ではないのです。
実にさまざまな解釈があることを学びました。
私は長年「学校で教えるべきことのリスト」であると考えていました。
が、それは随分と古い考え方のようです。
本日は大学院で学んだLearner-Centered Initiatives (LCI)のLalorの書籍から紹介します。
日本で私たちが考える「カリキュラム」とは、「学習すべきことのリスト」ではないでしょうか。
よく、日本の学校の先生たちと話していると「カリキュラムを消化するのが大変だ」と言われます。これは「伝統的なカリキュラム」と言われるようです。
また、伝統的なカリキュラムの中には、生徒が "知っていなければならない "詳細な事実やその他の情報の長いリストが含まれていることもあります。このようなカリキュラムで は、教師が中心となって、年度末までに教えるべきことをすべて「網羅」しようと情報を提供する教室になることが多い 。
まさにこれですね。
目的によって変わるカリキュラム
では他にどんなものがあるのか。
Lalorは「目的としてのカリキュラム」について言及しています。
カリキュラムは、目的によって変わるというのです。
例えば、こんな感じに。
これまで数百件を超えるサポート、ありがとうございました。今は500円のマガジンの定期購読者が750人を超えました。お気持ちだけで嬉しいです。文章を読んで元気になっていただければ。
