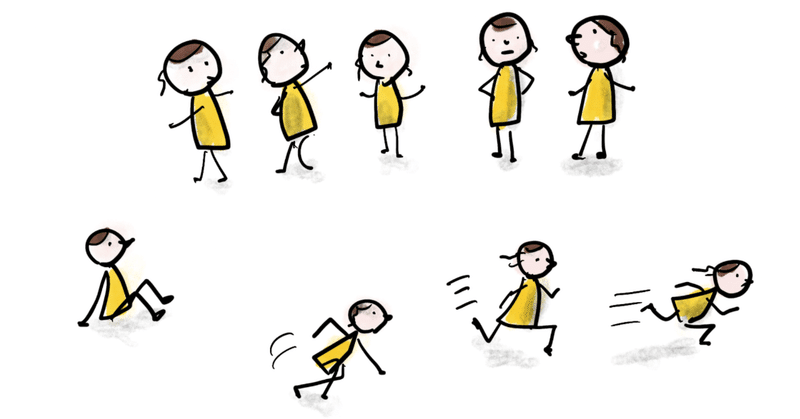
生徒数日本一。さらに10万人をめざす「N高」と海外インターナショナル・スクールの意外な共通点
日本にも教育の多様性が出てきました。
マレーシアで、N高の元広報のまりあさんに取材できました。
なぜN高が支持されるのか?
N高は「ネットの高校」として2016年に沖縄県に誕生。運営は学校法人角川ドワンゴ学園。
通信制の学校ですが、通学も可能です。さらに本校を茨城県つくば市におく「S高」も誕生しました。
2万3000人以上の生徒を集めており、現在も拡大中。
キャンパスは、沖縄県うるま市のほか、札幌・仙台・新潟・金沢・つくば・水戸・取手・高崎・宇都宮・代々木・御茶ノ水・池袋・立川・渋谷・秋葉原・町田・武蔵境・横浜・横浜金港・平塚・大宮・川越・千葉・柏・浜松・静岡・岐阜・四日市・名古屋・名駅・東岡崎・姫路・天王寺・心斎橋・梅田・京都・神戸・岡山・広島・高松・福岡・北九州・鹿児島にあるそうです。
授業やレポート提出はインターネットを通じて行われるが、通学コースも存在している。また、課外授業として、日本各地の自治体と連携した職業体験や、学校行事として、ドワンゴが主催するリアルイベントであるニコニコ超会議、ニコニコ町会議、ニコニコ超パーティと連携したN高文化祭など催しを実施している。
元広報のまりあさんは将来的に「10万人を目指している」と教えてくれました。
いつの間に、こんなことになっているのでしょうか?
急拡大の理由「N高は時代のニーズに合っていた」
まりあさんは、N高が「時代のニーズに合っていた」と言います。
「提供するコンテンツが時代に合っているということではないでしょうか。また、地方に住む人でも、平等に教育を受けられます」
一方で、最近では通学を選ぶ学生さんが増えているそうです。
基礎的な学業はオンラインで、各自が収録された授業を見るスタイル。
N高のキャンパスではプロジェクトや企業とのコラボレーション、職業体験プログラムや商品開発の機会など、プロジェクトの機会が頻繁にあります。「体験学習」ができるのです。
大学進学を目指す学生にはサポートもあります。
「N高には先生という言葉はありません」とまりあさん。「先生」とは呼ばず「メンター」で、最初から上下の関係ではないのです。ここも先生をファシリテーターとする先進的な学校に近いです。
メンターが、勉強をどうプランするかの相談に乗ってくれます。別途費用で大学進学に向けて伴走型のコーチを頼むことも可能です。
なぜ入学試験がないのか?
面白いなと思ったのは、入学時期が年に4回あることです。
入試はなく、基礎学力を見るだけで「基本的には誰でもウェルカム」。「入試というよりはマッチング」なので、受験勉強はしなくても入れます。
この辺りは、インテイクが複数あったり、空きさえあれば、大体いつからでも入れるインクルーシブな、インターナショナル・スクールと非常に似ていると感じました(インターの場合、入れなくても、何を強化するかを教えてくれ、数ヶ月後に受け直しできるケースもあります)。
奥平博一校長はインタビューでこう言っています。
N高は入学試験がないよね。それは、いろんな人がいてこそいいよって、いろんな人が世の中にいるんだっていうことを、大学時代や働く中で、身をもって感じてきたからなんです。
そのため、中途入学も盛んです。
中には、有名高校に一旦入学して「何かが違う」と違和感を感じて入ってくる方もいます。規律性障害があるとか、いわゆる日本の学校教育で拾いきれないケースに対応できています
と、まりあさん。
一方で、N中は一条校としての認定が降りていないので、所属中学校と連携する形で卒業します。
進路はどうなるのか?
進学先も多様です。2022年度の卒業生は7000人。うち30パーセントが大学進学しました。日本の学校への推薦もあります。プログラミングができる学生が企業から勧誘されるケースもあります。
「特筆すべきことでは、海外大の進学が伸びていることです。留学サポートをする課があり、マレーシアにも早くから注目し、マレーシア大学ツアーをしたり、エッセイのサポートをしたりします。課外活動が盛んで、自分のやりたいことを極める人が多く、海外大との相性が良いと思います。周りがいろんなことをしているので、刺激を受けるのではないでしょうか」
(まりあさん)
確かに海外大は学校名よりも成績ややったことを重視するので、相性は良さそうです。
校長先生はこう言います。
先生たちにも話をしているんですけど「枠」にはめるっていうのは大人からしたら楽なことなんですよね。でも、自分の人生しか知らないだけでいろんな人生があるわけじゃないですか。だからできるだけ否定しない、否定できる根拠がないですから。生徒のみなさんが言うことは否定せずに可能性を探ってもらうっていうのが根底にあります。
「N高にいると、入学時期も頻繁にあり、キャンパスからネットに、週1から週3通学に変更する方もいるので、何がマジョリティかわからないです」とまりあさんも口を揃える。
これもとてもマレーシアの(インクルーシブ教育をやっている)インターナショナル・スクールに近いですが、さらに自由度が高いです。
まりあさんが在校生にインタビューしてみると、親主導より、本人が調べて「ここに行きたい」と保護者に言ってくることが多いようです。まさに「子どもが教育を選んで」いるわけですね。
流石にここまで自由な教育は、海外でもあまり聞いたことがないのです。
逆に、このメソッドを海外に輸出したら、アニメ好き、ゲーム好きで日本に憧れている東南アジアの高校生が集まって、グローバルなごちゃ混ぜになるんでは、と思ったりしました。
それではまた。
ここから先は
これまで数百件を超えるサポート、ありがとうございました。今は500円のマガジンの定期購読者が750人を超えました。お気持ちだけで嬉しいです。文章を読んで元気になっていただければ。

