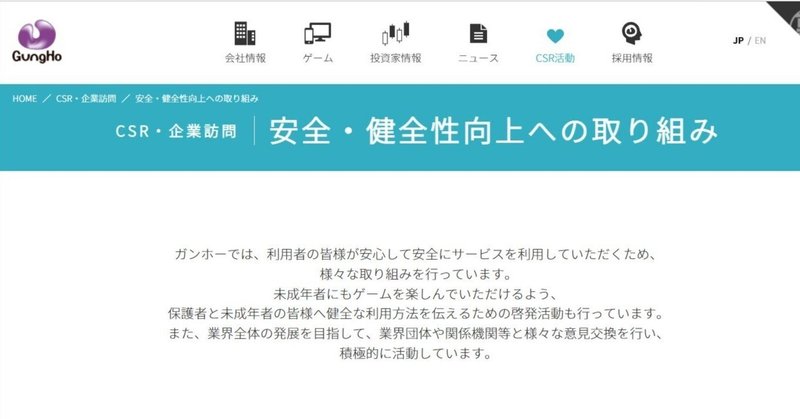
子どものオンラインゲーム高額課金を防ぐには / ガンホー
昨年度後半に実施していた消費生活相談員向けの研修でまだ紹介しきれていなかったものが残っていましたので、ここでご紹介します。
令和4年12月に開催された苦情処理研究会では、ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株)様より、「オンラインゲームの安心・安全対策講座」と題して、子どものオンラインゲーム課金に関して、その背景となる基礎知識、相談時の対応や再発防止策、同社での取組などについてWeb遠隔にてご講演いただきました。

近年のオンラインゲームは、基本料金は無料ですが、アイテム等を入手するのは有料(課金)という形態がほとんどとなっています。無料のままでも遊ぶことは可能ですが、より早く効率的に強くなりたい、かっこいいスキンなどを手に入れたいといった場合には、課金が必要となってきます。
しかし、そのことを親に言いづらい、あるいは電子決済なので自分ではできないために、親に内緒で課金してしまう(同社では「ナイショ課金」と表現されています)という事例が多数発生しています。
同社の情報によれば、12歳から15歳ぐらいまでの中学生前後の年齢がもっとも件数が多いそうです。年齢別での「ナイショ課金」に至った理由は、小学校低学年まではそもそも課金なのかどうかもよくわからないままに結果として課金になってしまったケースの割合が多いのですが、小学校高学年から中学生、高校生と年齢が上がるほど、強くなりたいから、課金と知っていながら行った、という割合が多くなります。
一方で、保護者の側も、子どもにお古のスマホ等を渡す際に、アカウントやクレジットカード情報の紐づけ解除などの設定が不十分であったために、カードや暗証番号がなくてもクリックするだけで課金ができてしまう状態であったという事例がよく聞かれます。
しかし、いくらセキュリティ等を強固にしても、子どもの側がそれらを乗り越えて課金してしまうケースもあります。単に物理的に課金できない設定とするだけではなく、親子間でよく話し合って予めルールを決めておく、子どもも納得した上でルールを守った利用とすることが、高額課金トラブル防止には重要であるということを学びました。
ガンホー様でも、同社のゲーム利用にあたっては保護者に課金の許可を得ているかを確認し、課金額に上限を設定することも可能であったり、「お約束メイカー」という、親子でスマホゲームに関する約束を作れるサイトを提供するなど、ゲームの安心・安全対策について様々な取組をされていることを伺いました。
なお、お小遣いとしての額をはるかに上回るような高額の契約を保護者の承諾なく子どもが勝手に締結してしまった場合、保護者が未成年者取消権を行使することができると民法に定められています。
スマホのオンラインゲームの場合、そのほとんどがプラットフォーム事業者経由で課金が行われていますので、まずは課金を行ったアカウントからプラットフォーム事業者に問い合わせ、未成年者による課金だったということを申し出ましょう。難しそうな場合は、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。ただし、オンラインゲームでは未成年者が契約したものと証明することが難しく、必ずしも取消できるとは限らないので、ご了承ください。
