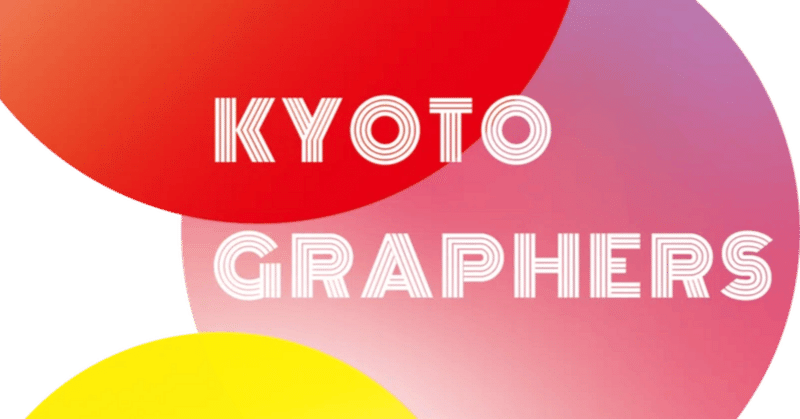
川内倫子『as it is』『Cui Cui』を語る会|写真を「みる」楽しさと「語る」意義
はじめに
みなさんこんにちは!コミュ部のこじもえです。
KYOTOGRAPHIEの会期も終了し、まだまだ余韻が残っているところでしょうか。
今回は5/8に行われた「川内倫子『as it is』『Cui Cui』を語る会」の様子をお届けしていこうと思います。
川内倫子さんの『as it is』『Cui Cui』といえば、2024年度のKYOTOGRAPHIEのプログラムとして、京セラ美術館で展示が行われていた作品です。
このイベントは、川内さんの展示もしくは写真集をみてきたスタッフのなかで感想を語り合おうという趣旨で開催されました。
最終的には、写真を「みる」ことの楽しみ方と写真を「語る」ことの意義について深く考えることのできた大変有意義な会となりました。
川内さんの写真を「みて」
まずは、川内さんの写真をみての感想をそれぞれで出し合ってみました。
たくさんの解釈や感想が出てきましたが、ここでは何人かの意見を抜粋してお届けします。
ふわふわした、エモーショナルな雰囲気のなかにある生々しさ
ひとりめ:生きることと死ぬことの生々しさを覆い隠してしまわないところに感銘を受けた。全体的に浮遊感のある川内さんの作品だけれど、そのなかには生と隣接した死、死があるからこそ煌めく生が描かれていると捉えている。
みんな見たことがあるけれど、どこか懐かしくて、忘れかけてた記憶にツンとする感じ
ふたりめ:川内さんの写真には少しだけ自分がいる。どこかで見たことのある風景だけれどもなにかが異なり、その差異にこそ自分を重ねてみるための余白がある。
一般的には死に対して恐れを抱くけれど、川内さんの写真は死をフラットに捉えているように感じる
さんにんめ:わたしも祖母の写真を帰省ごとに撮影している。悲哀ゆえに写真として残すのではなく、感情は後からついてくるものであり、死から逃れることはできない。だからこそ、いまこのときを残すことに意味がある。川内さんの作品にしても「死が怖い」という次元とは別のところで写真を撮影しているのだろうと展示空間を見ながら思っている。
ホームビデオみたいなのに、いやらしさがない表現
よにんめ:映像展示について、お子さんが成長していく姿を映していても、我(Ego)がでておらず、見る人がみんなが普遍的に「きれい」だと思えるところにプロとしての技術と川内さん自身の心の綺麗さを感じる。
写真を「感じる」から「語る」へ
ここからはこの会の主催の一人でもあるAkihisaさん、コミュ部のJunkoさん、あじおか、こじもえの座談形式でお届けしていきます。
感覚を言語化する意義とは?
あじおか:写真を学び、どんな写真が『良い写真』なのか言語化できるようになったことで、良い写真を見てㇵッとなる感覚がなくなった。ただ単純に感覚で『あ、いいなぁ』って思うことの方がよっぽど尊いのではないか。
こじもえ:でも、多くの写真やさまざまな解釈を取り込むことでしか、良い写真に衝撃を受けるための感受性は育まれないのでは。
Junko:その感覚もすごくわかる。
こじもえ:学ぶことによって、その驚きが失われてしまうっていうのは、私も何回か経験してることなのでわかる。
でも良い写真を見てハッとするだけで終わらせてしまうことが一番もったいない。その感覚を言語化してまた新しくハッとする感覚を得ていくという無限のプロセスが、写真を読むことの楽しみなのではないか。
Junko:キャプションを読んでから写真をみるか、写真をみてからキャプションを読むかという話にもつながってくる。キャプションがなかったら、『うちにも似たような家族写真があるわ』程度の解釈で終わってるかもしれない。でも、理由や意図を知ってからもう一度作品を見てみると理解が深まることもある。おそらく、ハッとなっただけで終わってしまう人に対して、テキストがあるのだと思う。
Akihisa:これは決まった価値基準の話ではないけれど、『エモい』といった感覚的なものを客観視することも鑑賞の一つのあり方だと思う。たとえば、このスイカの写真にもこのように映らなかった写真、写真集には選ばれなかった写真が存在している。じゃあ、この写真から感じられるものだけで、このスイカのことを判断していいのかどうかを考えてみると面白い。
Akihisa:写真に映っているものから得られる感覚が、本当に現実に備わっていたもの由来なのか、あるいは何かしらの技術によって作為的に作り出されたものなのかを考えていくことは、鑑賞を深める方法の一つになるのではないか。
その中で言葉にする必要があるのかないのかという問題はある。必ずしも言葉にしなくていいけれど、その感動を覚えていたり共有したりするためには言葉が絶対に必要。『すごい』とか『やばい』みたいなことは言えても、言葉が無くてはそこから更に解像度を上げて作品を語っていくことはできない。
あじおか:言語化できる人が集まって、いっぱい勉強して作った作品は作家と知識のある人にしかわからない展示になってしまうのではないか。初心者の人や写真を撮っていない人にはわからない自己満足になる可能性もある。逆に、コンセプトや写真家の意図をステートメントで示しすぎてしまうと、初心者には間口が広いが、解釈にも余白が無くなり、写真から考えるということをしなくなってしまう。
Akihisa:それでもKYOTOGRAPHIEのようなフェスティバルはいい取り組みだと思う。やはりインパクトがあって面白いものが見れるというわかりやすさがある。でも、それはあくまでも入口としてであって、そこから「鑑賞する」ということを考えていく機会があれば、さらに解釈を深めていける。もし解釈しきれない部分があるのであればそれを内発的に見つけていくこともできる。
おわりに
会の終わりにAkihisaさんがこのように語ってくださいました。
「こういう会をしたのは単純に楽しいから。参加してくれた人の話を聞いて『最初に思ってたことと何か違う』とか、話を聞いてから写真をみて『あれ、なんか違うな』ということが起きてほしい」
「改めて時間をかけてみた後は、何も考えずにみていた時とまた感じ方が変わることもある。それはどちらが正しいかということではなく、その変化を含めて鑑賞だというふうに思っている。鑑賞することによって何か日常に変化が起きればいい。別にそうでなくても、今日のようにみんなで集まって写真について話し合うことが『楽しい』と思えることがまずは第一歩」
写真は撮るだけでなく、写真に対して感じたことを言語化していくことや見返すことによって、さらに深みを増していきます。
KYOTOGRAPHIE2024の会期は終わってしまいましたが、カタログや写真集をお持ちの方はぜひもう一度見返してみてください。
あの時、会場で「みた」ときとは違う感じ方をするかもしれません。
そして、感じ方の変化を言葉にして周りの人に「語る」ことは新しい発見につながるかと思います。
KYOTOGRAPHIE 公式サイト
コミュ部 instagram ←インスタのフォローもお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
