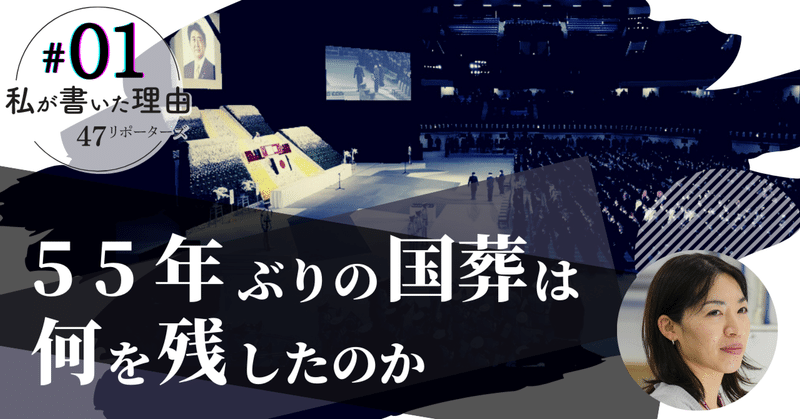
歴史にみる国葬の危うさ、国民の分断を招きながら突き進む政府への違和感
みなさんは9月27日の午後2時過ぎ、何をしていましたか?
私は大阪で安倍晋三元首相の国葬のテレビ中継を見ていました。
直前の報道各社の世論調査では賛否が分かれ、当日も会場となった日本武道館の外では数千人が献花に並ぶ一方、国葬に反対する人たちはデモをしていました。


そんな中でも葬儀自体は厳かに進み、菅義偉元首相が友人代表として感動的な弔辞を読み上げ、メディアはこぞってその内容を取り上げました。
岸田文雄首相が後に語ったように「やって良かった」と思う人も大勢いると思います。
それでも、私の中では大きな塊を無理に飲み込んだような違和感が残っています。
■ 自己紹介
はじめまして。大阪社会部の記者の井上詞子です。
安倍元首相の銃撃事件が起きた7月以降、共同通信はさまざまな記事を書いてきました。
私も同僚記者とともに「国葬」の記事を書きました。史料や専門家の話から、その歴史を振り返り、過去の事例や当時の政府の思惑などを解説しています。
今回はこの記事を書くに至った経緯や、私が取材を通して感じたことを振り返りたいと思います。
■ 最初は遠く感じた
政府が安倍元首相の国葬を検討しているという話は、事件後まもなく浮上しました。
その直後から「法的根拠がない」などと指摘する声が野党議員から上がっていましたが、共同通信の奈良支局や大阪社会部の記者たちは事件や容疑者の取材に追われていて、まだ永田町での議論にとどまっていた国葬は急いで取りかかるようなテーマではありませんでした。
私も当初は実感がわかず、それほど深く考えていませんでした。
事件直後に大阪社会部の記者がまとめた記事はコチラ↓
国葬について取材することが決まったのは事件から1週間後の7月15日の夜。
この事件について、デジタル向けの記事のラインナップを話し合う中でテーマの一つに上がり、私と同僚の水谷茜記者が取材に当たることになりました。
でも、この時はまだ世論を二分するような状況ではありませんでした。
■ 明らかになる課題
「戦前は国葬令という法令があったが、戦後に失効(法律の効力がなくなること)しているらしい」
「岸田政権は『内閣府設置法』に基づいて敢行しようとしているが、野党が反発しているようだ」
取材前の私の認識はその程度で、国葬がこのまま実施されるのは何か引っかかるけど明確には説明できない、そんな状態でした。
ただ取材を進める中で、今回の国葬がはらむ危うさを感じるようになってきました。
国や天皇に尽くした人物を盛大に弔う戦前・戦時中の国葬は、政府が国民をまとめ上げるために利用された側面がありました。
上に書いたように、国葬について定めた「国葬令」は戦後、失効しています。1967年には明確な法的根拠がない中で、吉田茂元首相の国葬が営まれましたが、その後は内閣と自民党が主催する「内閣・自民党合同葬」が主流となっていきました。
ところが、ここにきて岸田首相が国葬を復活させるというのです。
それも、国民の代表機関である国会で議論することなく、内閣が政策方針などを決定する時に使う「閣議決定」という手続きで決めてしまいました。
取材でお話を伺った中央大文学部の宮間純一教授は「国葬は戦前・戦中期に危険な装置として働いた」と指摘し、「この制度を曖昧な状態で生かしておくのは非常に危険だ」と警鐘を鳴らしていました。

安倍晋三元首相が国葬にふさわしいかどうかではなく、もっと根本的な問題として、その時の内閣が独断で実施できる制度で良いのか。これを機に国葬の基準や決定プロセスを明確にしておくべきではないのか…。
記事を書き始める頃には「読んだ人が考えるきっかけになるような内容にしたい」と考えていました。
■ 国葬が残したもの
自民党と世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の接点が次々と明らかになるにつれ、国葬にも厳しい目が向けられるようになりました。
政治と宗教の問題が取り上げられなければ、国葬もこれほど注目されず、反対の声も高まることはなかったかもしれません。
政府は予定通り国葬を実施しましたが、吉田元首相の時とは異なり、国民に黙祷のような形で「弔意」を表明することは求めないなど、反対意見に配慮した姿勢を示しました。
ただ、それによって(国ではなく内閣が主催者である)「内閣葬」にせず、「国葬」とした意味が一層不明確になったように思います。
そこまでして岸田首相がこだわった国葬とは結局何だったのでしょうか。
国民の分断も深まったように感じました。SNSでは、政府の対応について議論するのではなく、自分と意見の異なる立場の人をお互いに攻撃するようなやり取りも見られました。
戦前・戦時中に政治利用された国葬が現代によみがえったことの意味を考える時、「聞く力」を標榜した岸田政権が垣間見せた強引さを含め、どこか不気味なものを残した気がしてなりません。
井上記者と水谷記者がまとめた国葬に関する記事はコチラ↓

井上 詞子(いのうえ・のりこ) 1982年、米国生まれ。出版社を経て2008年入社。14年から本社生活報道部で社会保障や雇用・労働問題を取材。21年2月から大阪社会部。最近の関心は農業、直近のマイブームは草刈り。
<皆さんのご意見、ご感想を是非お聞かせ下さい>

