
Vol.12 Timeline/Mild High Club〈今のところnoteでまだ誰もレビューしていない名盤たち〉
Timeline(2015) Mild High Club
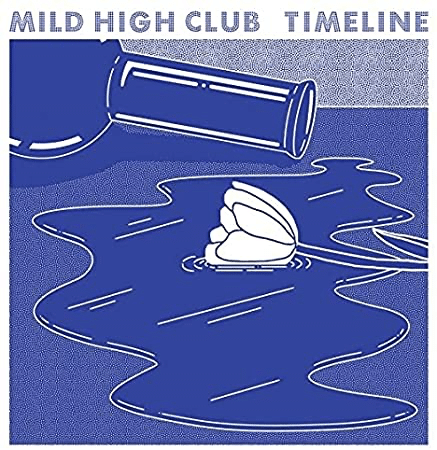
Mild High ClubはLAを拠点とするミュージシャンのAlexander Brettinが主催のプロジェクト。恐らくBrettinの仕事で1番知られているのはTyler,the Creatorとの共作だろう。また彼はStone Throw Recordsに籍を置き、その縁もあってか同じくStone Throw所属のSSWであるJerry PaperやBenny Singsとのコラボ歴もある。
今挙げたどのミュージシャンも「部屋」の匂いがするような緩いムードが漂っており、もしこの中に一つでも知っている名前があったなら、一斉に聞いてみてぜひハマってほしい。特にタイラーのファンなんかは(もちろん自分も含め)USヒップホップのメインストリームをすぐに聴き進めるよりも、周辺のベットルームポップシーン(それこそMild High Clubとか同じくコラボ相手のRex Orange Countyとか)を聞いて「タイラーのノリ」を掴みに行った方がスムースかつヘルシーにディグれるのでは?と思う。ヘルシーなディグが原理上存在するかどうかはひとまず置いておいて。
Mild High Clubが「Timeline」を発表した2015年前後において、「ベットルーム・サイケポップ」は確実に宅録インディーの一大ムーブメントだった。ここにおける「サイケ」とは60〜70年代のサイケデリック・ロックほどの定型があるわけではなく、広義のリラックス/酩酊状態に浸らせてくれる何かだった。そして何より、狭い部屋で1人耳を傾けることを志向しているポップスでもあった。その性質上インターネットでの人気が高く、このムーブメントの寵児であったMac DeMarcoやMen I Trustの代表曲の再生数には目を見張るものがある。恐らくUSにおけるサッドコアのように、この先も一定のファンベースを抱えながらゆったりと年輪を重ねていくのだろう。
「Timeline」の音は整然としていて、各楽器の音の仔細がクリアに聞こえる。これは従来のサイケデリック・ロックとは異なった方法論だ。ドロドロにひずませたファズギターとザラついたボーカル、そして半ば強引に音圧の増強を担うリズム隊。音が溶け出すことによってあらゆる壁ー現実と非現実、理性と本能、此岸と彼岸ーの境界を揺さぶることによって宙ぶらりんのまま、ゆらゆら漂わせる感覚をリスナーに喚起すること。それによる快楽の誘因こそがサイケデリック・ロックの担った役割だった。
「Timeline」はそのレースには参加していない。楽器は、楽器のままそこにある。チャンネル数も絞られているし(このレコーディングでは4トラックのMTRを使ったとか)、まるで無菌室で録られてるみたいだ。そして楽器の鳴りを整列させた上で、その列が崩れるスレスレのところで音が揺らいでいる。だから全体としては整然としていても、しっかりサイケデリックなフィーリングが損なわれていない。むしろ「整然としていて、トラックの包括的な統御が行われている様」が醸す「遠さ」と、「宅録と生楽器の織り成す豊かな音像」が感じさせる「近さ」という、コンポーザーとリスナーの距離間を溶解させることによってサイケデリックな気分が演出されているとさえ思ってしまう。
このアルバムの、とびきりノスタルジックでエモーショナルな部分にはオルガンの音色が顔を出す。言葉少なに恋の行く末を案じるM4「You and Me」では気だるいギターのアルペジオの裏でひたすらオルガンの、伸びきった短音が響き、歌が終わるのと同時にその詩の代弁を執るようにソロへと移行する。その音もやはり微かに震えていて、主人公が唇を震わせながら言葉をこぼしている様がありありと浮かぶようだ。
そのものM8「Elegy」(=哀歌)では、身も蓋もなく愛を告白する後ろで、よろよろとオルガンがコードにしがみついている。対照的に、この曲の中でピアノは悠然とオブリガード(メインのメロディーを補いながら、曲のアレンジ全体に寄与するもう一つのメロディー)を担っている。この二つの鍵盤、特に歌が終わると顕著だが、ピアノのスッキリ自立した旋律と後ろの牧歌的でフラフラと頼りのないオルガンの音は、やはり壁によって隔てられているとしか思えない。自立とフラフラ(≒依存)という二つの極があり、その二つの極が同時に同時に鳴らされている。その感覚、その心情の移り変わりを克服できないからこそ、身も蓋もない愛の告白に主人公は至ったのではないか。曲の最後、それまでさまよっていたオルガンの音のみが緩やかにピッチを駆け上がって次のM9「Wippig Willow」になだれ込んでトラックは終わる。最後に依存が選び取られる様、そのやるせなくも肯定されたような表情が、このアルバムのムードを何より象徴していと個人的に思った。
ちょっと感傷的になりすぎたけど、要はいつ聞いてもウットリできる良いアルバムです。ベットルーム・ポップのファンはもちろんだけど、個人的にはAORとかソフトロックとか、そっちの方面のファンにも聞いてもらいたい。そっちを通過した耳でも楽しめるというか、Todd RudgrenとかJames Taylorとかと並列させて聴くと意外に「良いSSW」として真っすぐ楽しめるかも。
最後にライブ映像。シンラインかっこいい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
