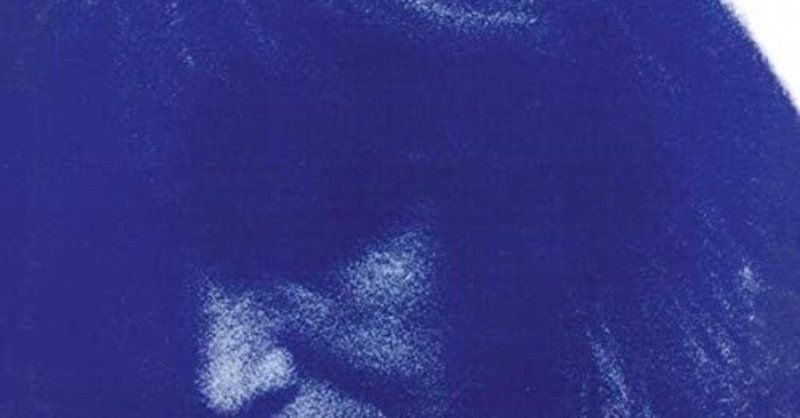
Vol.6 Doris Monteiro Agora/Doris Monteiro 〈今のところnoteでまだ誰もレビューしていない名盤たち〉
Agora (1977) Doris Monteiro

https://www.youtube.com/watch?v=Ico6HrbCHVc
Doris Monteiroはブラジルはリオ生まれのシンガーで、御年87歳の大ベテランだ。ボサノヴァがヒットチャートに上がる前の1950年代序盤から、既にシンガーとしてレコードを出している。そこからボサノヴァの誕生から、MPBの確立、進化と80年代に用意されているAORブームまでを演者として最中から観測していた。モンテイロはそれらにコミットしつつも、常に自らの解を用意していた。その一つがこの「Agora」である。
彼女のキャリア初期の数枚はオーセンティックな歌謡曲シンガーといった趣で、大仰なオーケストラをバックにモンテイロが朗々と歌唱しているものがほとんどだ。歌声にもいたいげでイノセンスな響きがまだ残っている。
転機になったのは1964年にリリースしたセルフタイトル作。ここではマルコスヴァーリやエウミールデオダードの曲を取り上げ、たおやかなエレピの音色が印象的に響く。音数をぐっと絞った構成で、モンテイロもそれに答えるようにしなやかで丸みのある表情を歌に忍び込ませている。これからMPB方面に舵を切ってゆくわけだが、その節々で彼女のニュアンスの巧さには感嘆させられるものがある。曲に合わせてアプローチを千変万化させられるのは、絶大なるシンガーの特権だ。
このアルバムを皮切りに、彼女のアーティスティックな一面が前景化してくる。そして少々ややこしくなる。というのも、彼女は64年作のものを含めて、8枚ものセルフタイトル・アルバムをリリースしている。何なら今回のテーマである「Agora 」もセルタイトルとしてカウントされている場合だってある。ややこしい、完全にあぶらだこ状態だ。しかし、ここはあえてそれを逆手にとり、セルフタイトル作のみに絞ってその足跡を追うことにする。彼女のセルフタイトル作はどれも内容がバラエティに富んでおり、キャリアを辿る手立てとして適しているからだ。モンテイロをまだ知らない人はセルフタイトルだけでも追っていれば、ひとまずはそのエッセンスを味わえるであろう。
64年作の次のセルフタイトルは70年。ここまでにモンテイロは三枚アルバムを出してはいるが、これらはどれも50年代のショービズ期を思わせるトラックが大胆に導入されている。しかし単なるリバイバルではなく、サンバの導入に合わせてビート感が明らかに増強している。音数も野暮ったくなるラインに漸近するようにぎりぎりの地点で統御されており、あるべきところにあるべき音が設置されている感覚に囚われる。そして70年作のセルフタイトル作はここ数年の集大成といった趣で、前セルフタイトル作(この呼び方は正しいのか?)の内容とその後の作品の折衷で、クールに仕上がったモンテイロのボーカルとオーケストラ、そしてサンバ由来の踊れるビートが集約した秀作に仕上がっている。
翌年である‘71年にもセルフタイトルをリリース。意図したものかは定かではないが、前年のものとジャケットの色彩が対になっている。しかし内容にそこまでの差異があるわけでもなく、前作のムードを踏襲している。しいて言うなら演奏がミニマムになり、バラード調の曲がグッと引き立っている。アグレッシブな前作と比べ、幾分かメランコリーな仕上がり。
そしてそのまた翌年の‘72年にもセルフタイトルをリリース。3年連続でセルフタイトルをリリースするなんて、ネット検索が主流の現代社会なら絶対御法度のプロモーションだろう。ただ、このストイックであっけらかんとした態度がより一層モンテイロのオブスキュアな一面を演出している、と勝手ながら感じている。
一聴して気になるのはストリングスの使い方。以前からバラード調の曲では多用されてはいたが、今作からアップテンポの曲でも使用され始めている。このストリングスが与える効果は大きく、切迫感と疾走感を曲全体にちりばめている。ポップで親しみやすい曲が多く、モンテイロ入門なら最も勧めやすいのかも。
次のセルフタイトルは2年後の‘74年になる。70~72年の3年間で彼女は3枚のセルフタイトルアルバムをリリースしてきたわけだが、実はこれと並行して同世代のサンバ界の雄であるミルチーニョとのデュオでアルバムを3作出している。こちらはソロ作とはガラッと変わり、アグレッシブなサンバの上でモンテイロが軽快に歌っている。これらの作品は先のセルフタイトル作群と交互にリリースされており、この3年間で彼女は「ミルチーニョとのサンバデュオ→メロウなセルフタイトル・アルバム」というサイクルを3度繰り返していることになる。これぞ正しくルーティンワークだ。
このサイクルはジャズ由来のメロウなサウンド+ショーロ・サンバ由来のアグレッシブなビートという土壌を整備した。意図して行ったのかは定かではないが、この試みは間違いなく彼女の作品としての強度を底上げした。そしてそれが結実する萌芽を見せたのがこの74年のセルフタイトルである。このアルバムの、特に前半部分は都会的なエレピと気味よく刻まれるパーカッション、クラシックギターの絡み合いが唯一無二のまろやかなグルーヴを生み出している。64年発のセルフタイトルと聞き比べると、彼女が遥かネクストレベルに達しているのが分かるであろう。ちなみに各種サブスク及びYoutubeでこのアルバムの一曲目は聞けない。厳密には聞くことはできるがあまりのノイズで曲の原型がズタズタに破かれており、聞くに堪えなくない。マスター版が痛んでいるのかデータの受け渡しが失敗しているのかは不明だが、とてもじゃないけど聞けない。大人しく盤を買って聴こう。
そしてここから3年の月日を経て彼女はカムバックする。完全に成熟した姿で、深いブルーを湛えながら。
恐らくこのアルバムのジャケットを見た大半の音楽マニアはジョニ・ミッチェルの「Blue」を想起するだろう。僕もそうだった。しかし、ここで描写されているのは人間の内面に潜むブルーというよりも、むしろ都会のネオンに当てられた青白い表情である。
M1冒頭の粘っこいエレキのカッティングを聴けば、このアルバムが前作までとは全く違ったムードを湛えているのは自明だ。軽快ながらも土のにおいが残った音色は、彼女が見いだした同世代のAORとMPBの折衷点であろう。
M4 で聞けるエレピの旋律と執拗に繰り返されるエレキのリフレイン、モンテイロの歌声に呼応するようになるトランペットの絡み合いは間違いなくこのアルバムのハイライトだろう。前作までの雰囲気だったらもう少しパーカッシブにアレンジしていたのかもしれないが、そこをグッと抑えて鳴るリムショットの音色が飛びぬけて心地が良い。この塩梅の良さがこのアルバムを名盤たらしめているのは疑いようがない。
洗練された音色と土着的なリズムが完璧に調和していることが、このアルバムの驚異的に素晴らしい点だと、個人的には思う。アレンジもミニマムに抑えられていて、いつ何時聞いてもしつこくない良さがある。だからこそ他人に勧めやすいし、万人に是非聞いてほしい。アルバムを通して一定の温度感で進行しているのも、繰り返し聞きたくなる気分を十二分に煽ってくれる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
