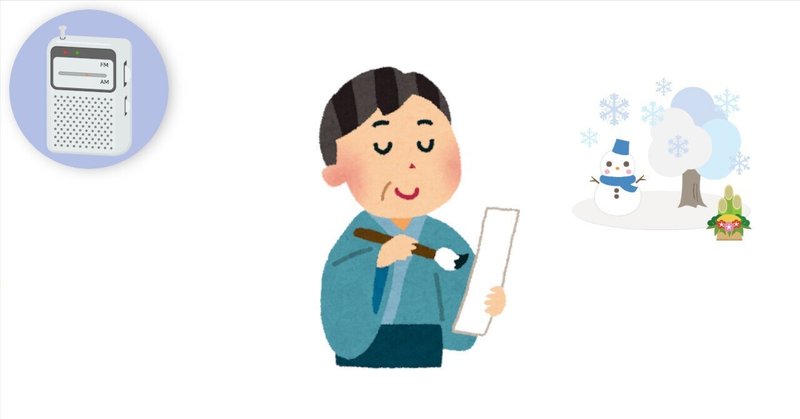
僅かな季節の移り変わりを見逃さずに詠み止めよう! 数学好きが学ぶ俳句の世界:冬・新年の句で締めくくり
数学好きの筆者が俳句の世界に足を踏み込んで、はや一年が経ちました。
こうしてみるとあっという間の一年でしたが、確実に俳句の腕前は上達したと感じています。
以前は句集を読んでも意味が分からなかったのですが、今では少しずつ理解できるようになってきました。
やはり、俳句を理解するためには、自分自身も句を詠んでみる必要があるんですね。
さて今回は、筆者の詠んだ冬・新年の句を解説してこのシリーズの締めくくりとしたいと思います。
読者の皆様が句作りの参考になれば幸いです。
刈られたる草の香の立ち初時雨
時雨とは冬の初めによく降る通り雨のことですが、特にこの冬初めての時雨を初時雨と呼びます。
この句は筆者が初時雨に遭ったときの体験を詠んでいます。
「そういえばこれがこの冬初めてだなあ」と感じながら時雨の空を眺めていると、ふと草の香りが漂ってきました。あたりを見回すと草がちょうど刈られたばかりだったのです。
「刈られたる」の「たる」は完了の助動詞「たり」の連体形で、この場合は草がすでに刈り取られてしまったことを表しています。
また、「立ち」と動詞の連用形で切れを作っていることにも注目しましょう。
草が刈られるのは普通の出来事ですが、初時雨の季語が付くことでその場の季節感と筆者の心情が呼び起され、イメージが膨らんでいくのが分かるはずです。
僅かな季節の移り変わりを見逃さずに詠み止めること
これこそが、俳句で一番重要なポイントなのです。
足もとをふくら雀に取られけり
雀は冬になると餌を求めて人間に接近してくるようになりますが、特に寒い日に羽の中に空気を入れて膨らんでいる雀のことをふくら雀と呼びます。
かわいらしい名前ですね。
この句も筆者自身の体験で、ふくら雀が足元に近づいて来たかと思えば、ちょこまかと動いて足のやり場に困った様子を描いています。
説明すると野暮になっちゃいますが、「あ~あ、足元をふくら雀に取られちゃった」と冗談めかして詠んでいるわけです。
さて、シリーズ最後の句は新年の句で締めくくりたいと思います。
壁紙の跡にぴたりと初暦
新年に使い始める新しい暦のことを初暦と呼びます。
このような新年の季語には新年らしさがイメージとして含まれるため、扱いに注意が必要です。
それと同時に、予定調和になりがちなお正月のイベントをいかに詠むか度量が試されることになります。
おそらく、皆さんも経験があると思いますが、壁掛けのカレンダーを使い続けると、壁紙がその箇所だけ色褪せずに跡になってしまいますよね。その状況を詠んだ句です。
見方によっては皮肉とも受け取られるでしょう。もちろん、どう解釈しようが読者次第ですが…
これは新年の句です!
新しい年への期待を込めて、前向きな句として捉えましょう。
以上で、このシリーズも完結です。
初心者が俳句を詠む際のポイントを、筆者自身の経験をもとにお伝えしてきました。
読者の皆さんにも、俳句を通じて感じた成長や学びが共感できれば幸いです。
ありがとうございました!
最後まで記事を読んでいただきありがとうございました!
