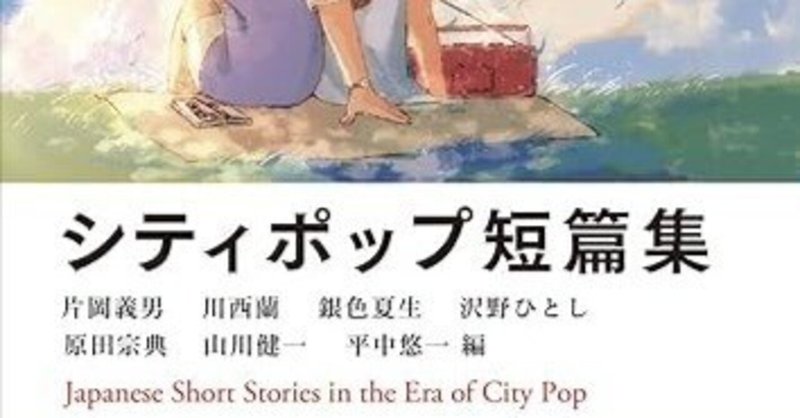
シティポップ短篇集とフィリピン
2024年4月10日、1980年代に日本で出版された短編小説を集めたアンソロジー「シティポップ短篇集」が発売されて、全国紙や大手出版系のサイトでもインタビューや書評が載ったりと話題になってる。
もちろん、今世界中で再評価されている80年代の日本のポップ音楽「シティポップ」というキーワードが表題に使われているからというのもあるんだろうけど、シティポップが生まれた80年代の日本の空気、シティポップのバックグラウンドを描いた小説が一冊にまとまったアンソロジーということでもとても興味深い本になっていると思う。
僕自身は80年代に高校〜大学生だった世代なので、若い人たちとは感じ方も違うと思うけれど、今回はシティポップ短編集の感想と、シティポップやそれが生まれた頃の日本の社会・空気とフィリピンとの接点を書いてみることにした。

収録作品
楽園の土曜日 - 片岡義男
秋の儀式 - 川西蘭
夏の午後 - 銀色夏生
マイ・シュガー・ベイブ - 川西蘭
プリズムをくれた少女 - 沢野ひとし
かぼちゃ、Come on! - 平中悠一
バスに乗って それで - 原田宗典
テーブルの上にパンはないけれど、愛がいっぱい - 山川健一
鎖骨の感触 - 片岡義男
ライナーノーツ - 平中悠一
あの頃憧れたちょっと大人の世界
収められた9作品には、明記されていないけれど、20代半ばから30代と思しき登場人物が描かれているものが多い。登場人物の振る舞いや言葉は、特に片岡義男さんの作品など、僕は学生の頃、素直にかっこいいな、と感じた。舞台設定や展開は「あるある、こういうの!」というノリではなく、なんとなく自分のことにリンクしているようないないような…そんな微妙な感覚を当時は覚えたものだった。
これは「ライナーノーツ」で平中氏がシティポップの歌詞についての部分で語っている「現実そのものではなく、現実をベースにしながらむしろ理想化されたイマジネーションの中のリアリティ(フィクション)が描き出されている」(p292)ということなのだろうか。
今の若者が読むとどんなふうに感じるのだろう。
川西蘭さんの「マイシュガーベイブ」と山川健一さんの「テーブルの上にパンはないけれど、愛がいっぱい」はラジオDJ、大手銀行員など、当時の花形職業(死語か?)の登場人物のプライベートが描かれている。どちらも魅力的なパートナーとの恋愛が描かれているけれど、実際に自分がそうなるか(なったか)どうかは別にして、当時はこういうのも自分の将来に起こりうる一つの可能性と思い込むことができた。
川西蘭さんのもう一つ、「秋の儀式」と銀色夏生さんの「夏の午後」、沢野ひとしさんの「プリズムをくれた少女」はどれもすごく短いお話だけれど、それぞれに読み応えのある作品だと思う。
大沢誉志幸の84年の大ヒット「そして僕は途方に暮れる」という曲が大好きだったので、僕には銀色夏生さんは作詞家としての印象が強かったけれど、文章もなかなか魅力的。
「プリズムをくれた少女」はこの作品だけ小学生が主人公のお話だけれど、なぜこの作品が収録されたのかは「ライナーノーツ」を参照されたし。その後でもう一回読むとなるほどーとなるはず。
一番印象に残ったのは川西蘭さんの「秋の儀式」。主人公がカフェでお茶を飲むのだけれどこういうのもとても80年代的だなと思う。路面店に洋書屋がある通りのカフェでお茶を飲む「僕」を自分に投影すれば、なんだか読んでいる僕までオシャレな人になったような気分になる(笑)。そして風変わりな儀式をする女の子に出会う。この女の子もとても魅力的だ。僕がこの女の子をとても魅力的だと思うということは、作者の術中にまんまとハマったということらしい(笑)←ここも「ライナーノーツ」を参照されたし。
かぼちゃ、Come on!
ところで、編者の平中悠一氏も80年代半ばに文壇デビューした「シティポップ世代」。シティポップ短篇集には自身の短編「かぼちゃ、come on!」も収められれている。この作品はハタチ過ぎの街の若者のとりとめのないドキドキ感、ワクワク感、オロオロ感がうまく描かれていて、あのころのいろんな思い出が、甘酸っぱくほろ苦く胸に蘇ってきた。
トータルアルバムに通じる
今はLPもCDもカセットも、過去のものとなっているけれど、80年代に「アルバム」を買って音楽を聴いていた僕には短編の収録順も印象的。よく、魅力的な楽曲をうまく並べられたアルバムを評して「トータルで聴ける…」などと言われるが、この本に収録された短編の並び順もまさにそんな感じで、実によく考えられている。
「解説」を「ライナーノーツ」としているのもフィジカルフォーマットで音楽を聴いていた世代にはニンマリするところ。
この辺も音楽に精通している編者ならではといったところだろう。
なんといってもライナーノーツが秀逸
80年代にシティポップも都会小説もオンタイムで経験した僕には収録作品はどれも懐かしかったけれど、なんといっても秀逸だったのは巻末に40ページを割いて書かれた「ライナーノーツ」だ。
文中で平中氏も書いているように、確かに90年代以降、80年代の音楽や小説は軽薄とされ、これまで正面から真面目に取り上げられることはなかったように思う。アイデア自体は80年代からあったそうだが、それなら今俺が。。。というところだろうか。
平中氏はどこかのSNSで、「だれもが頷く当たり前の感想を目新しいことばで語るより、まだだれも語っていない真実を当たり前のことばで語りたい」と言っていたが、長い間忘れられ、向き合われてこなかった80年代の文化を非常に深い洞察力で解き明かしつつ、それをだれにでも分かる「当たり前のことば」で語っている。
80年代の音楽や文学、その頃の社会も参照する形で冷静に現在を分析している点も興味深い。
音楽では山下達郎、大瀧詠一、ソバカスのある少女、DOWNTOWN…文学では、ライ麦畑でつかまえて、星の王子さま…など今の若い世代にも馴染みのあるわかりやすいキーワードをふんだんに用いながらこれまでなかった角度から分析をする平中氏。
だからこのライナーノーツは、読みやすい部分だけスッと読んでも十分楽しめるが、じっくり読んでも多様な発見がある。読む人を選ばないというか、読む人のレベルによって楽しめるというか。より深いところまで理解したいと思う人には文豪や哲学者、70〜90年代に起こった世界の事件まで多様なキーワードを用意してくれているのでそこから氏が書いたことを改めて読み直すことも可能だ。
そういう意味ではこの本はまさに「今」読むべき本なのかも。
フィリピンとの繋がり
装画
ところで、ピン中(フィリピン中毒)の僕としては最後にフィリピンとの関わりを書いておきたい。
まず、カバージャケット。
これは在米のイラストレーターDeisa Hidalgoが手がけている。ライナーノーツの最後でも紹介されている通り、平中氏がSpotifyで韓国のポップ音楽を聴く中で出会った楽曲のアートワークを描いていたのが彼女だったのだそう。
Deisaのファミリーネームをみたとき、僕はフィリピン人の苗字によくある名前だなと思いネット検索してみた。すると、Deisaは渡米前、フィリピンの名門私学の美術科に籍を置く学生で、フィリピンの若者向けのファッションブランドのコンセプトイメージやフィリピン映画のポスターなども描いていたことがわかった。
全くの偶然とはいえ、シティポップ短篇集にフィリピン人イラストレーターが関係していて、なんだか嬉しい気分になった(by ピン中)。
シティポップとフィリピン
世界的に注目されているシティポップだが、フィリピンでも大人気。好景気を背景に、アナログ盤を扱うレコードショップもフィリピンで増えてきたが、シティポップの復刻盤や中古盤も(フィリピンペソの貨幣価値から見れば)かなり高額でレコード棚に並ぶようになった。
そしてリスナーだけではなくシティポップを聴き込みインスパイアされた楽曲を発表する若いアーティストも出現するようになった。
ALYSONというマニラベースのインディペンデントバンドだが、彼らはシティポップに影響されたと公言していて、2023年にリリースされたシングルFeels So Goodではアートワークに「デフィネトリー・ラーブ!」と日本語(カタカナ)が入っており、曲のミックスは日本のスタジオで行ったとのこと。彼らのシティポップへの「入れ込みよう」がわかるようだ。
楽曲はAOR的なポップでウエルメイドな明るいミディアムナンバー。英語を解し、アメリカンポップスの影響も色濃いフィリピン人アーティストが「シティポップっぽい」楽曲を作るとこういう感じになるのか。
ソウルフルな女性ボーカルをゲストに迎え、男性ボーカルとの掛け合いもイイ感じ。
オススメの一曲。
もう一曲。昨年6月にリリースされ爆発的ヒットとなったRaining In Manila。
デ・ラ・サール大の附属高の学生バンドが母体のインディーズバンドLola Amourのオリジナル曲で、彼らは山下達郎が1982年にリリースしたアルバム「For You」に収録されているメガヒット「Sparkle」に大きくインスパイアされたと言っているが、彼らはシティポップのサウンド面だけでなく、当時の日本の社会や空気感にも注目し、それらと現在のフィリピンが置かれた状況を重ね合わせる形で楽曲に反映させているようだ。
シティポップについて書かれたものを検索する中で見つけた記事にこんなのがある
海外からのブームなので、どうしても歌詞の内容や楽曲の文化的背景は軽視されがちだが…(中略)…当時を知る世代と享楽的に音だけを楽しむ世代とのギャップが生まれるのは、仕方のないことかもしれない。しかし…(中略)…音から入った音楽ファンが、やがてその曲が何を歌っているか、どんな背景があるのかを紐解いていくようになれば理想だろう。
これは集英社オンライン上の記事で、アップされたのは2022年4月24日。
今でも世界的にはサンプリングやカバーレコーディング、復刻盤など「目に見える(耳に聴こえる)部分が注目されているが、いち早くその背景にまで思いを巡らせて自らの創作に活かしたフィリピン人アーティストは流石!と言いたいところだ(byピン中)。
ひょっとしたらフィリピンは日本以外で一番「シティポップ短篇集」が刺さる国なのかも知れない(byピン中)。
オマケ
↓参考動画(Lola Amourのリーダーが大ヒット曲Raining In Manilaのタガログ語歌詞を英語で解説しているものだが、前半でいかに山下達郎のSparkle、80年代の日本の状況に影響を受けたかを語っている)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
