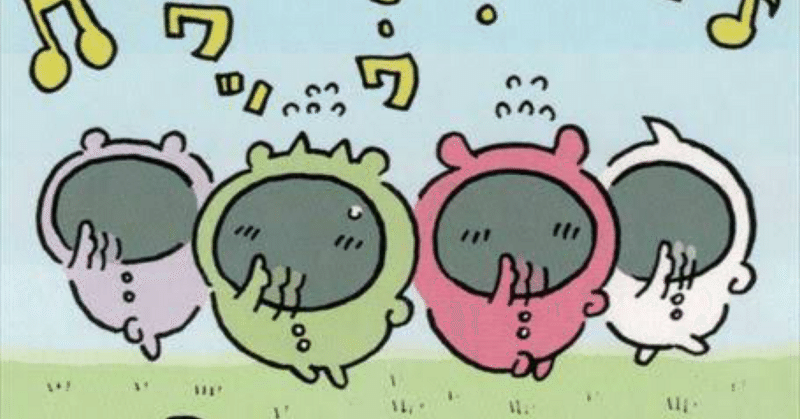
たった1人のパジャマパーティーズ 短編
いいよな、ちいかわ
いいよなぁ
「間」がね
「間」ね…
私はどこにでもいる中年男性。学生時代から付き合いのある友人3人と、不定期に通話をする。根っこがゲーマーの我々は、数十年前と同じかそれ以上の熱量で最近のゲームの話をする。
時折、目が悪くなったとかミョウガが妙に美味く感じるようになったとか、身の上話がでる。すっかりおっさんじゃん、お前もな、と時の流れを感じていた。
誰かが言い出した。「ちいかわって良いよな…」と。
そう、ちいかわは、良い。可愛さで売っているようで少し味わうと苦味やエグ味が出てくる。そしてそれらが、なんとも飲み込みやすいバランスで成立している。悲壮感とか、無力感とか、重ねてしまった年齢と傷跡に沁みる。名作だ。
友人の1人A氏が、真剣な語調で切り出した。
「俺たちもさ、パジャマパーティーズには成れるんじゃないか」
ひと笑い起きて、別な話題になるかと思ったが空気が静かに留まり始めた。皆、普段と違う真剣さを感じ取ったのだろう。
「俺達が歌って踊る…ってコト?」
「ェェ〜?」
「プルゥァッ」
みな戯けて振る舞うが、すぐに静かになってしまう。A氏は続ける。
「段々さ、元気、なくなっていくじゃん。いつまでバカなことやれるか分からないじゃん」
語調は明るいが、言葉の重さは濡れた布団のようだ。私を含めた3人は、何も言えなかった。
Bがようやく口を開く。
「俺たちがパジャマ着ちゃうとさ、ちいかわみたいにはならないと思うんだ。病院から逃げてきた中年患者っていうか。だからさ…」
そう、みんなそれぞれの生活がある。私にも家族ができた。Aは独身だが有名な会社で良い立場になっている。BもCも子供がいて忙しくすごしている。
「パジャマじゃなくて、全身タイツじゃ無いとあのフィット感は出せないと思うんだ」
私はツッコミを入れる前に「確かに」と思ってしまった。
「そう…かも」
「あのフィット感がなきゃ、パジャマパーティーズじゃない」
「あんだけフィットしてりゃ、俺達もかわいいんじゃないか」
ワッ…と会話が弾む。素材はどうする。誰が何色を担当するか。音源は誰が用意するか。いつ集まって練習をするか。
冗談半分で進んでいたはずが、皆スケジュールを調整し始めた。懐かしさと、昔一緒に遊んでいた頃の「熱」を思い出していた。
「スタジオとか公民館とかレンタルすれば練習できるんじゃないか?」「たしかに。場所抑えちゃうか」
学生時代も、みんなが浮かれている時に、正論を言うのが私の役回りだった。ちょっと待ってくれ、と話を遮る。
「…パジャマパーティーズが練習する場所は、公園じゃないか?見られることにも慣れないと」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ウ、ワ、ワ、ウワ!〜
全身タイツは蒸れる。運動不足で息は上がるし、関節が重い。身体が熱いが周囲の視線は冷たい。スマホでこちらを撮影している者もいるが、当然ファンではないし冷笑している。
「揃ってきたな、振り付け」
「歌いながら踊るのキツいな。竜宮小町もこんだけ大変だったのかな」
「まだアイマス2の話してるのお前くらいだぞ。辛さで言えばミルキィホームズだろ」
全員で汗を拭きながら、スマホで撮影した自分達の振り付けをチェックする。汗と加齢臭と、潰れたマメを拭き取ったタオルは嫌な臭いがする。馬鹿なことをしているが、不思議な充実感があった。
「B、お前は奥さんや子供になんて言って出てきた?」
「実は別居中でさ…離婚の話も出てたりして…Cは?」
「なんていうか…この歳になると、腹割って話せる友人って大事なんだなっていうか…家族と同じくらいの大切にしたい〜みたいな話したら、いってらっしゃいって」
「惚気るじゃん」
「ムカついて漏らしたから、ちょっとトイレ行ってくるわ」
季節は3月。本番は4月1日にした。エイプリルフールであれば、多少不審な格好をしていても黙認されるんじゃないかという見込みだ。大凡の振り付けは揃ってきたので、あとはパフォーマンスの改良に時間を割きたい。Aがトイレから戻ったら、入退場の演出を話し合おう。
「ヤダーーーーーーーーー!!」
中年男性の野太い悲鳴が響き渡る。Aだ。公園のトイレの方向から聞こえる。周囲に目を向けると、パトカーが停まっている。助けに行こうかとも思ったが、冷静になる。全身タイツの不審者が増えるだけだ。修羅場慣れしたAがあんなに情けない声で叫ぶわけがない。あの叫びは『早く逃げろ』と我々に伝えるためのメッセージかもしれない。
道具を急いでまとめて、撤収の準備をする。2人組の警察官がこちらに小走りで向かってくる。BとCが警察官に向かって走り出した。
「早く行け!」
「俺らは口割らないから、逃げろ!」
奇声を上げながら突撃する2人。断腸の思いで私は逃げた。ちいさくもないし、かわいくもない我々は、公園で踊ることも許されていない。中肉中背のキモいやつ。ちゅうきもだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4月1日。大きな公園には人がたくさん居た。恐らくライブ配信をしているであろう若者や、何かの企画なのかコスプレをする者や、地方番組の取材カメラも回っている。新年度の映像が欲しいのだろう。
私はA、B、Cが使っていたタオルを両手に結びつけ、全身タイツで構えていた。あいつらは出てこれない場所にいるが、パジャマパーティーズは終わっていない。
スピーカーを最大音量にして、たくさん練習したダンスを始める。
ウ、ワ、ワ、ウワ……
1人だと、なんとも物足りない。疲労でも緊張でもない、嫌な感覚に包まれて身体が重い。違う、俺はもっと踊れる。もっと歌える。仲間が居たんだ。本当は、1人じゃないんだ。
小さく聞こえる暴言、嘲笑。今までの人生で散々味わってきたはずなのに、今日はとても辛かった。確かに俺は気持ち悪い。不快で申し訳ない。そういう気持ちが、心のままに歌って踊りたい気持ちを刺している。それが辛かった。俺の中の心さえ、常識とか社会とかに追い込まれてしまっている。
現場には複数人の警察官がパトロールしていて、騒いでいる若者へ注意をしていた。当然私も注意を受けるが、明らかに嫌そうな顔と強い口調だ。
何やってんの?仕事は?連絡取れる家族はいるの?
クスクスと聞こえる笑い声。
公園から逃げた日の景色を思い出す。すごい罵声を浴びせられていたA、地面に強く押し付けられていたB、Cは口元を切って血が出ていた。
悪いのは我々だけども、そんなに強く殴らなくていいんじゃないか
もっと危ないことしてる若者には苦笑いで済ませるのに、我々には警棒を振りかざすのか
悲しさ、悔しさ、虚しさ、そういった感情が最大限に高まり、爆発した。気がつくと、左フックで警察官の顎を殴り抜いていた。駆けつけてくる警察とギャラリーを蹴散らし、全力疾走で公園から飛び出した。
久々に本気で人を殴ったし、本気で走った。学生時代の思い出が蘇る。
Aは当時キックボクシングをしていて、格闘技に興味があった私にミット打ちをさせてくれた。「モーションがわかりにくいから、お前の左は当たるよ!死角からの左フックだ!」と褒められた。教え方が上手かった。
Bは陸上部で、私を勧誘してくれていた。「もっと身体を起こして、真っ直ぐな姿勢を意識して。持久力はあるから長距離走向いてると思うんだけどなぁ。やろうよ陸上」と。ゲーセンまでランニングしてた日々が懐かしい。
Cからはよく人生相談を受けていた。「何だかんだ言って、真剣に話聞いてくれるから信用しているよ」と。それはお前が良い奴だからだよ、とは言えなかった。
公園の近くにある、警察署に着いた。公園で揉み合った時に額を切ってしまい、血が流れる。身につけていた3人のタオルをバンダナ状にして、額に縛る。元々嫌な色だったのに、血が滲んで鈍い赤色になってしまった。
パジャマパーティーズの歌を歌いながら正門から突撃する。
たった1人のパジャマパーティーズ、最初で最後の卒業ライブだ。
何度も練習したダンスと歌を、自分の全てをここでぶつける。複数人の警察官に抑えつけられながら、最期まで歌うのをやめなかった。
聞いてください。曲はドラゴンボールより
『ソリッドステート・スカウター』
完
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
