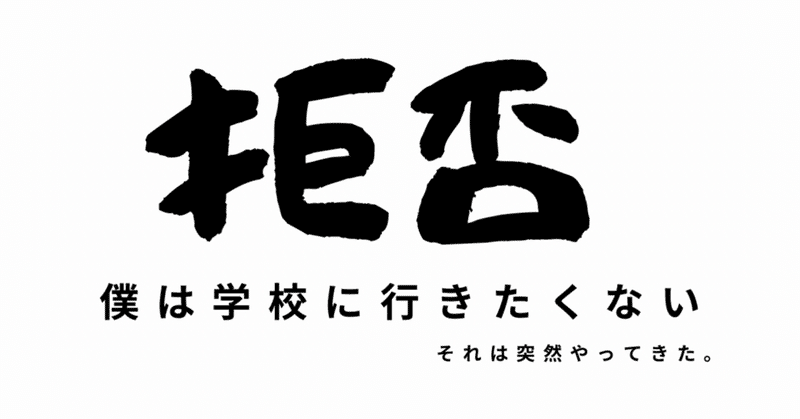
僕は学校に行きたくない
これは息子が小学3年生の時に突然起きた登校拒否のお話です。
息子は現在中学生。
身長は高め、体重は軽め、ズボラでマイペースな野球少年です。
今でこそ毎日元気に登校している息子ですが、小学3年生の頃に突然
「学校に行きたくない」
と言い出したのです。
この時の私の対処法が正しいのかは今でもわかりません。
それでも同じような状況で悩んでいる誰かの参考になればと思います。
1.始まり
それは何の変哲もない月曜日の朝でした。
いつものように登校の準備をしていたように見えた息子が突然
「学校に行きたくない」
と言い出したのです。
休み明けは誰しも気分が乗らないもので、これまでも「面倒くさいなぁ」とか「休みたいなぁ」と言うことはありましたが今回は様子が違います。
ソファに寝ころんだまま全く動こうとしません。
「月曜日って行きたくないよね。わかるわかる」
なんて声を掛けながらも準備するよう促しますが反応なし。
ついには「休みたい!」と言って泣き出してしまいました。
2.理由を探る
私も仕事をしていたので「休んでいいよ」と簡単には言えません。
しかし母として、「こんな時に休まなくていつ休むんだ!」
と自分に言い聞かせ、仕事を休むことにしました。
①話を聞く
まずは息子の話を聞かなければと思い、
「行きたくない理由を教えてほしい」
と声をかけました。
しかし息子は、
「わからない」
と言うばかり。
「教えてくれないとお母さんもわからないよ」
と言っても答えてくれません。
有力な情報を得られそうにないので別の方法を考えました。
②文字にしてもらう
もしかしたら言葉では言い表せない、もしくは言いたくない何かがあるのかもしれません。
そこで私は
「今思っていること、困っていること、何でもいいから書いてみて」
と言い、家にあったノートとペンを渡してみました。
すると息子はノートにびっしりと今の気持ちを書いてくれました。
書いてあった大まかな内容は
・学校に行きたくない
・疲れたから休みたい
・ゲームをしたい
・お腹の調子が悪い
・吐きそう
というようなもの。
結局これといった明確な理由は見つかりませんでしたが、体調が悪いから行きたくないのかなと思い熱を測ってみましたが、平熱です。
理由がわからずすっきりしないものの、今日は休ませて様子をみようと思い、1日家で過ごすことにしました。
③環境を変えて話してみる
お腹の調子が悪いと書いてあったものの、頻繁にトイレに行ったりする様子はありません。
そこで、
「ちょっとドライブに行こう」
と声をかけ2人で出かけることに。
ちょうど紅葉が綺麗な時期だったので、2人で景色を見ながら話してみることにしました。
いじめの可能性も考え、
「学校は楽しい?」
と聞いてみると、
「まぁ楽しいよ」
とのこと。
ただ、友達との関係には少し悩んでいるようで、
「僕が女の子と話していると、〇〇くんが、あの2人は付き合ってるとか好きなんじゃないのってからかってくる」
と話してくれました。
息子が通っている学校は小規模で、幼稚園のころからの付き合いの子たちばかり。
私が下の子の出産で仕事をしていなかったこともあり、息子も幼稚園に入ったのは他の子たちよりも遅かったのです。
息子が入園したときには既に子どもながらにコミュニティが出来上がっていて、「後から来たくせにと言われて嫌な気持ちになった」「どうしてもっと早く入園させてくれなかったのか」と言っていたことが何度かありました。
からかってくる友達は主に2人のようですが、その2人とも仲良く遊んでいる時もあり、明確に「いじめ」とも言えません。
それでも嫌な思いをしたことは事実なので、この話は念頭に置いておくことにしました。
3.向き合い方
結局理由がわからないまま数日が経ちました。
最初のうちは、渋る息子をどうにか説得し学校へ連れて行っていたものの、泣きじゃくり、うずくまって動かなくなる息子を登校させるのは簡単なことではありませんでした。
私自身も疲れてしまい「泣きたいのはこっちだよ」と言ってしまったこともありました。
私より先に仕事へと出かけていく夫は、朝の息子の様子を実際に見たことがないため、「そのうち行くようになるでしょ」と楽観的。
子育てには協力的な夫ですが、息子の様子を目の当たりにしたことがないのでとても温度差がありました。
そのうち説得することに疲れ、丸1日休ませたことも何度かありました。
①担任の先生と情報共有
当時の息子の担任の先生に事情を話すと、
「無理やり連れてきてくださいとは言えませんが、登校させてくれればこちらで出来ることは全力で対応させていただきます。一番大変なのは、家に引きこもってしまい、状況が見えなくなってしまうことです。そうなってしまっては私たちに出来ることが限られて。登校させてさえくれれば力になれることは必ずあります」
と言ってくれました。
そして私からは、
「登校したらなるべく普通に接してほしい。あまり気にかけて頻繁に声掛けをするとかえって気持ちが沈んでしまう可能性があります。ただ、本人から何かしらの訴えがあった時には聞いてくださると助かります」
と伝えました。
泣いている時に優しくされると余計に涙が出てくる現象ってありますよね?あまり特別扱いをされると必要以上に甘えてしまったり、自分は今かわいそうな子なんだと変に思い込んでしまったりするのではないかと心配でした。
しかし、困った時には手を差し伸べてくれるという環境は保障してあげたいとも思いました。
無理なお願いかもしれないと思いましたが、先生も全面的に協力しますと言ってくださいました。
②病院へ
ノートに書いてもらったり、景色を見ながら話をしたことでわかったのは、本人的にもこれといった明確な理由が無いということでした。
友達との関係で悩んでいるというのが最有力候補でしたが、話しているうちにそれもコロコロと変わります。
「からかわれて嫌だった」「〇〇先生が苦手」「吐きそう。具合が悪い」など訴えの内容が定まりません。
どれも本当の気持ちなのかもしれませんが、私に聞かれたから答えなければならないと思い絞りだしたようにも感じました。
理由がわからなければどうしようもないとはいえ、毎朝学校に行かせたい私と行きたくない息子で押し問答を繰り返していても状況が変わることはありません。
そこでまずは、「具合が悪い」の部分を解明することに。
何度測っても熱は無く、風邪症状もありません。吐き気がすると言っていますが実際に吐いたことは1度も無かったので、病院に連れて行っても良いものか、何を理由に診察してもらえば良いのか、こんなことで病院に連れてくるなと言われるのではないかと思い、なかなか連れて行けずにいたのです。
しかし、このままでは前に進めないと思った私は、思い切って病院に連れて行くことにしました。
今の状況を変えるきっかけになれば良いと思ったことと、私が説得するよりも、実際に診察してもらいお医者さんから「大丈夫」と太鼓判を押してもらうほうが効果があると考えたからです。
かかりつけの小児科の先生は優しい年配の先生です。
息子には聞かれないように事情をすべてそのまま説明し、診察してもらうことに。
「具合が悪いのは辛いね。先生がちゃんと調べてあげるから」
と言って問診や尿検査、血液検査をしてくれました。
結果、体には異常が無いことがわかりました。
「大丈夫。きみの体は元気だ!心の元気が無いのは先生は診てあげられないけど、体は健康で元気だと証明できたから安心してね」
と言ってくれました。
それ以来気持ちが軽くなったのか口数も増え、以前の明るさを少し取り戻したように感じました。
③約束
ストレスが原因で体調を崩すことがあるように、健康面で問題がないからと言って「さぁ学校に行きなさい」と言うわけにはいきません。
しかし病気が原因ではないことがわかり、私としてもホッとしました。
そこで、
「元気なことがわかったからいつものように学校に行ってほしいなと思っているんだけどどうかな」
と話してみました。
しかし「行きたくない」という息子の主張は変わりません。
これでは議論は平行線のままです。しかしこれまで色々とそれらしい理由を並べてどうにか登校させ、保健室で過ごしたりすることもあったのですが、これでは私の主張を押し通すばかりで、息子の想いを聞いてあげられていないことに気付きました。
そこで私から、
「どうしても休みたいという気持ちは良く分かった。これまで色々と無理を言ってごめんね。今日は1日学校を休んで好きなことをやっていていいよ。その代わり、お母さんのお願いも聞いてくれるかな?」
と伝えてみました。
息子も「いいよ」と了承してくれたのでこんなお願いをしてみました。
「今日は1日お休みにするけど、これからは遅刻しても良いし早退しても良い。でも1時間でも30分でもいいから毎日学校には行ってほしいな。インフルエンザでしばらく学校を休むと、その後行きづらいなぁって思ったり、教室に入る時ちょっと緊張しちゃうことってあるでしょ?長くお休みをしてしまうと、元気になってまたいつものように学校に行きたい!と思っても行きづらくなってしまうと思う。だから休みたい気持ちも大事にするし、いつかの自分のために学校に行ける準備もしておいて欲しい。半分頑張って、半分頑張らないってことにしてほしいな」
正直、行きたくないとうずくまって動かない息子を説得して登校させるよりも、このまま休ませてしまう方が遥かに楽だと思いました。
しかし1度休み癖がついてしまうとそのまま不登校になってしまう可能性は大いにあります。
そうなればまた学校に行けるようになるまでには相当な時間と労力が必要となるでしょう。
どんな形でも、毎日学校に足を運ぶという習慣を壊してはいけない。
そう感じました。
ただし、これはイジメが原因ではないと判断したからであって、必ずしも欠かさずに登校させることが正しいとは言えません。
最近では、無理に登校させずに自宅で学習したり、「学校」というものの価値観が大きく変化していることは分かっています。
必ずしも不登校がダメなこととも思いません。
それでも「学校」でしか得られないものがたくさんあること、田舎に住んでいるため、自宅で学習できる環境や塾などの施設が無いことを考えても、登校できる未来を目指すことが息子にとってはベストだと思いました。
それでも息子がこのお願いを受け入れてくれなければ、無理に登校させるべきではないとも思っていました。
しかし、渋々ではありましたが息子はこの提案を受け入れてくれました。
④応援要請
頻繁に早退や遅刻をするとなると私も仕事を休まなくてはなりません。
しかしいつまで続くかもわからないこの状況に1人で対処するのは不可能です。
幸い私の実家が近くにあり、母は仕事をしていなかったので事情を説明し、協力をお願いしました。
私だけではとても対応しきれなかったので、実家の母にはとても感謝しています。
また、息子は相当なばばっ子でもあったので、何でも気軽に相談できる間柄であると同時に良き理解者でもありました。
このような状況に1人で対応することはとても難しいことです。
必死に向き合おうとする人自身の心が折れてしまっては元も子もありません。
頼れる人は片っ端から頼るべきだと思います。
4.変化
「約束」のあとも行きたくないと泣き叫ぶ毎日は変わらないものの、それでも休むことなく学校に足を運ぶことが出来るようになりました。
動き出してしまえばどうにかなるものの、行くまでが辛いのは大人でもよくあることですよね。
それでもすぐに「帰りたい」ということもあったようですが、先生が
「それじゃあ今日は給食を食べたら帰ろう」とか「午後の理科の授業では実験をするよ」などと上手く話しながら対応してくださっていたようです。
この頃、行きたくない理由は主に「吐き気」でした。
あまりに吐き気を訴えるので、もう一度病院にも連れて行きましたが結果は同じ。
それ以外の理由については、本人の口から何かしらの訴えがない限りは必要以上に追及しないことを心がけました。
あまり何度も聞きすぎると、行きたくない理由を無理に作り上げてしまう可能性があると思ったからです。
本当はそう思っていないのに、何度も口にしているうちにその気になってしまうという事態は避けたいと思いました。
①息子の変化
そんな生活が3か月ほど続いたころ、学校で演劇の発表会が行われました。参加できないのではないかと思っていてのですが、少ない登校時間の中でどうにか練習し、本番も「緊張する」と言って吐き気を訴えながらも休みたいとは言わずに参加することができました。
私の中ではそれだけで万々歳!口元を抑えながら小さめな声ではありましたがよく頑張ったと思います。
息子自身も参加できたこと、最後まで演じきれたことで自信がついたようで晴れやかな顔をしていました。
正直、参加させるかどうかはギリギリまで悩みました。
なぜなら、いつも吐き気を訴えていた息子は、口元を手で覆う仕草が癖になっていたからです。
家族は見慣れていたのであまり気にしていませんでしたが、他の人が見たらどう思うのだろうと不安だったからです。
それでも「休む」という選択をしなかった息子の意志を尊重すること以上に大切なことがあるだろうかという結論に至り、参加させることに決めました。
息子にも少し良い変化が見られた日でもありました。
②周囲の変化
よく頑張った!と思っていた家族とは違い、いつも面倒を見てくれていたとはいえ、学校での様子を知る由もない実家の母にとってはショックな光景だったようです。
「あんな姿で発表会に出るなんて恥ずかしい」
と息子に対して怒鳴ったのです。
今思えば、母も相当疲れていたのだと思います。
しかし、当時は私もそんなことに気付く余裕もなく、
「どうしてそんな冷たいことが言えるの?立派に演技してたし、一生懸命頑張ってたよ!」
と言い返しケンカに発展してしまいました。
その時たまたま居合わせた私の姉が仲裁に入ってくれ、
「私も〇〇があんな状態だとは思わなかったから母の気持ちもわかる。でも家族にしかわからない事情もあるだろうから、頭ごなしに怒るのもよくないよ」
と言ってくれました。
そこでようやく私も、日頃から面倒を見てもらっているのに、家族としてどう対処していくつもりでいるのかを母に共有していなかったことに気付きました。
そこで私から
・遅刻や早退はしても良いから休まずに登校しようと伝えてあること
・周りの目を気にするよりも本人がやりたい事、出来る事をやらせてあげた いと思っている事
・どんな形であれ登校できたことや、行事に参加できた時には褒めてあげたいと思っていること。
の3つを伝えました。
そしてこのケンカをきっかけに同じ方向を向いて息子の「行きたくない」に対処して行こうと思えるようになり、より強いチームが完成しました。
しかしこの出来事の数日後、母も私も息子の対応に疲弊していて心身共に限界だったようで、熱を出して寝込むこととなりましたとさ。トホホ
一定の期間が過ぎると疲れが出てくるようです。
自分や周囲の気持ち、体調の変化も見逃さないようにしましょう。
5.突然の終息
そんな生活のまま冬休みに突入。
そしてこのタイミングで息子の「学校に行きたくない」はあっさりと終息しました。
期間にして4か月程度ではありましたが、永遠に続くのではないかという不安。
このまま二度と元気に登校する姿を見ることは出来ないのではないかと悩み、本当に苦しい時間でした。
私も息子もたくさん泣いた辛い4か月でした。
①交友関係を変える作戦
登校拒否が終息したあとも、からかってくる友達との関係は相変わらずだったので、何かしらの対処をする必要はあると感じていました。
さらに、息子がよく言っていたのが、
「みんなとそれなりに仲は良いけど、一番仲良しの人は誰?って聞いた時に僕の名前を言ってくれる子はいないと思う」
という言葉でした。
この交友関係を変えるためにはどうしたら良いのかと悩む日々。
もちろん大きくなるにつれて人間関係は変わるだろうし、子ども同士の力関係というのも変化するはずです。しかし息子は「今」困っていて「今」変化を求めているのです。
そんな時、ママ友から
「〇〇くん、野球に興味ない?少年野球のチームなんだけど、人数が足りなくて困ってるんだよね」
と声を掛けられました。
これまでも何度か誘ってくれていたのですが、息子が興味を示さなかったことと、どちらかというと運動は苦手なほうだったことから断っていたのです。
しかし、これはチャンスかもしれないと思いました。
今回のことをきっかけに、何か夢中になれるものや、我武者羅に頑張れるものに出会い、自分の力にしてほしいと感じていました。
さらに、その野球チームには息子の同級生が数名所属していたので、同じスポーツで汗を流し、楽しい・悔しいといった感情を共有することで交友関係に変化があるのではないかと思ったのです。
そこで息子に話してみたところ「やってみたい」との返事が!
私も夫も野球の経験は無く、知識も無い。
お金もかかるし遠征や大会で休日も忙しくなる…など不安もありましたが、息子のためになるならば!と思い切って入部させることに決めました。
②出会い
この選択はずばり大正解でした。
一緒に過ごす時間が増えたことで「親友」と呼べるほどに仲良しな友達ができ、交友関係で悩むことがなくなりました。
その子とは今でも大の仲良しで、暇さえあれば野球の話ばかりしています。
そして親も子もすっかり野球に夢中になり、今までこれといった趣味が無かった私も「息子の野球応援」が趣味になりました。
息子自身も、早く上手くなりたい!試合に出たい!という気持ちから、チームでの練習以外に自主練もするようになり、野球が楽しくて仕方がないようでした。
そして念願だったレギュラーの座をゲットできたことで自信がついたようで、学校生活においてもリーダーに立候補したり、これまで避けてきた係の仕事にも挑戦するようになりました。
そんな様子を見ていたからなのか、単純に時間が解決してくれたという事なのかは分かりませんが、クラスメイトにからかわれることもなくなり、今では良い距離感で生活出来ているようです。
③最後に
この4か月を振り返ってみると、すぐにでも忘れてしまいたいほど苦しい時間でした。
きっと私以上に息子は苦しんでいたことでしょう。
それでも逃げずに立ち向かったからこそ今の生活があり、今の息子の姿があるのだと思います。
どんなに辛くても私との約束を守り、毎日学校に足を運び続けたこと。
そこで身に着けた力はこれから先、息子を守る盾となり、何かに立ち向かうときには武器となってくれるだろうと信じています。
冒頭にも書きましたが、これが正解だとは限りません。
色々な意見があると思います。
それでも今笑顔で登校していること、夢中になれるものに出会えたこと、大切な仲間がいること。
私たち家族にとってはそれが全てです。
母として、悩んだり壁にぶつかることはたくさんありますが、母だって人間です。簡単には上手くいかないなんて当たり前の事。
そのたびに子どもと一緒に成長していければ良いのだと思います。
6.まとめ
①私の対処法一覧
・まずは話を聞く
・気持ちを紙に書き出してもらう
・いつもと違う2人だけの空間で話をしてみる
・息子の要求を受け入れる
・その代わりに私の要求も聞いて欲しいとお願いしてみる
・親の想いは背中で語らずなるべく言葉で伝える
・プロの太鼓判をもらう
(息子の場合は小児科の先生)
・先生や協力してくれる人としっかり情報共有
・遅刻、早退OK!でもなるべく休まない
・多くを求めず、出来たことを褒める
・環境を変えるため、新しいことに挑戦させてみる
②感じたこと一覧
・子どもだからわからないと決めつけずに本音で話すことが大切
・時々は現実逃避をすべし。いつも全力で向き合い続けていたら壊れてしまいます。誰かに預けて買い物に行くも良し!ちょっと高いスイーツを買って食べるも良し!悪いことではありません。むしろ必要な時間です。
・先生からの連絡は必要最低限に。このような場合、毎日状況報告の電話をくれたりする場合もあるようで、それはそれで先生の気遣いなので有難いと思う反面けっこうしんどかったりすると思います。お互いに。なので私はよくも悪くも変化があった時だけ連絡をくれるようにお願いしました。
・成功体験の積み重ねは大事。この時、休日に外出することも嫌がっていたので(理由は吐きそうだから)、無理に外出させることはしませんでした。ただ調子が良さそうな時は少し強引に連れだして、「買い物に出かけても吐かなかった」という事実を自分自身で体験することによって外出もするようになりました。
子どもの「学校に行きたくない」で悩んでいる方はきっとたくさんいると思います。
絶対大丈夫!なんて無責任なことは言えません。
それでも、私の経験から何か1つの言葉・行動・対処法、どれでも良いので誰かの力になれたらと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
