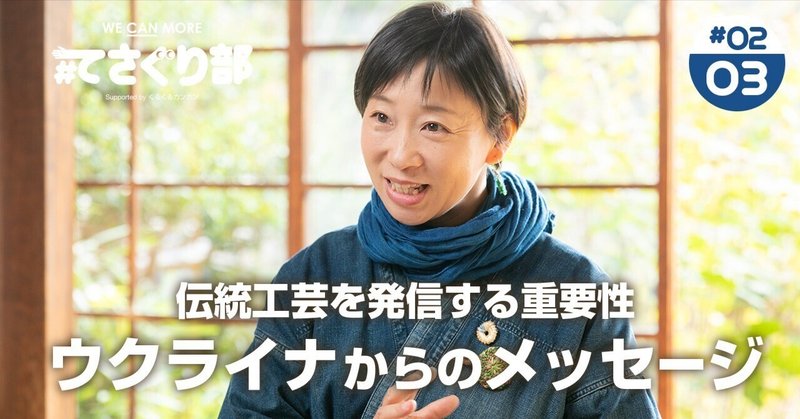
伝統工芸を発信する重要性に気がついた、ウクライナからのメッセージ
一度は途絶えかけた日本唯一の編みの技術、「大森細工」を引き継いだ、麦わら細工職人の辻享子さん(前回のお話はこちら)。
製作のかたわら、SNSやイベントを通じて魅力を発信し続けている。そしてある日、SNSがきっかけで、その貴重な技術が海外でも知られることに。
苦手なSNSを活用し始めた理由

享子さんは今、X(旧Twitter)、Instagram、Facebookなどで、作品や工房の様子を発信している。
手のひらに載せた可愛らしい動物たち、壁に映る影も美しい編みの置物、夜を照らす妖艶なほたる籠……。「民藝麦わらの店 晨(あした)」の投稿には美しい作品が並ぶ。眺めていると、「このアクセサリーが欲しい!」「これ、部屋に置きたい!」と思うものが次々と出てくる。
その中には、日本で唯一、この工房だけが技を持つ「大森細工」の作品も。麦わら細工の編みの技法の一つである大森細工は、麦わらを 4 回折り合わせて菱形の網目を作り、それをきれいに連ねて、ふっくらと丸みのある形に仕上げるのが特徴だ。その名のとおり、東京・大森で発祥。一度は途絶えかけたが、今、享子(3代目)さんとお母さんの紀子さん(2代目)が継承し作品づくりに勤しんでいる。
技術を磨いても知ってもらえなければ意味がない
今では毎日のように情報を発信している享子さんも、かつてはSNSにあまり興味がなく、ただただ、ひたむきに作品づくりをしていたのだという。一念発起して、SNSを始めたのは3年前。
「もともと、麦わら細工の魅力を一人でも多くの人に伝えたいという気持ちはありました。でも、なかなか機会がなくて。奮起したきっかけは、ネットにあった『麦わら細工の技術が“唯一”残る城崎』という間違った記述を見つけたこと。正しい情報を発信して多くの人に知ってもらわなければ、大森で継承されてきた麦わら細工は途絶えたと誤解されてしまう。そう危機感を覚えました」

Instagram https://www.instagram.com/mugiwara_shuzenji
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100071181797975
X https://twitter.com/monchiki213
麦わらとSNSがつないでくれたウクライナの職人

コツコツ発信し続けるそんなある日、ふと、海外とつながることに。
「3年前、知らない国の言葉でSNSにメッセージが届いたんです。最初は不審に思って取り合わなかったのですが、繰り返しアプローチがあって。ついに翻訳アプリで読んでみたら、ウクライナの女性、ミラさんからのメッセージでした」
リシチェンコ・リュドミラ(通称ミラさん)は、ウクライナに暮らす70代の麦わら細工職人。伝統的な技術を駆使した作品は、現地の博物館にも展示されている。
「アナログ世代の彼女が1日も欠かさずに発信し続けていたのは、ネットで発信すれば誰かが見てくれるという希望があったから。そして、麦わら細工に関する投稿を探すなか、大森細工の写真を載せた私の投稿を見つけてくれたんです」
おりしもその頃、享子さんもお母さんも、技の継承を諦めかけていたという。
「後継ぎがいないので、大森細工を後世に残すのは無理かなと諦めかけていました。でも、素晴らしい日本の伝統を絶やしてはいけない!というミラさんのメッセージに、『大森細工は日本で唯一の技術なんだ!』と、あらためて気づいたんです。私たちの技術を受け継ぎたいという人が出てきてくれるように、たくさんの人に知ってもらわなくちゃと、前向きな気持ちになれました」

Instagram https://www.instagram.com/straw_from_love/
Facebook https://www.facebook.com/BeautifulStraw
オンラインだけでなく、実際に手にとって欲しいから

麦わら細工に理想的な素材を得るため、麦も自分たちで育てている
見て、触れて、感じて知ってほしいから「アナログ作戦」を展開
ミラさんとSNSを通じて交流を深め、アメリカやポーランド、ベラルーシ、カナダ、フランスなど、海外の職人と知り合うことができた享子さん。これをきっかけに、「この素晴らしい技術を未来に残さなければ」という思いをますます強くしていく。
「とはいえ、世間で知られていなければ、どんなにSNSにあげても検索さえしてもらえませんよね。こうなったら、見て、触れて、感じて知ってもらうしかない。麦わら細工を実際に見て、触ってもらえるアナログ作戦を展開しようと決意しました」
そこで享子さんがチャレンジしたのは、個展開催に向けたクラウドファンディング。
「実は5年前、地元の伝統工芸職人を紹介する冊子の刊行をゴールに掲げ、クラウドファンディングに挑戦したことがあるんです。その時は目標金額にまったく届かず惨敗でした。お金を募る難しさはもちろんのこと、『なぜ、伝統工芸の魅力を分かってもらえないんだろう?』と思うと悲しくて。伝統工芸や麦わら細工や自分を全否定された気持ちになって、数日間は毎晩しくしくと泣いていました」
それでも挑戦するのは、大森細工を絶やしてはいけないという思いから。今回はSNSという手段を使いながら、目標達成に向けて走り出した。
初代が職人となり工房を開くまでの軌跡、もともとは温泉街のバナナ園だった工房の歴史、強くて美しい麦わら細工のこと……。プロジェクトページに麦わら細工への思いを綴ると、次々と賛同する人が現れ、目標金額65万円を5日で達成。最終的には目標額の194%という資金を集めることができたという。
「ご支援いただくだけでなく、多くの方がSNSでクラウドファンディングのことを拡散してくださいました。目標達成が叶うまで私と一緒にドキドキしてくれている人がいて、とても嬉しかった」

個展を開催、麦わら細工に光が当たった!
開催地は、江戸時代に麦わら細工が一世を風靡した地、東京を選んだ。
名付けた個展のタイトルは、麦わら細工が未来も輝き続けることを願って、「再興 Rerise 麦わら細工」。
張り細工へのライティングは、麦わらがより煌びやかに輝くように。
吊るした作品が、エアコンの風の流れで優しく揺れるように。
編み細工の影が、より美しく壁に映るように。
……など細部にまでこだわり、麦わら細工の魅力が伝わるように工夫した。
そんなこだわりが功をなし、3日間の開催期間中は、幅広い年齢層の人が来場した。初日の朝は雨天だったにもかかわらず、オープンを会場外で待つ人がいるほどの盛況ぶり。
「SNSを見て来てくださった方がたくさんいました。なにより、麦わら細工の美しさや面白さを来場者の方々と共感できたのが嬉しくて! 麦わら細工を知ってもらえて、とても幸せな時間でした。心なしか、作品たちも生き生きして見えましたよ」。
個展会場のTerritory Gallery。白い壁に映えるよう、展示の仕方にもこだわった
個展を終えた後も、麦蒔きやクラウドファンディングのお礼とお返し、来年の干支の置物づくり……と、享子さんは休む間もなく活動している。そんな麦わら細工愛にあふれる享子さんに、作品づくりを直伝してもらえることに! 工房のこれから、享子さんの今後の目標を伺いながら、ライターKが初めての麦わら細工づくりに挑戦する。

製作に時間がかかるため、販売は20体限定
次回に続く。

クレジット
文:K
編集:JOURNALHOUSE
撮影:伊東武志(Studio GRAPHICA)
校正:月鈴子
取材協力:民藝麦わらの店 晨、茶庵 芙蓉
制作協力:富士珈機
#てさぐり部 とは

#てさぐり部 は「知りたい・食べてみたい・やってみたい」──そんな知的好奇心だけを武器に、ちょっと難しいことに果敢に取り組み、手さぐりで挑戦する楽しさを見つけようというメディアです。
決まったメンバーを「 #てさぐり部 」と呼んでいるわけではなく、答えのない挑戦を楽しむ人たちの総称として使っています。
だから、なにかちょっと難しいことに取り組む人はみんな #てさぐり部 です。noteをはじめ、公式InstagramやXでのコミュニケーションなど、積極的にハッシュタグを使ってくださいね!
お問い合わせメールアドレス
contact[アット]kurukurucancan.jp
