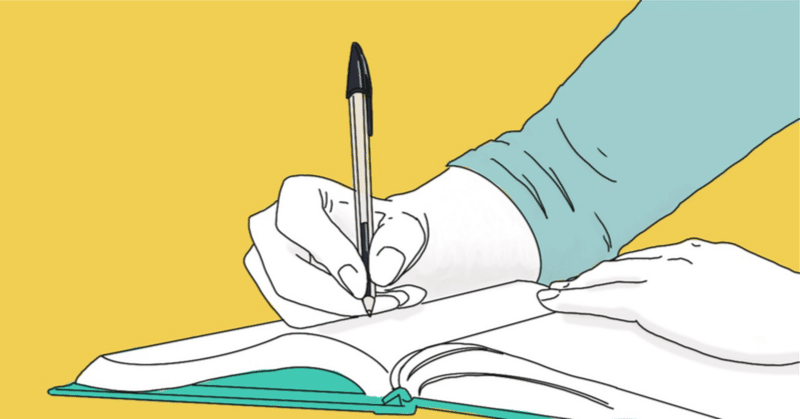
あの…その「写経」本当に効果ありますか?
文章がうまくなりたかったら、とにかく写経してみな!という風潮、わたしはちょっと懐疑的です…というのも、ただの書き写しは、ほぼ「無意味」だから!
もの書きなら、一度は試したことがあるだろう「写経」。
今回は、効果のある写経ってなにか?
具体的にどうやったらいいのか?を考えてみようと思います。
一般的に「写経」とはお経を書き写すことですが、ここではライティングの練習をするために、他の人の記事やエッセイを書き写す練習法のことについて書いていきます。
写経は「無意味」と思いこんだ思春期
ことの発端は、くろめがが中学生のころ。
うん十年前まで遡らなくてはなりません…
タイムリーーーープ!!!
当時、学校には朝学習タイムがあり、月ごとに課題がローテーションするシステムでした。
新聞の社説を書き写す課題もあったのですが、担任から詳しい説明はなく(あったのかもしれないが、まるっきり覚えていない…)ひたすら写経する日々がはじまります。
書き写したら文章がうまくなる!という話だったので(そこだけは都合よく覚えてた笑)当時から本の虫だったくろめがは一生懸命に写していたのですが…
開始10分くらいでなんの意味もなさそうなことがわかり、それから先何年もその気持ちが覆ることはありませんでした。
写経をがんばっているそこのあなた!
このときのわたしと同じことになっていないでしょうか?
ギクッとした方のために、わたしが「あれ?写経ってやっぱり役に立つかも…?」と思ったところまで時を進めましょう。
イラストをはじめて変わった写経への意識
写経への意識が変わったのは、社会人1年目のとき。
かねてからデジタルイラストを描いてみたかったわたしは、初めてのボーナスをはたいて当時最先端だったiPad Pro(第一世代)とApple Pencilを購入。
念願のデジ絵デビューを果たしました。
(文章の話じゃなくてスンマセン…汗)
当時は『宝石の国』にハマっていたので、お昼休みは誰もいないフロアに行き、市川先生のイラストを見ながらせっせとトレースをしました。
描くことに慣れてきたら模写に移行。
わたしがめっちゃ大事にしてる画集。箔押しいっぱいで美しさ無限大。余談だけど評価レビュー200件超えで星4.8ってすごすぎない?笑
そこそこの期間、この練習をくり返したことで、理想とするイラストの方向性が見えてきました。
(もちろん市川先生には遠くおよびませんが、その中でも妥協点というか、自分の技術との兼ね合いで折り合いのつくところ)
で、ある日気づいたのです。
(あ、これが文章で言うところの写経なのか!)と…!
モデルにしたいイラストがある場合の練習はこちら。
・モデルを上からそのままなぞる「トレース」
・モデルを見ながら似せて書く「模写」
このふたつは厳密に区別されています。
トレースでは、描き方、塗り方など、モデルの技巧的なところを追体験しながら学べます。
考えずとも手を動かせば描けてしまうので、ラクに数をこなしやすい分、手を動かした量と身になる量が釣り合わない感じもします。
一方の模写は、より観察が必要になるので、頭を使わなくてはいけません。
作者の意図やクセ、そのイラストをイラストたらしめている要素はどこなのか?などを観察し、「どう描いたら似るのか?」を考えながら描いていきます。
時間もかかりますし、頭も使います。ただ、考えた分アウトプットの質はあがります。
で、ここで「写経」に話を戻していきたいのですが、写経って、ここまで正確にやり方がわかれていませんよね?
写経のやり方をちょっくらググってきましたが、
・数をこなす(なんで?)
・読まれてる人気の記事を選ぶ(ほう)
・でもジャンルはドンピシャじゃなくてもいいよ(え?なんで?)
・コピーライティングの知識を入れてからやろう(具体的な話はほぼなし)
みたいな上位記事が多かったですし、そういう曖昧さもあって、なんとなく写経を続けてしまう方が出てくることにつながるのでしょう。
効果の出やすい写経のやり方
じゃあ効果が出る写経ってなんなんだいっ!(なかやまきんに君風)
わたしもイラストの件があってから、たまにですが文章の写経もするようになりました。
でも、さっきの上位記事の方たちの主張とはだいぶ違ったやり方です。
題材は現状をわかってから
わたくし大学生になるまで十数年くらい、ちょっとガチめにピアノをやってたんですが、目的もなく通し練習(最初から最後まで弾きとおす練習)ばっかりしてもぜんぜん上手くならんのですよ。
何かを練習するのであれば、
・どこが弱いのか(現状の把握)
・どこを目指すのか(理想/目標の設定)
このふたつをしっかり定めることが不可欠です。
なので、たとえばくだんの記事の言うように「コピーライティングの技術をかじってから写経に挑め」というのであれば、
・自分はコピーライティングをどこで/なにに使うのか?
ここが明確になってないと、題材を選べません。
たしかに、突き詰めていけば「あらゆるところに共通するポイント」みたいなものはあります。でも、さっきのイラストの話に戻って、


描きたい人たちが、同じ題材で練習するのは効率的だと思いますか?
思いませんよね?
なので、(さっきの話なら)自分がどんな場面でどんなコピーライティングをしたいのか?をしっかり決めてから題材を選んだほうが絶対いいです。
同じWebでも、ニュースやブログ記事なのか、情報商材なのか、メルマガなのか、SNSなのか…同じコピーライティングでも毛色が違いますもんね。
ちなみに、イラストのように「こんなのが描いて(書いて)みたい!」というので決めるのも大いにアリだと思います。
量は少なくても別にいい
題材を決めたら、次は弱点の把握です。
つまり、「どこが」「なにが」できないのかを考えて「どこまで」「どう」なりたいのかを決めること。
たとえば…
★とあるブロガーさん
キャッチーな記事タイトルをつけるのが苦手なんだよな〜
【ゴール】キャッチーなタイトルのストックを増やす
→ニュースサイトのタイトルだけをたくさん写経しよう
★とあるWebライター初心者さん
とにかく文章を書くのが苦手だから、上手い人の手クセをわたしの両手にも宿らせたい!
【ゴール1】上手い文章の型の習得
【ゴール2】こなれた文章がどんなものかわかる
【ゴール3】タイピングの速度をあげる
【ゴール4】量を書くこと自体に体を慣れさせる
→似ているジャンルの上位記事を写経してみよう
この場合は、もう少し悩みや目標を細かく分析してみる必要がありますね。手クセを宿らせる、をさらに明文化して、どのゴールに行くかを考えなくてはいけません。ただ、考えすぎて動けないよりは、まずはやってみて、やりながら考えるのもひとつ手ではあります。思考停止でやり続けるのがいちばん危険です!
★とあるnoteエッセイストさん
最近、導入からボディーにもっていく流れがワンパターンになりがちだなぁ
【ゴール】導入から本文へのつなぎのバリエーションを増やす
→好きな作家さんの導入〜本文へのつなぎをいくつか写経してみよう
これも、目的によって「複数人」やるのか「好きな一人だけ」やるのかは変わってきます。バリエーションを増やしたいなら複数人、好きな作家さんの雰囲気を自分の文章にも宿したいならその作家さんだけです。
練習方法はイメージしていただけたでしょうか?
この理論でいけば、目標がきちんと達成できるなら、細切れ写経でも部分的な写経でもいいわけです。
無理に量をこなす必要も、別にありません。
ちなみに、ここでは記事の都合で題材→弱点としていますが、もちろん題材決めと弱点決めは順不同です!
写経にもどかしさを感じている方、写経をやる=たくさんとにかく書く!ではない(とわたしは常々思っている)ので、ただひたすらに量を書く写経から、いったん離れてみてはどうですか?
ご自身の悩みと目的/目標をしっかり決めることが、写経の効果をきちんと引き出す「要(かなめ)」ですよ!
もちろん、どんな世界にも量にものを言わせた練習法はありますし、それらを否定しているわけではありません。ただ、そういう写経以外にも効果が出るし、楽しいやり方があるよ!というのが伝わったらうれしいです^^
ほかにも、やってみて効果が実感できた練習法や写経の方法があれば、コメント欄でぜひ教えてくださいね!
それではまた来週!
【追伸】
8日(土)夜9:00から、Webディレクターの桐野ひさやさんとXでスペースをやります!(ひさやさんは100日noteを達成したやり手のクリエイターさんです^^)
テーマはズバリ「読まれるnoteの書き方/続け方」なので、ご興味のある方はぜひ聞きにいらしてくださいね!(終了後はここにアーカイブのリンクを貼っておきます)
スペースでは質問も大募集中です!
・毎日noteのコツは?
・育児しながらいつnote書いてるの?
・睡眠何時間ですか?
などなど、noteに関係のないことでも、ひさやさんやくろめがに聞きたいことがあれば下のフォームからぜひどうぞ^^(ここに書きこんだらすぐ送れます!)
▼このnoteを書いた人▼

文字の世界を渡り歩いて6年目。noteを愛するフリー編集者。悩めるクリエイターさんやライターさん向けに、noteがもっと楽しくなる情報を発信中。X(Twitter)ではラフな雰囲気で、交流メインに活動中。企画やスペースなどもやっています。
▼無限サポートつき記事はこちら▼
note初心者さん、note迷子さんを全力で応援します!質問に対して何度でもアドバイスや添削を受けられる「質問券」つき^^
▼Kindle本も出しました▼
note記事とスマホで手軽にKindle出版する方法をまとめた本です。あなたも出版…いかがですか?^^
サポートすると、記事をオススメとして紹介することができます。おもしろかったら、あなたのフォロワーさんにもオススメしていただけるととっても嬉しいです✨
