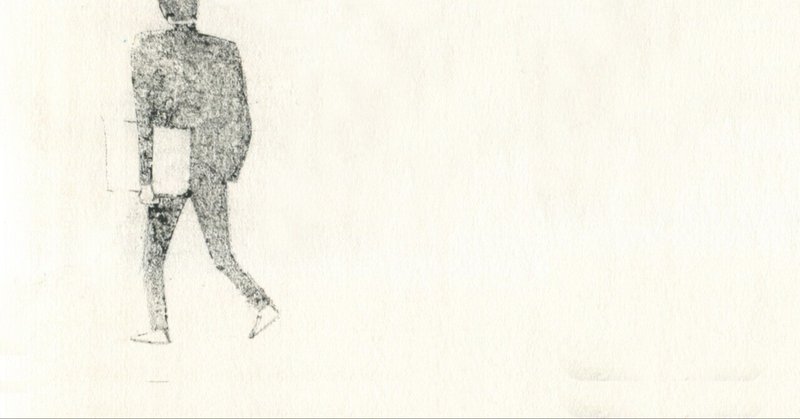
こういう日に君は来たまえ
この年まで生きてきて、興味の無いものは?と聞かれたら
「詩です」と言ってきました。
それがこの数ヶ月なぜか詩が気になりはじめたら、ある日こんな詩に出会いました。
「こういう日に君は来たまえ」
太陽のひかりは白くて
ゆうべの雨で黒く濡れた土には
小さな破片のきらきらするような
空気がまぶしい
ふと日陰にはいったり
たまり水に手をつけたりすると
驚く程 つめたいんだ
こういう日に君は来たまえ
にこにこ笑いながら
片足でとんで来たまえ
風は少しつめたいようだが
青い空を流れて行くさりげない雲を
もう一度しゃべりながら 眺めよう
気の早い奴はコートを着たりして
そろそろ校庭を歩き回っているかもしれない
でも君は忘れずに皆のところに来たまえ
背の高い雑木の葉っぱも
まだ茶色に乾きはしない
こういう日にね
「ある日灰色の馬車を降り」
これは「ある日灰色の馬車を降り」という詩集の中にある詩です。
1946年に17歳の林 玉樹という青年が、先に逝ってしまった級友に宛てた追悼詩です。
ちょうど時期的に家を巣立つ息子がいるので感情が被ったのか、
昔からずっと戦争で散っていった若い命を悲しんでいるせいなのか
この詩を読んだ時、泣きそうになりました。
この詩で追悼されている友は、戦争に出向いて亡くなったのでありませんが、戦時下の学徒勤労で極度の労働を強いられた末の病死です。
まだ14、15歳の若者達ですね。
私は戦争を知らない世代です。直接祖父や祖母から戦争の実体験を聞いた記憶もありませんが、かなり子供の頃から戦争や制圧によって人が死んでしまう事に相当の恐怖と悲しみを感じてきました。
この淡々と友に語られる言葉の中に、まだ経験していないその先の苦労を知らぬ事や、戦争時代を真ん中であるけれど捨てぬ希望も両方感じます。
作者にはこのように病気や戦争によって相当の死と直面してきたと思われる少しの命運感のようなものもあるのでしょう。
しかし逆に感情に揺さぶられずに叫びも聞こえない語り口が、一層心に突き刺さります。
彼らが暮らしの中で奪われたものは一体なんだったのか、私には薄い想像しかできませんが。
このタイトルだからこそ、の詩
他の今の言葉で言い変えてみたらどうだろう。
「こんな日に戻っておいで」
「こういう日に帰ってきなさい」
「こんな日に来るといいよ」
どれも違う。
「こんな日に君は来たまえ」という語り方の中に
若さ、学生らしさ、未来、希望、潔さ、凛々しさ、そういうものが一気に伝わってくるのでしょう。
タイトルがすごい。どうしてもこの語りでなければならない。
というか、このタイトルだけでやられてしまいました。
私は考えてみましたら、本当は詩が好きなのかも知れない、と。
であるから絵を描く人になったのではないか、と思うのです。
言葉や線や音で表そうとする人。
詩人や絵描きや音楽家。どの人も一場面や物語を人に伝えようとするんですね。何十年も前に自分のwebsiteを作った時、「物語が見えてくるような絵を描きます」と載せていたことを思い出しました。
人が動くことで湧き上がる温度だったり空気だったり。そういう物がどの場所にもどの時間にもあります。人が人と暮らすから家族や友がいる。
どうか世界中の人が、家族や友という大事な人と一緒に過ごせますようにと思います。当たり前の言い方ですが、”豊かに生きていく”には他にはどんな条件もつけられないのです。
慣れてしまう恐怖
この詩の前後に彼等の前途揚々の日々が見えてきます。確実にその場所で過ごした楽しい日々があったはず。
先日ある式典で同じ年ほどの青年が「帰る家があり、いつも食事が用意されていて温かい布団で寝ることができる。そして愉快な仲間と一緒に質の高い学びを受けることができる」と語っていました。
いつの時代もこの当たり前が、”若者の前提”である事が必要です。
昨今の世界情勢の中でこの前提は当たり前のように毎日耳にしますが、私自身この言葉に慣れてはいないだろうか、とこの詩を読んで改めて思いました。
きっと今も世界中のどこかで、逝ってしまった友に「こんな日に戻っておいでよね」と語りかけている青年がいるはず。かつては一緒に過ごした色鮮やかであった地に、です。
そういう実態や言葉に慣れる事が私は恐ろしくてたまりません。
自由でいられる年代
私は運も時代も良く、彩り豊かな青春時代を過ごしました。それは裕福という意味ではなく、夢や希望を思い抱くには十分に平和であったという事です。
平和であり、自由でもありました。両親から沢山の愛情と応援をもらいながら、色や音に囲まれた若い時代でありました。
現在のようにネットも情報もなかった時代でしたが、逆に今よりもっと色豊かで大きな思考を持つことができたと思います。
誰にもどんな蒼か決めつけられない。どんな音なのかを制限されない。私だけの蒼であったり、音であったりが私の若い時代を支え、未来へと運んでくれたのです。
頭の中で自由な世界を創りあげられる事だけが、若者がその先へと進むことができる原動力です。
この詩集、国会図書館にあるようですが現在デジタル化のために閲覧不可、とのこと。来年の夏まで待たねばならないようです。
この作者の他の詩と言葉も楽しみに1年待ちます。
「こういう日に君は来たまえ」と言ってもらえるその日は、どんな日になるのかな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
