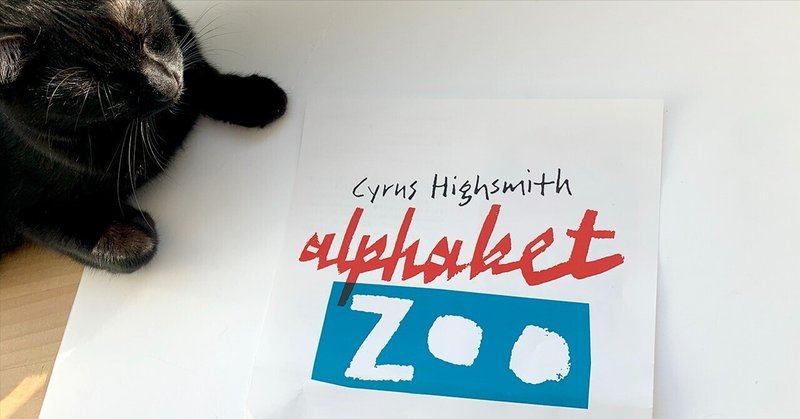
絵であり文字であり | サイラス・ハイスミス展
ある日インスタを開いたら、突然飛び込んできた「サイラス・ハイスミス展」日本初の開催!の投稿。
日本で個展をやってくれるんですか?!と、次の日ギャラリーに大興奮で駆けつけました。
サイラス・ハイスミス氏(Cyrus Highsmith)は、著名なタイポグラフィーデザイナー・イラストレーター・作家であり、講師でもあります。長年ボストンのFont Bureauでデザイナーとして仕事をされて、2017年からモリサワの欧文書体部門でクリエイティブ・ディレクターを務められています。
私はこの人の大・大・大ファンで、私のPinterestのボードは彼の作品で溢れかえっています。
作品はどれもシンプルな構図とかわいさとユーモアに溢れています。且つグラフィカルであり、どこまでも優しく温かみを感じるライン。


日本の子供向け絵本も手掛けていらっしゃるので、日本のお子さんにも大人気です。どの動物も本当に可愛いのですが、私は怪獣シリーズが大好き。
ウルトラマンの切り絵風の絵も有名ですし、子供の目というものを本当に理解されて好きなんだろうなあ、と思います。

ひらがなを勉強する、というコンセプトで作られた「あり いぬ うさぎ」はハイスミス氏がイラストを描かれています。
逆に日本語に精通していない彼の文字とイラストの表現は、これから”ひらがな”という、日本語の8割を占める大事な文字を覚えていくお子さんの心と眼にダイレクトに響くと思います。

ご本人、数日在廊されておられたので少しお話を聞く時間もありました。
とても飄々としていらっしゃる方で、物腰も柔らかく、なるほどこういう人だからあんなにソフトな作品が出来上がるんだなあ、と思いました。
絵と一体感のある絶妙なフォント。どこまでが文字でどこまでが絵なのか、ボーダーレスに見えるその手法をずっと知りたいと思っていました。
「文字としての型、絵としての型、切り込み方のパターンみたいなものがあるんですか?」と伺ってみました。
ハイスミス氏は、文字・絵と別々に考えるという事を特に意識はしていらっしゃらない、との事。
彼にとって全ては "Shape"であり、作るものの対象を考える事が先。
そのものによって文字も絵も自ずと紙の上で統合されて形になるのだそうです。
そして「とにかくスケッチが全て、です」とおっしゃっていました。
ご自身も常にスケッチブックとペンを持ち歩き、いつでもどこでもスケッチをしているそうで、今描こうとしているものを誰が見るのか、読むのか、をいつも頭に置いておられるそう。
ペンケースの中は愛用のペンが沢山。”描く”ことは仕事なのか、暮らしなのか。

また。基本はカリグラフィーです、ともおっしゃっていました。
私も実際にカリグラフィーも何度かやりましたが、実際のカリグラフィーにライン・ルールの影響を強く受けすぎないだろうか?と思うのですが、ハイスミス氏の作品からは、そのような規制や縛りを感じる事はありません。
でもこの本を読むとそんな疑問は一発で解消されます。
ハイスミス氏が美大生に向けてわかりやすくタイポグラフィーを説明。
手法についてはもちろんなんですが、デザインもイラストも全部素敵!
彼の創る書体のルール、そして何を重要視しているかとても丁寧に説明されています。
日本の書体も大好きなものが色々ありますが、欧文フォントはアルファベットしかない分個性がさまざまで、どんなフォントに一生の中に出会えるかは私の大事な楽しみでもあります。
ハイスミス氏の手掛けた"serge"も大好きな書体の一つです。
前記した、彼の「全ては Shape である」という言葉の意味がよくわかります。線を描くというより、形やその間の空間を描いている。
Negative spaceとPositive spaceの関係ををとても大事にしていらっしゃる。
空間を描く、なんて心がキュンとしてしまう言葉じゃあないですか。
幼少期にお母さんから絵を描くことを教えてもらったハイスミス氏がたどり着いた方法なんですね。
線にとらわれず、形としてものを見て創り出していくことで更に俯瞰で表現できる事は多くなるのでしょう。もっと言うと、”見たもの”という限定された世界ではなくて、”見て消化し落とし込んだ結果”にある自分独自のモノなのだと思います。

先日の棟方志功もピカソも同じ事を言っています。
「見えている事ではなく、心の中にあるものを描く」。
自分の中に落とし込まれるそれは、自分のフィルターを通りどんな形になっているのか、出てきて初めて驚いたり面白かったり。
そして作品を見てもよくわかりますが、一番大事にしていることは、「物語」なのだ、と。
これは僭越ながら私も全く同じで、線も色もそこにStoryはいつも存在します。ただ何も想像もしないで何かを描く、ということは私はほぼありません。物語と音がいつでも伴います。
ハイスミス氏に音の存在についてはお聞きする時間がありませんでしたが、私の勝手な想像で、音も存在しているのだろうと。
でもそれは誰かミュージシャンの音楽というより、自然の音だったり、作品を読み・見ている人達が発している楽しい声だったりするのではないでしょうか。
確かに思います。アウトプットする先には、それを見る人が必ず存在し、その人たちを抜きにして表現する事は難しいです。
しかし考えてみると、絵だけではなく、会話も料理も何もかも。
共通するトピックがあり、言葉を発し、その反応を聞く。
美味しいものを作り、それを食べる人がいる。
全て自分から出たものには受け止める人がいて、その反応をこちらもまた受け止める。何もかも、キャッチボールですね。
良いボールを投げれば相手も取りやすい。単に手法の問題ではなくて大事なのは、”楽しくキャッチボールができる”ということではないでしょうか。
取りにくい球を投げていれば、取る相手も楽しくない。楽しそうにしていない相手にこちらも返したくなくなる。
人と人のコミュニケーションのために人は生き・創造していくのだなあ、と素晴らしい作品や人と出会うと思うのです。
これからもハイスミス氏の素敵な作品を楽しく見て暮らしていきたい。
そして私を幸せにしてくれる世界中の創造する皆さま、ありがとう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
