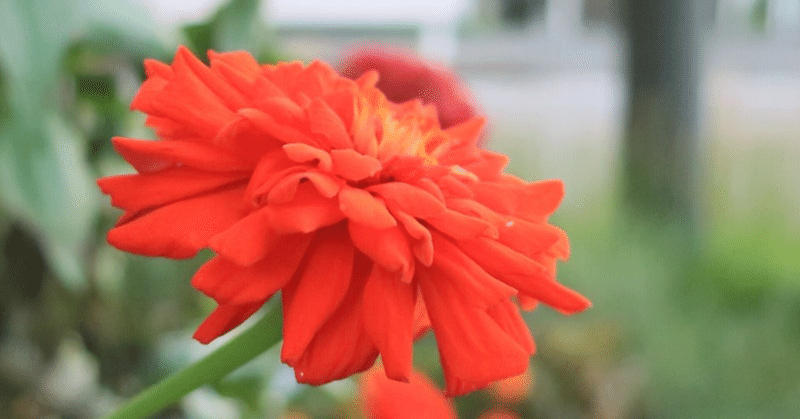
経済対策は需要対策である
構造改革とか成長戦略とかいうのは、供給側の政策である。要するに、今より安く大量に作れるようにする、ということだ。もちろんそれも必要なことだから、全く反対するものではない。
ただ、いくら安く大量に作れるようにしたからと言っても、買う人がいなければ誰も作ろうとしない。需要がなければ、供給が増えるわけがないのだ。
これに対し、金融緩和や財政出動は、需要側の政策である。日銀がお札を印刷して世の中に出し、政府が補助金や給付金でお金を配る。お金が増えれば需要も増えるという訳だ。減税も民間にお金が残るようになるので同じ効果があるし、公共事業で半ば強制的に需要そのものを作ることもある。
自由な資本主義経済だから、需要が増えれば供給は増える。需要側の政策が重要と考える理由である。
イメージとして、経済がいいときと悪いときの状態を描いてみた。

矢印の太さがGDPだと思ってもらえればいい。
経済がいいときは、需要(≒消費)が増えるから給与も増え、給与が増えるから需要も増える。好循環である。逆に悪いときは、需要が減るから給与も減り、給与が減るから需要も減るという悪循環となる。
そこで、経済対策では、お金を配ることで需要を作り出すことを目的とする。

労働者・消費者ではなく企業にお金を出し、設備投資など企業の需要を増やしたり、給与を増やすことで需要を増やす場合もあるが、基本的には同じことだ。
これら経済対策の意味が理解できれば、需要側の対策が重要という意味もわかるのではないか。また、内容よりも規模が大切だということも、イメージとして捉えてもらえれば幸いである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
