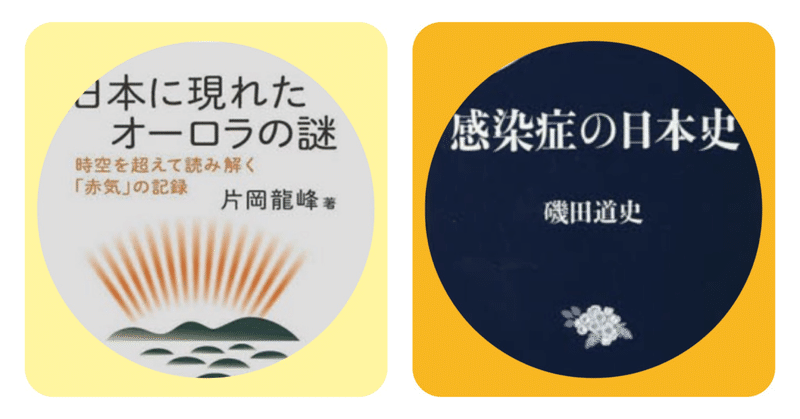
【#読書の記憶から13】時間を遡って×過去から学ぼうぜ
「もう5波だぜ。」
…もちろん新型コロナウイルス感染症の話。
季節をいくつか越えて付き合ってきて、もはや“新型”でもない感じ。「ヤツ」「あれ」と呼ぶくらいラフな感覚で、見えないけれど脅威をもってずっと我々のそばに居る。
そんなコロナウイルス自体にももちろん説教したいけど、感染症対策にも説教したい。
「もう5波だぜ?!」
この1年半、どんな進歩があったのか。
ワクチン接種の動きは大きいけれど、外出自粛の要請と(ことに飲食)店舗の営業制限、基本は第1波の時と変わっていない気がするのだけれど…。
『感染症の日本史』磯田道史
NDC:493.8(ウイルス感染症)
昔むかしの日本も、度々新種の感染症の危機に直面してきた歴史がある。
そして、現在のような最新の医療や研究知識がなかったにもかかわらず、どうにかこうにか危機を乗り越えてきたはず。
そんな過去の場面から、真似て生かすことはできなかったのかなぁ……同じような局面もあったと思うのだけれど……と、読んでいるうちに、悲しい気分になりました。そして何度か本を閉じるほど辛くなりました。
コロナで亡くなった、そして辛い思いをしている方々に。
そして具体策と想像力を欠いたこの国の政策に。
“総合的な知性からの発想が要る問題には、長く・幅広く・時間軸で物事を捉える歴史学を“
本文そのものはたいへん読みやすく、「病気史」とも「医療史」とも異なる、経済や社会状況や無名の人物の暮らしまで含んだ「医療生活史」「患者史」の観点の大切さを感じます。
「我々がやるべきことは、すでに歴史が答えを出していることが多いのかもしれません。」
「複雑に遠くまで及ぶ歴史の因果関係を見破るのが、歴史家の仕事」
かつて日本人が感染症に臨んだ歴史と、磯田先生の切実な言葉が印象的な1冊でした。
もう1冊は、時空を超えて、文理の壁をも越えて。
『日本に現れたオーロラの謎 時空を超えて読み解く『赤気』の記録』片岡龍峰
NDC:451.7(大気中の光・電気・音響現象)⇦面白い分類ですね。
“日本最古のオーロラの記録“を探る本著。
著者は、国立極地研究所というところでオーロラの研究をしている先生です。
研究の対象(今回はオーロラ)はしっかり理系分野だけれど、日本最古の天文記録が残るとされる『日本書紀』から、江戸時代の古書籍『星解』、気象庁保管の写真フィルム資料まで、文系分野の文献も参考に探求を進めていく過程が、興味深く面白い1冊です。
“天(あめ)に赤気(あかきしるし)有り。形雉尾(きぎしのを=キジのしっぽ)に似れり。”『日本書紀』
なぜ赤色なのか、雉の尾の形なのかは本著にて。
科学的見地からの推察と、古文書における記録との繋がりによって日本におけるオーロラの歴史を究明しようとする試みにわくわく。
そして、新しい科学的知見を古いデータや文献から見出すことができた点に大きな喜びと意義をもち、文系分野へも双方向へ(研究によって)貢献していくことへの期待が、熱量をもって述べられています。
“次世代へ記憶をつなぐこと“
“文系・理系の学問の共通点は、事実や真実が端的に記録され語り継がれていく美しさを追求する学問であること。“
時間は進み続ける。でも、時空を越えて過去から新たに知ることの大切さと面白さはいつの時代にも不可欠なのだと感じた2冊でした。
【#つながる読書】
次は…
/
蓄積された時間(歴史)が醸し出す雰囲気がそこに。
\
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
