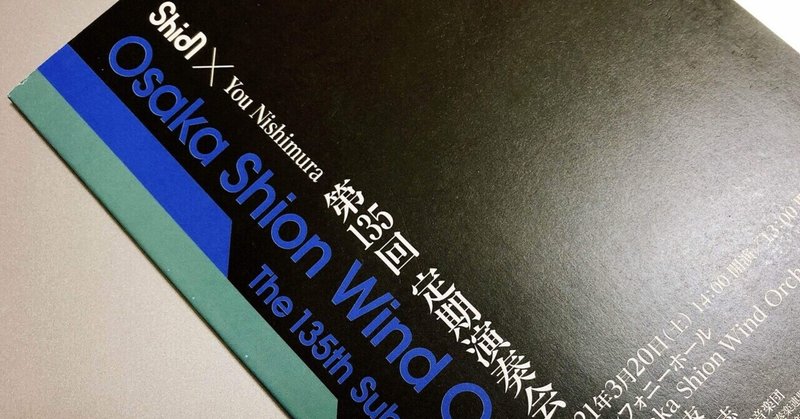
【100年越しの同窓会】Osaka Shion Wind Orchestra 第135回定期演奏会レポート
Osaka Shion Wind Orchestra(以下、シオン)第135回定期演奏会を聴いてきたので感想をつらつらと。
今まではTwitterに連投する形式で書いてましたが、毎回文字制限かからないように書き直すと大変だし読みにくいので、今回はnoteを使って書いてみました。
■コロナ禍での演奏会にあって

シオンの生演奏を聞くのは、2019年4月27日のデメイ氏の自作自演以来、ほぼ2年ぶりという有様。
昨年はコロナ禍に加えて仕事の急用も多く、全く大阪に帰省できない状況だったが、僕の大好きな「中国の不思議な役人」を取り上げる今回の公演は何としても聴きたいと、どうにかスケジュールをこじ開ける事に成功。
無事に鑑賞できたので東京に戻ってから反すうして咀嚼して浮かんだ感想を書いていく。
※なお、「首都圏の緊急事態宣言が解除されていない状態で東京から足を運ぶのはいかがなものか?」という点は悩みましたし、当然批判的なご意見をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、個人での厳重な対策の上、会場での対策にも全面協力の上で鑑賞させていただきました。
■はじめに
本年2月24日に逝去されました元大阪市音楽団楽団長、木村吉宏先生のご冥福をお祈り申し上げます。
私は直接お会いする、演奏を聴く機会には恵まれませんでしたが、
「ニュー・ウィンド・レパートリー」を始め数々の市音(当時)の名録音を夢中になって聴いたのは、かけがえのない青春の1ページであり、私の吹奏楽人生の原点となっております。
シオンはじめコロナ禍の音楽業界はたいへんな苦境にさられておりますが、木村先生が紡いできた吹奏楽の”進化”をたどる本公演を、きっと木村先生は微笑んで聴いてくださったことでしょう。
私はプロの演奏家ではありませんが、立場は違えども木村先生のご遺志を継ぎ、日本の吹奏楽の発展に貢献し続けます。
■プログラミング
2年後にせまったシオン創立100周年を前に、シオンが誕生した1920年代の名曲が集結。
今まであまり意識していなかったけど、V.ウィリアムズやガーシュイン、ラヴェル、バルトークて同年代の作曲家なのか。
2つの大戦のはざまに翻弄されながらも、ウィリアムズはイングランド民謡を、ガーシュウィンはジャズを、ラヴェルはウィンナ・ワルツを、そしてバルトークは舞台音楽を、それぞれが自身の作曲技法と組み合わせ、新しい潮流を生み出していった歴史が見えてくる。
混迷の時代だからこそ、新しい音楽が渇望されたということか。
そして、そんな時代に市民の熱意によって軍楽隊から独立した日本の吹奏楽団が100年近い時を経て、同じ世代の作品を一堂に会して演奏会を開くとは、なんともロマンチックな“同窓会”である。
こういう「面白そう!」と感じる意欲的なプログラミングもシオンの魅力なのだ。
※同窓会というのはあくまで「同年代」というくくりなだけで、実際に面識があったとか。同じ学校で学んだ仲間とか、そういった意味ではありません。念のため。
■レポート
各楽器が程よくブレンドしたシオンサウンドが、シンフォニーホールいっぱいに広がる。
やっぱりこの感覚は、生で聴かないと体験できない。
曲の前にAでチューニングしてる場面ですら、懐かしくて笑みが溢れた。
時代が変わっても、変わらないこの音を僕は観客の立場から守りたいと思った。
・素朴な紳士「イギリス民謡組曲」
本公演1曲目は、V.ウィリアムズの「イギリス民謡組曲」
往年の名曲だけど、近年演奏会で取り上げられる機会が少なくなったような気がする。
民謡だから庶民に親しまれた歌なんだろう。素朴でのどかな風景が広がるが、紳士の国らしく端正でお上品な仕上がり。
・スタイリッシュな暴走列車「ラプソディー・イン・ブルー」
続いてはピアニスト松永貴志氏を迎えての、ガーシュインの代表曲「ラプソディー・イン・ブルー」
※以下、ジャズピアノはからっきし素人の感想なので大目に見てください。
ドラマ「のだめカンタービレ」のメインテーマに採用されて一躍有名になった曲だが、テレビで聞くのは、オーケストラが「ジャ、ジャ、ジャーーン(ドッカーン!)」とド迫力の音を鳴らしつつ、安全運転の”いいこちゃん”な演奏を多く聴いてきた。(てか『のだめ』ってもう15年のドラマなのか、時の流れ早すぎ(汗))
一方本公演は、初演時のビッグバンドに近い、小ぶりな編成でアレンジされており、迫力は控えめだった。
しかし、それは決して”大人しくていい子ちゃん”な演奏というわけでは全く無く、むしろこの人数だからこそ小回りが効いてアグレッシブになっていた。
松永さん、演奏中終始左足をプランプランさせており、第1印象は
「落ち着きのない人やなー」(失礼(笑))
そして印象通り、アゴーギグ(で合ってます?)のオンパレードで、ジェットコースターのごとく揺さぶってくる。
「カチカチカチカチ、メトロノームに合わせて演奏するなんて、性に合わねーよ!」と言わんばかりに、自由奔放にめぐるましくテンポと表情が移ろってゆく。
松永氏のピアノに引っ張られるようにシオンもヒートアップ。
「俺のピアノについて来れるかい?」
「なんの!」
「じゃあこれならどうだ!!」
「まだまだ~!!」
そんな会話が聞こえてきそうだった。
西村氏も前曲とうって変わって、ぴょんぴょん跳ねてルンルンでタクトを振っているのが印象的だった。
コンマスの古賀氏はじめソリストの皆様もブラボー!
アンコールの「神戸」もなんともシャレオツなひととき。
前半で大分お腹いっぱいになった。
・狂乱の舞「ラ・ヴァルス」
休憩を挟んで後半2曲は西村氏直々のアレンジによる大曲2連発。
1発目はラヴェルが生み出した傑作「ラ・ヴァルス」
ヴァルスと言っても某ジブリ映画ではない。
ワルツのフランス語読みだ。
曲の前半、ワルツが立ち現れたかと思ったら、狂騒の不協和音の中でダンスが昇華していく。
さながら、ウィンナワルツの舞踏会と聞いて来てみたら、宮廷で「武闘会」が始まったのか?ってくらいの変貌ぶりである(え、そのギャグ寒いって?大目に見てください笑)。
この狂しさがクセになる。
・クラシック界のR指定「組曲『中国の不思議な役人』」
そして演奏会のトリは、一番のお目当て「組曲『中国の不思議な役人』」。
僕のお気に入りの演奏は、2005年の全日本吹奏楽コンクール一般の部(当時)での創価学会関西吹奏楽団による演奏。
確かその年の1位金賞と記憶しているが、超骨太なド迫力のサウンドに釘付けになった。今も吹奏楽を続けているのはこの演奏の出会いも大きかったりする。
そんな思い出の曲がシオンと同世代だったとは、不思議な縁を感じる。
ところでこの曲、ストーリーがグロテスクすぎて、初演時も大顰蹙を買ったのだが、現代でも、とても中高生に聞かせられる内容ではない。
大ヒット公開中の劇場版「鬼滅の刃」で「首が吹っ飛ぶシーンがグロくて娘に見せたくなかった」とかいう会社の上司がいたが、そんな生易しいものではない。
なんてったって役人は「殺しても死なずに少女を追いかけ回す」んだから。
現代に映画化したらR18指定間違いなしである。
そんな曲が、上記の創価学会関西吹奏楽団はじめ、吹奏楽コンクールではよく演奏されている。
やっぱり、作品の持つ”エネルギー”に惹きつけられるのだろうか。
愛を渇望する役人の人ならざるエネルギーと、それを表現しきったバルトークの作曲技法の融合が、この傑作の誕生につながったのなら、道徳不道徳はさておき、とても幸運なことだと思う。
そんな役人をシオンが取り上げるのは、僕の記憶が正しければ第95回定期以来、約14年ぶり。
当時は森田一浩氏による編曲で、故・小松一彦氏が大阪市音楽団首席客演指揮者に就任して初の演奏会で披露された。
この時、”少女の踊り”が29小節カットされてしまったのだが、今回の西村版はその29小節も含めた完全版だった。
さて前置きが長くなったが演奏はというと、冒頭、我らが石井楽団長の”クラクション”が響き渡る。
(ちなみに僕が中学生時代、石井先生が学校までレッスンに来てくださってました。当時は市音の新人でいらしたのに今や楽団長ですよ。いや本当にお懐かしい。。。)
ニューヨーク・フィルのJ.アレッシとかブラック・ダイク・バンドのB.ベイカーとかが好きなトロンボーン吹きからすると、シオンのトロンボーンはやや大人しめな印象があったけど、
石井先生のパワー全開の”クラクション”はまさに
「キターーー!」
という状態。
もう既に勝った。これだけで今日聴きに来た甲斐があったというものだ。
演奏中、指揮の西村氏が"少女"になったり、"老人"になったり、"少年"になったり、そして"役人"になったりと、まるで”一人パントマイム”を見ているような錯覚におちいった。
あと、トロンボーントップの方(山田さん?存じ上げないエキストラの方でした)は前半ずっと休みなのが気になっていたが、役人の登場シーンから参戦。1stを2本にして役人のキャラクターをより強調する演出だろうか。
温存していただけあって、終盤のハイトーンも落ち込まずにクライマックスまで駆け抜けられていた。
実に濃厚な音楽絵巻を堪能させてもらった。
トロンボーンの皆様、そして全パートブラボー!!
■最後に~音楽は心の栄養
本編終了後、西村氏が叫んだ。
「誰かが言った。音楽は不要不急だと。冗っっっっっ談じゃない!!!」
「音楽で飢えはしのげないけど、間違いなく、心の栄養になる!!!」
よくぞ言ってくださいました。
アンコールは「海の歌」
もともとイギリス民謡組曲の2楽章として作曲され、後に単独のマーチになった曲。ウィリアムズに始まりウィリアムズに終わるとは、こういう粋なプログラミング、本当に好き。
シオンの皆様、心の栄養、補給させていただきました。ありがとう。
今年はあと何回聴きに来れるかな?
とりあえず9月の玉木優さんとの公演は絶対に空けたい。
最後までお付き合いくださった方は、ありがとうございました!
よろしければサポートお願いします
