
採用広報チーム立ち上げストーリー~「大変…でも候補者に“想い”を伝えたい!」~後編
みなさんこんにちは。
くふうカンパニー人事の池森です!
今回は人事の皆さん必見!
採用広報の立ち上げストーリーの後編になります。
くふう住まいでは採用広報を通じて候補者様に情報を届けられるようになったとのこと。
どのような想いで採用広報に取り組まれてきたのかを
くふうカンパニーの人事部 採用広報チームの3名(くふう住まい担当-清水さん・山根さん・小西さん)にお聞きしました。
ぜひご覧ください!
前編では記事の作成方法についてお伝えしています。前編はこちら↓

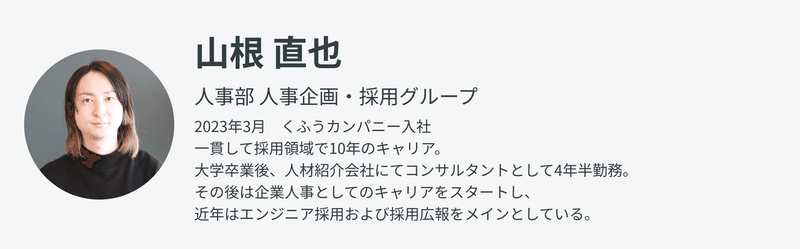

くふう住まい 採用広報活動奮闘記①:採用広報チームメンバーの想い
最初に決めたのは「読者の方にどのような感情を抱いてほしいか」というゴール
-清水
採用広報を始める前に、まず全員で話し合ったのは記事を出した後の「ゴール」です。
以下がその際のメモになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
"SUCCESS IMAGE
住宅=固い・きつい・古いのイメージ(不動産業界のイメージの悪さを払拭したい。to不動産の営業もあまりよくない)
"達成した時に見える風景"
「くふう住まいってこんな会社なんだ。求人サイトで見て気になってたけど、やっぱり応募してみよう」
"HIGHLIGHT"
スポットライトが当たるシーン
"キーアクション"
求職者の知りたいさまざまな分野の情報が掲載されていて、ページを見る手が止まらない。
その時に与えたい感情は「ワクワク」と「安心感」
例)
社員インタビュー「こんな人がいるのか、一緒に働いてみたい」
福利厚生「給与や休日のこともイメージができる、家族とも相談しやすい」
社内の様子「フルリモートでも交流できそう/オフィスおしゃれ」
仕事「1日の自分の様子がイメージできて安心」
それぞれの記事でポジティブな気付きを積み重ねる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
くふう住まいは、2023年4月にくふうカンパニーグループの株式会社しずおかオンラインより、同社が運営するローカルの住まい情報メディア「イエタテ」及び家づくりの相談窓口「イエタテ相談カウンター」等の住まい関連事業を承継しました。
そこで、最初に記事として出すテーマは経営陣へのインタビューにしようと決めました。
新生・くふう住まいとして役員一人ひとりの色を際立たせた記事を作り、候補者の方には事業内容だけでなくこれまでの歴史や経営陣の考えなどにフォーカスしたいと考えました。
事業内容だけでなくこれまでの歴史、住宅業界においてくふう住まいが目指す世界、それを実現するための経営理念や事業戦略などにフォーカスし、候補者の方により理解を深めていただき「くふう住まいについて、もっと話を聞いてみたい」という気持ちになってもらいたいと考えたからです。
今読み返してみても、最初に掲げたゴールには一定到達しているんじゃないかな、と感じています。
【代表の長井×取締役の坂本 対談】
"住まいにまつわる後悔をなくす" 強みの異なる2事業の協同で、さらなる成長拡大へ
新生・くふう住まい全体の話の後はその後はメンバーインタビューやイベント記事を中心に構成しています。
現在のように note を活用して採用広報を行う以前はホームページの情報と面談や面接で話す内容のみでした。
他にも情報を発信する手法はありましたが、例えば採用媒体だと誌面の大きさ的にも伝えきれなかったり、人材紹介会社経由だと第三者の言葉を介して候補者の方に伝わります。
その点、採用広報は候補者の方にダイレクトに私たち自身を伝えることができると考えています。
くふう住まいは明確に成長を目指しており、とても面白いフェーズです。
くふう住まいの事業の現状ですが、例えば、注文住宅情報メディアとカウンター事業の「イエタテ」が前年比144%で成長中など、くふうカンパニーの IR でも発表した「5年後の住宅関連施工取り扱い件数 No.1」を目指す中で堅調に推移している状況です。
物価が上がる中でも「安くて良い家を買いたい」と思うユーザー様は多く、そんな時にくふう住まいであれば地域密着の工務店やリノベーションを主とした企業様とユーザー様のマッチングに強いという特色が好意的に受け入れられている表れといえるでしょう。
ただ、今後もマーケットは変化していくと思いますので、今の体制のまま同じことを繰り返していたら、目標とするステージには到達できないかもしれません。
それゆえ、現場も手探りで組織改革や業務効率化など、目標達成に向けて様々なことに柔軟に取り組んでいます。
「こうすれば必ず成功する」という正解はありませんので、試行錯誤しながら日々奮闘しています。
だからこそ現場の声もいいものはどんどん取り入れられる環境、そんな雰囲気が伝えられるような記事を届けていきたいです。

くふう住まい 採用広報活動奮闘記②:くふう住まいの熱いメンバーの想い
-山根
私は基本的にエンジニアリングの話やイベントで出たテック系の話を中心に記事を書いています。
CTO の大川さんとは元々採用担当として求人票の作成などでお話はしていましたが、今回の記事を通じて改めて「どんな想いでくふう住まいで仕事をしているのか」という点を深堀できました。
【CTO 大川 インタビュー】
ユーザーの悩みを解消し、サービスを進化させる ― CTO の使命とチャレンジ
例えば、大川さんが「ユーザーファースト※」なプロダクトづくりに向き合うきっかけ、そしてそれを実現するためにどのような行動をしているのかが線でつながっていく様子が分かります。
また、「ユーザーファースト」な世界観を実現するために大川さんがされた行動が、社内に良い影響を与え周囲が変わっていく様子を伺いました。
それらをお聞きしていくうちに、「ユーザーファースト」という言葉はただのメッセージではなくて、想いの連鎖によって形成された文化なのだということに気付かされました。
※ "ユーザーファースト" とはグループが掲げる Value(大切にしたい価値)です
また、採用広報のヒアリングを通じて、人となりだけではなく開発組織の文化にも触れることができました。
くふう住まいはくふうカンパニーグループの中でも特に組織全体でAI活用を推進しています。
その文化はエンジニアだけのものではありません。
非エンジニアの方(ビジネスサイド)を主体に AI を活用してやりたいことを提案し、それをエンジニアが機能として開発して形にしています。
そのため、社内全体で AI の業務利用が活性化しているのです。
例えばメディア編集の自動化を ChatGPT が行っていますが、なんとこちらは2023年4月新卒入社の楢木(ならき)さんが開発したものなんです。
このような取組から、くふう住まいはくふうカンパニーグループの全社会で「テクノロジストMVP ※」という賞も受賞しています。
※テクノロジストMVP とはグループでの年に1度のアワード表彰で送られる賞のことです。
採用広報の面白いところは、普段候補者の方が面接の場では接しない現場の方がどんな想いでどんな工夫をしているかを伝えられる場である、という点と考えています。
つまり、体外的に現場メンバーが日の目を浴びることのできる場所だと考えています。
会社を支えているメンバー一人ひとりが、ただ業務を行っているわけではなく、自分なりの想いを持っていたり、良くも悪くも腹を割って話してくれた内容を世に出せることが面白いと感じます。
私としては、普段の選考フローでは見られないような中身を発信していきたいです。
くふう住まい 採用広報活動奮闘記③:それぞれが持つ “熱” をカタチにした、デザインへの想い
-小西
くふう住まいの note はデザイナーさんとの連携も欠かせません!
まず note を立ち上げるにあたり、note 全体のデザインからサムネイメージまでを数パターン作成していただき、採用担当チームで検討し、現在の姿となりました。
【当時のやりとり】

①バナー、トップ画像
デザインの意図としてはコーポレートカラーである水色を基調としたものに加えて
風通しのよさ
若さ
ITの分野で事業を進めている
ユーザーに密着している(エリア問わず)
スピード感
というイメージを与えるものがいいなと考えていました。
最初はコーポレートカラーでもある「青」を基調としたものを作成していただいたのですが、
「なんだかかっこよすぎる?」
「温かみが感じられないかもしれない」
「もっと地域に寄り添ったイメージを出したい」
という意見があり、採用広報チームとデザイナーさんとで話し合いを重ね、以下のデザインで決着しました。
新しいデザインには
町の暮らしに紐づいているサービスだというメッセージ
町の様子
人へのよりそい×青のコーポレートカラーかつIT感
という想いを込めています。

②こだわりのサムネイル
(1)写真を使用しない場合

はじめは背景にある町の様子だけにしていたのですが、「生活の中にあるサービス」という意味を伝えたく、手前の人のイラストを追加していただきました。 これで地域密着という印象も読者の方に与えることができると考えています。
(2)写真を使用する場合

インタビュー記事の場合はX等でサムネイルが出たときに「誰」の「どのような」記事なのかを明確にわかるようにタイトルや文字の配置にもこだわっています。
記事が埋もれては意味がないので、せっかくなら全ての方に読んでいただきたいのでできるだけ「目に留まるように」という想いから細部まで気を配っています。
最後に・・・
-小西
面接に来ていただいた候補者の方から「note を読みました!」と何度も言われるようになりました。
記事を読んでいただいた上で、考えに共感して応募してくれたとのことでした。
更に面接でも「note で〇〇と仰ってましたが…」と、我々の想いを知った上で質問をしていただくことが多くなり、改めて候補者の方に「想いを届けられている」のだという気持ちになります。
私が記事を作成する時にいつも感じることがあります。
それはくふう住まいのどなたにお聞きしても会社のカラーや大切にしている価値観が同じだということです。
「徹底的なユーザーファースト」で「今後も事業を成長させていく」という気概を持っている方の集まりなので、これからも記事を通じて様々な切り口でくふう住まいの良さを伝え、同じ想いをお持ちの方に知っていただけるような記事を書いていきたいです!
今回は株式会社くふう住まいの採用広報チームにお話を伺いました!
くふうカンパニーでは一緒に働いてくださる仲間を募集しています。
一度お話を聞いてみたいという方はぜひご連絡ください!
