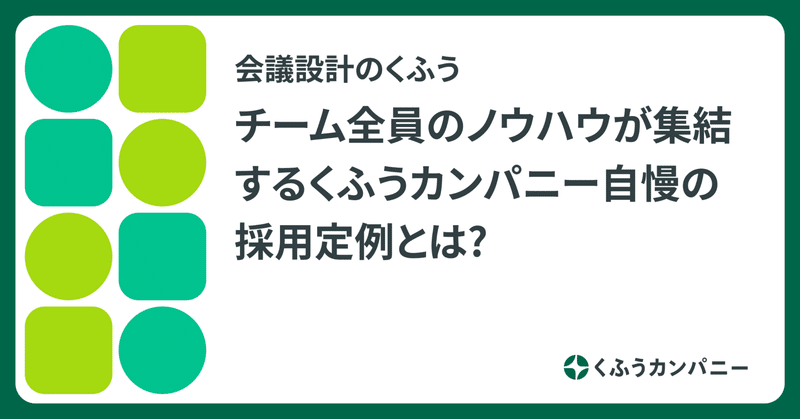
チーム全員のノウハウが集結するくふうカンパニー自慢の採用定例とは?
みなさんこんにちは。
くふうカンパニー人事の池森です!

突然ではございますが…
「約3%」
こちらは何を表した数字だと思いますか?
実はこちらは新卒エンジニア採用におけるくふうカンパニーの認知度なのだそうです。
※採用チームの新卒エンジニア採用担当、森田さん調べです。
一見、3%と聞くと非常に少ない数字のように思えますが、なんと2024年4月には8名ほどの新卒エンジニアが入社してくれました。
この認知度をどのようにひっくり返し、採用に繋げたのか…気になりますよね?
私たちくふうカンパニーの採用チームは、このように自分の採用におけるノウハウを週に1度採用定例という会議で発表しあっています。
様々な話題が提供されるので色々な質問や感想が出て、会議は大盛り上がり。あっという間の1時間を過ごします。
しかし、ほんの半年前までは、実はとても静かな採用定例だったのです。
ではなぜこのような会議へと変化したのでしょうか?
今回はこの定例会議の変化についてお伝えしたいと思います。
これまでの採用定例は非常に静かであった
はじめに、くふうカンパニーは各グループ内事業会社の経営支援機能を有した企業です。
一般的な事業会社と若干異なり、コーポレート部門に関しては各事業会社への業務支援という形で業務を行っています。
人事-採用部門においては人事メンバーが各事業会社の採用を担当しています。
例えば、AさんはくふうAIスタジオのエンジニア中途採用を担当、Bさんはくふう住まいの中途採用を担当、というような形になっています。
他にもロコガイド、エニマリ、しずおかオンライン、くふうカンパニーで行っている新卒採用などそれぞれを各メンバーが担当しています。
これまでの採用定例では、
各担当者が自分の担当している会社の1週間分の採用進捗などを報告し、困っていることがあれば相談。
参加しているメンバーはその報告に対して気になることを質問する
という形式で情報共有を行っていました。
持ち時間は一人あたり5-10分程度です。
議論や質問がなかったわけではありませんでしたが、なんとなく上辺を撫でているような、そんな報告が毎週繰り返されていました。
「採用定例はこのままで本当に良いのだろうか?」
実は人事部長の岩森さんも少し前から同じことを仰られていて、時同じくして同じ採用チームの山根さんも同じ想いを抱えていたことを知りました。
もう3人が同じ考えを持っているのであれば、この採用定例の方法を変えるしか道はない!ということでそこから話が進み、
それでは採用定例の形態を変えてみたらよいのではないか?
という話に発展したので、私たちがこれまでの採用定例に参加して思っていたことを整理してみました。
担当している事業会社のことはわかるが、それ以外の深い情報を知らないため、質問しようにも前提がわからない
例)「今なぜその施策をやっているのか?」と聞きたくても、前提がわからないため意味のない質問になりそう
1時間で採用メンバー6名の報告を行わなければいけないので、あまり突っ込んで前提を確認している時間もない
自分の報告が終了したら、正直そのまま黙っていても会議をやり過ごせてしまう
一方的な情報伝達の場となっており、「情報交換」にはなっていない
定例会議が終わった後、全員が全員、ふわっとした状態になっているのでは?
では、理想の採用定例とは何だろう…?
「この1時間を意味のあるものにしたい」、そう思い採用定例自体のやり方を試しにガラっと変えてみようということになりました。
まずは「この場をどういうものにしたいか?」という理想像が必要です。
せっかく6名も採用担当がいるので、各々の知見を出しあって課題解決のための施策話し合いの場にしたい
全員がその場で考え発言できる、議論が活性するような会議にしたい
活気と情報に溢れる1時間にしたいというのが私たちの意見でした。

気の済むまで話し合うことができる採用定例にしたい!
理想の状態にするには、会議自体を報告会ではなく、「課題解決のための施策」を話し合う場にした方が良いと考えました。
そのためには最初の課題部分にも記載した
「担当している事業会社のことはわかるが、それ以外の深い情報を知らないため、質問しようにも前提がわからない」
という状態を払拭しなければいけません。
そのための施策として、まずは6名の報告で1時間を使用するのではなく、
輪番制にし、毎週1社(※)、議論が延長しそうな場合は翌週も使用し、気の済むまで話し合う
という形にしてみたらどうだろう、と時間の使い方を変えることにしました。
※1人で1社担当していることもあれば、複数名で1社を担当することもあるため、担当者ごとではなく事業会社ごとでの発表という前提です。
採用チーム全員が同じ粒度・同じレベルで他社を理解し、採用担当者が知る生の情報を全員で共有して初めて議論になると考えたからです。
更に、その際のテーマをメンバーにまかせっきりにするのではなく、あえてテーマを決め、全社の担当分が1周するまで同じテーマで発表・報告・相談し合うことにしました。
同じテーマで行う理由は、全員の理解度が同じ粒度・同じスピードで向上することを目的としています。
部長の岩森さんに提案したところ、「まずはやってみよう!」ということで運営を任せてくださり、非常にスムーズに会議形態を変更することができました。
柔軟に対応いただけるのがくふうカンパニーの良いところでもあります。
新しい「採用定例」は活発な議論と有益な情報交換の場に見事変化!
最初に選んだテーマは「各社を知る」ということで、担当している企業について改めて全員に発表することからスタートしました。
自分の担当している企業における
採用職種
具体的な採用課題
組織課題
現在採用成功に向けて取り組んでいること
ただし、気軽に参加してほしいので、あえて発表スタイルのフォーマットの指定などはせず、各々自由な様式で自由に発言してもらうようにしました。
実際に定例の形式を変更してみて感じているのは、参加者・発表者の双方にメリットがあるということです。
参加者のメリットは当初の目的通り、今まで上辺だけの情報しか知らなかった部分から実際の担当者から聞くことで深い情報を得ることができ、全員が同じ情報を持ったうえで課題解決策へのアドバイスや前職からの経験談を共有することができたという点です。
また、そのため議論も活発になり、黙っている人がいない状態を作ることができました。
更に発表者は、その日のために情報を精査し準備をすることで企業の採用課題についての棚卸をすることができます。
日々の業務の中で自分の担当企業について整理する機会は少なく、棚卸する中で「次にやるべき施策はコレだな」と浮かぶこともありました。
ちなみに、その後は
・第一四半期を振り返る
・自分のとっておきの求人票を紹介する
・候補者様を選進捗管理
というテーマで進めています。
最後に
今までは壁打ち相手がマネジメント層に集中している状態でしたが、
「何かあれば採用定例でも相談してみよう」
という気持ちがメンバー内にも生まれているのではと感じています。
全く異なる業種・職種を担当している採用チームですが、そのおかげで様々な情報の交換ができ、採用担当一人ひとりのスキルアップにも繋がっていく、そんな採用定例を今後も続けていきたいと考えています。
くふうカンパニーでは一緒に働いてくださる仲間を募集しています。
一度お話を聞いてみたいという方はぜひご連絡ください!
