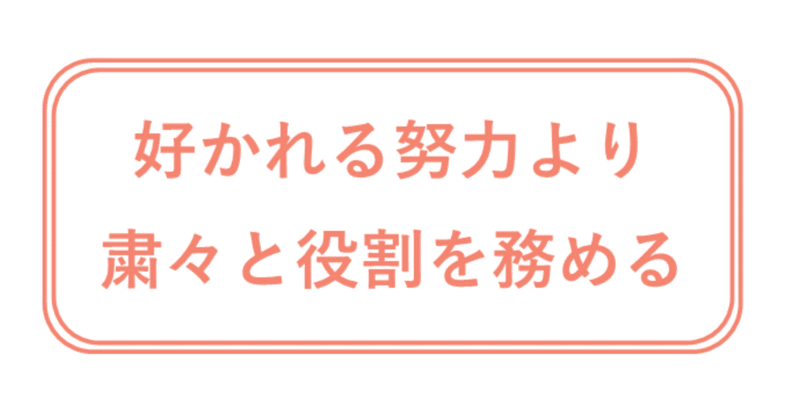
無理に「好かれる努力」なんてする必要はない
■ 生きているかぎり人間関係から逃れられない
介護サービスとは、高齢者とマンツーマンに関わる仕事である。
どの仕事でも他人と関わることにはなるが、介護においてはご本人の心身の状態や家庭環境に足を踏み入れることから、直接的にも間接的にも、利用者とのコミュニケーションおよび人間関係は避けて通れない。
さらに、利用者のご家族との関わりもあるし、職場の上司や同僚などの関わりも加わることから、人間関係に精神的負担を強いられることがある。
その結果、介護の仕事を辞めるということになる。実際、介護職を辞めた理由として「人間関係」が上位にきている。
もちろん、人間関係というのは介護に限った話ではない。営業職だって接客業だって配達業だって、何の仕事においても他者との関りは。個人事業であっても、結局はお客さんやユーザといった他者がいて成立する。
生きている限り、私たちは人間関係から逃れられない。だからこそ、人間関係に悩みながらも、他者との関わりをやりくりしていかなければ苦しい人生になってしまう。
■ 「嫌われている」かどうかは確認しようがない
さて、介護の仕事に話を戻そう。
私の身近にも、介護の仕事において人間関係に悩んでいる介護職員は多い。その1つに「利用者から嫌われている」「利用者から嫌われるのが怖い」というものがある。
利用者というのは、お客さんである高齢者のことである。高齢者に介護サービスを提供しているとき、あるいはサービス提供前後に「嫌われる」というワードが頭をよぎるのだろう。
これは分からないまでもない。何なら介護の仕事どころか、学生さんでもご近所付き合いでもある話でもある。
しかし、相手が本当に嫌っているのかどうかは分からない。それを高齢者本人に聞いたところで、本当のことを言ってくれるかは微妙だ。
介護サービスでも当然ながら苦情受付はあるが、例えば介護事業者が利用者たる高齢者に対して、「スタッフの●●はどうですか?」と聞いたところで、よほど目に余ることがない限りは「問題ありませんよ」という無難な返答で終わる。
ご存知の方も多いと思うが、苦情というのは大きな問題から比較すると氷山の一角である。それはお客さんやユーザは不満を抱いてもモノの購入やサービス利用をやめるだけで留まるからだ。わざわざ、時間と感情を費やして苦情を言うなんて面倒なことはしないのだ。
また、介護において言えば、介護サービスを利用している高齢者は「介護をしてもらっているのに、不満を言うなんてできない」という後ろめたさもある。
このようなこともあり、特定の介護職員が利用者から「嫌われている」かどうかなんて確認しようがないと思ったほうが良い。
つまり、「利用者の〇〇さんから嫌われているかも・・・」と思ったとしても確認しようがないのだから、気にするだけ時間の無駄であると割り切ったほうが良いのだ。
■ 「好かれる努力」は逆効果
とは言え、なかなか割り切れるものでないのが人間である。そんな簡単に割り切れたら人間関係に悩む人は少なくなるはずだ。
嫌われているかもという不安を抱えるのもまた、人間関係を抱える人間が生きるということなのかもしれない。
しかし、問題なのは「嫌われているかも」という不快感に耐え切れなくなり、「嫌われないようにしなければ」と考え始める。
そして、嫌われないために「好かれる努力」を始めることになる。
明らかに何かのハウツー本を参考にしたり、テクニック的なことを表面的になぞらえて「自分は良い人だよ」「自分は楽しい人だよ」みたいな言動を一生懸命に行う。
「何とかして早く利用者に好かれなければ、介護の仕事に支障が出る」という気持ちはわかるが、焦りすぎだと思う。
「好かれる努力」をする人は、失礼ながら必死過ぎて”痛い”。あまりに必死過ぎると、特に介護を受ける高齢者は引いてしまうこともある。
高齢者が引いてしまうと余計に距離が生まれてしまい、それがまた人間関係で悩みがちな介護職員が「これだけ頑張っても、まだ利用者の〇〇さんから嫌われている気がする・・・」となる。
嫌われていることを気にして、嫌われないようにと「好かれる努力」をしているのに、その努力によって利用者たる高齢者との関係性に影響が出るという悪循環。
もはや、「好かれる努力」なんてやめたほうが良いのだ。
■ 好かれなくても仕事はできる
では、どうすれば良いのか?
まずは「好かれる努力」をやめよう。
介護の仕事は確かに人間同士であるが、別に人気商売というほどではない。
確かに「ヘルパーの✕✕さんに来て欲しい」など”選ばれる”介護スタッフはいるが、ご指名がなければ介護サービスの仕事はできないわけではない。
高齢者だって人間なのでお気に入りの人はいるだろうし、好き嫌いはあるだろうが、「スタッフの✕✕さんでなければ駄目だ!!」なんて言っていたら、その人が勤務日でなければその利用者は放置せざるを得ない。
まあ、そのような困った利用者は少なからずいるが、「今日は✕✕さんはお休みの日ですよ」と他職員が伝えて「出てこい!」なんて言うことはほとんどない。大抵の場合は「仕方ないね」という感じで終わる。
結局は、利用者にとってお気に入りの介護職員がいることと、介護サービスを受けるということは話が異なるのだ。
つまり、その利用者から好かれていなくても、介護の仕事はできるのだ。
極論を言えば、客観的に関わり方に問題なく、介助手順も事業所の指示どおりに行えていれば、利用者から嫌われていても介護サービスは提供できる。
相手に不快感を与えたくないという気持ちは大切だが、無理に「好かれる努力」をして疲弊するよりも、利用者たる高齢者のために自立支援に基づいた介護サービスを粛々と行うことも、プロフェッショナルである。
それでも「スタッフの△△という人は駄目だ!」と出禁をくらったならば、ショックかもしれないが、「こういうお客さんもいる」と1つの経験と考えて、一方で自分のことを受け入れてくれる他の利用者さんに注力すればいいだけの話だ。
受け入れてくれない人もいれば、ちゃんと受け入れてくれる人もいる。
そのことにもちゃんと目を向けることも大切である。
――― 介護職は、ある意味でアイドルのようなものかもしれない。
自分を覚えてもらうところから始まり、そこから好き(推し)になってもらい、ご指名を受けることができれば仕事として潤いが保たれる。
しかし、1人の人間に対して誰もが「好き」となるわけでない。そんな神様のような世の中は少し異常だと面う。
だからこそ、「嫌われているかも」と思ったとしても、それが相手からの態度や言動としてだけで確証がなければ、粛々と介護サービスに専念すればいいのだ。
無理に「好かれる努力」なんてする必要はない。
プロフェッショナルとして、どの利用者にも平等に、一方で個々に合った対応をするだけである。
ここまで読んでいただき、感謝。
途中で読むのをやめた方へも、感謝。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
